【井中優治の農家コラム 第1回】農業の抱える悩みを解決する分業化モデル「株式会社収穫祭」創業に至るまで
福岡県京都郡みやこ町で農業を始めて6年経ちました。井中優治(イチュウユウジ)と言います。
年号の変わり目を機に「株式会社収穫祭」という会社を新規創業しました。生産・流通と双方を手がけることで「農業の1.5次産業化」を促す、新業態ベンチャー企業を目指した組織作りを模索しています。
今回、「SMART AGRI」でのSNSのライター募集に応募し、自分の農業への関わりや会社設立に関して、コラムを執筆させていただくことになりました。
その後帰国してからは、そのまま農業を始めるのではなく、一度社会を知るためできる限り多くの社長へ会える広告営業の仕事に就こうと考え、広告代理店へ就職、社会人キャリアを重ねました。
その後、結婚を機に脱サラ。広告代理店時代に培った「プロモーション」「マーケティング」「営業力」の3つを武器にして、福岡県京都郡みやこ町で農業をスタートしました。
皆がつくっているものと同じものでは競争相手が多く取引先の拡大は見込めず、希少性だけでは、経営の柱になるほどには販売できない。スーパーの店員さんや市場の仲買人さんへのヒアリングを重ねながら市場調査を行い、農水省のデータや市況を見ながら作物を絞っていきました。
トマトの販売量が売り場では減少傾向にあり、生産が大玉からミニトマトへ移りアイテム数は増加している、規模拡大などで生産量が増えている事などからちょっとしたブームが来ている事などを市場調査でつかんだことで、一つの予測を立てました。
「この先、ブームは落ち着き生食需要の減少やコアターゲットの高齢化でトマトの販売量がさらに減っていくだろう」と、そこで私は、この先もトマト生産を続けるために、競争ができるだけ少なく、新規需要の開拓が可能な、調理用トマトにターゲットに絞った生産を行ってはどうかと考え作り始めました。
そんな中、出会った取引先のスーパーマーケット「ハローデイ」は、多い店舗で約30種類のトマトが棚を埋め、トマトの品ぞろえ日本一の店でした。しかしトマトブームがひと段落した売り場には、赤い丸いトマトしかなく、糖度一辺倒の売り文句は、お客様に飽きが見られるなど、見直しが必要な状態でした。
私が栽培していた細長く、火を加えることで旨味を増す調理用トマト「サンマルツァーノリゼルバ」はタイミング良く、バイヤーの目に留まり、今まで売り場になかった調理用のジャンルを開拓することで売り場の更なる売上アップへ貢献できるのではと、納品が開始されました。
普通のトマトでソースなどをつくると水っぽくなるのに対して、サンマルツァーノリゼルバだと旨味がある濃いソースができるため喜ばれるなど、お客様からの好評を得ることができ、定期的な取引へ発展いたしました。

マーケティングの結果の狙い通りの展開でしたが、予想を反して、海外で生活していて日本に売っておらず実は探していたという方や、糖度よりも歯ごたえがいいトマトが欲しかったという方など、意外なご意見をいただくことができ、需要の大きさと市場の拡大が狙えるのではと感じることができました。
最近は外国人技能実習生の増加により若干ですが売れ方に変化の兆しが見えてきています。訪日外国人観光客は、「日本食」を中心に堪能して帰ります。しかし、住むとなれば、どこの国の方でも「里の味」が恋しくなるもの。
福岡では、ネパール、ベトナムと東南アジアからの移住が増えている背景から「空心菜」の需要が、若干ですが伸び始めています。
この情報を掴んだ売り場は、空心菜を売りたいと思っています。
では、この情報を元に「空心菜をつくってください」と、農家さんにお願いするとしたらどうでしょうか?
など、新規需要の野菜を委託生産するにもハードルは高く、受けてくれる農家を見つけるのもひと苦労です。
農家側も頼まれてつくった野菜が、「売れないからいらない」と取り引きを途中で切られたらたまったものではありません。
そこで、2016年に双方の悩みを解決するためのプロジェクト「農業法人ハローファーム犀川圃場」を、福岡県京都郡みやこ町に創設するに至りました。
ですが実際は、収穫→調整→JA・卸→市場→仲卸→流通センター→店舗と複雑な工程を経て、お客様へと届きます。この期間、収穫から約5日間。
これをハローファーム犀川では、農家で集荷された野菜を、翌朝の店頭で販売ができるように物流の短縮を行いました。
また、ひとつのチャレンジとして、規格と工程を変えることで農家手取りを上げながら、安定した納品ができないかと、農家から「収穫したまま」の姿で仕入れ、自社のパックセンターで梱包し、売り場には「並べるだけ」の姿で納品ができないか検討することにしました。

その過程で農家が感じていた「野菜が安すぎる」の正体も漠然とわかりました。野菜価格の下落なども原因ですが、正しくは「手間に対しての手取り額の少なさ」です。
生産ピークの時は、仕事量は増え、夜遅くまで梱包に追われることがある中で、どこも最盛期のため野菜価格は下落します(いわゆる豊作貧乏状態)。手間と労力は増大するのに、単価が安いのが納得できないと思うのは当然の心理でしょう。
それなら、その手間の部分を取り除き継続した農業を行うことができる取引内容であれば、多くの農家の努力が報われるのではないかと新たなビジネスモデルの姿が漠然と浮かんできました。
一定の目的を達したため、グループから独立し株式会社収穫祭を設立することとしました。
「お客様の声」を「生産」に生かし栽培するという本来のハローファームのモデルを生かしながら、さらに生産現場を楽に稼げる分野へ変えるため、生産と梱包の分業化を行い、売上の拡大を行える「農業1.5次産業化」を模索していきたいと思います。
次回は、収穫祭の取り組み「農業1.5次産業化モデル」の紹介をいたします。
年号の変わり目を機に「株式会社収穫祭」という会社を新規創業しました。生産・流通と双方を手がけることで「農業の1.5次産業化」を促す、新業態ベンチャー企業を目指した組織作りを模索しています。
今回、「SMART AGRI」でのSNSのライター募集に応募し、自分の農業への関わりや会社設立に関して、コラムを執筆させていただくことになりました。
井中優治さんプロフィール
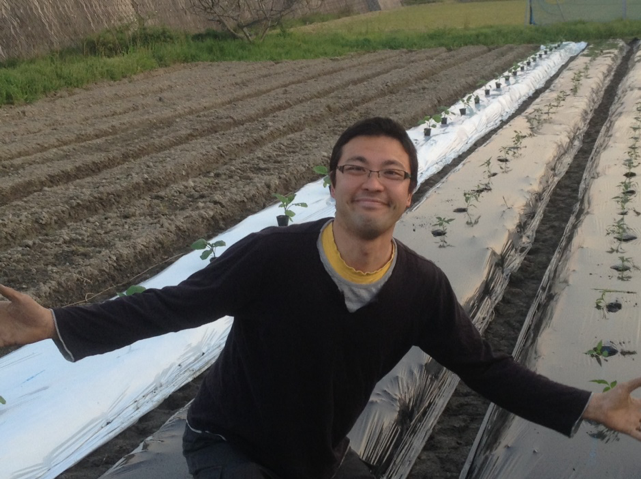 いちゅうゆうじ。株式会社収穫祭ベジプロモーター。福岡県農業大学校卒。オランダで1年農業研修。広告代理店勤務を経て、新規就農6年目。令和元年5月7日に株式会社収穫祭を創業。主に農業現場の声や九州のイベント情報などを発信している。
いちゅうゆうじ。株式会社収穫祭ベジプロモーター。福岡県農業大学校卒。オランダで1年農業研修。広告代理店勤務を経て、新規就農6年目。令和元年5月7日に株式会社収穫祭を創業。主に農業現場の声や九州のイベント情報などを発信している。
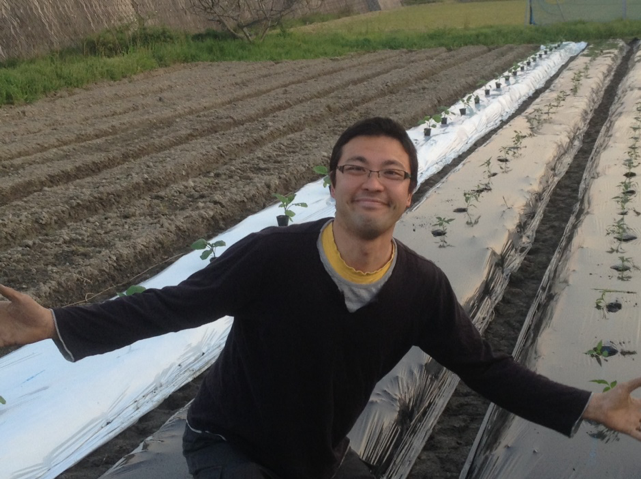 いちゅうゆうじ。株式会社収穫祭ベジプロモーター。福岡県農業大学校卒。オランダで1年農業研修。広告代理店勤務を経て、新規就農6年目。令和元年5月7日に株式会社収穫祭を創業。主に農業現場の声や九州のイベント情報などを発信している。
いちゅうゆうじ。株式会社収穫祭ベジプロモーター。福岡県農業大学校卒。オランダで1年農業研修。広告代理店勤務を経て、新規就農6年目。令和元年5月7日に株式会社収穫祭を創業。主に農業現場の声や九州のイベント情報などを発信している。脱サラからスタートした農業経営
私が農業を本気で目指したのは、行橋高校農業技術科へ進学したのがきっかけでした。食べ物をつくる楽しみや農作業の楽しさを知った反面、農業の厳しさや担い手の不足なども知る事なり福岡県農業大学校へ進学。大学校を卒業後、オランダへJAECの派遣制度を使い1年研修へ行き、さらに農業を詳しく学びました。その後帰国してからは、そのまま農業を始めるのではなく、一度社会を知るためできる限り多くの社長へ会える広告営業の仕事に就こうと考え、広告代理店へ就職、社会人キャリアを重ねました。
その後、結婚を機に脱サラ。広告代理店時代に培った「プロモーション」「マーケティング」「営業力」の3つを武器にして、福岡県京都郡みやこ町で農業をスタートしました。
マーケティングから需要を予測し調理用トマトを生産
新規で農業を始めるにあたり、マーケティングを取り入れ何をつくろうかと考えました。皆がつくっているものと同じものでは競争相手が多く取引先の拡大は見込めず、希少性だけでは、経営の柱になるほどには販売できない。スーパーの店員さんや市場の仲買人さんへのヒアリングを重ねながら市場調査を行い、農水省のデータや市況を見ながら作物を絞っていきました。
トマトの販売量が売り場では減少傾向にあり、生産が大玉からミニトマトへ移りアイテム数は増加している、規模拡大などで生産量が増えている事などからちょっとしたブームが来ている事などを市場調査でつかんだことで、一つの予測を立てました。
「この先、ブームは落ち着き生食需要の減少やコアターゲットの高齢化でトマトの販売量がさらに減っていくだろう」と、そこで私は、この先もトマト生産を続けるために、競争ができるだけ少なく、新規需要の開拓が可能な、調理用トマトにターゲットに絞った生産を行ってはどうかと考え作り始めました。
そんな中、出会った取引先のスーパーマーケット「ハローデイ」は、多い店舗で約30種類のトマトが棚を埋め、トマトの品ぞろえ日本一の店でした。しかしトマトブームがひと段落した売り場には、赤い丸いトマトしかなく、糖度一辺倒の売り文句は、お客様に飽きが見られるなど、見直しが必要な状態でした。
私が栽培していた細長く、火を加えることで旨味を増す調理用トマト「サンマルツァーノリゼルバ」はタイミング良く、バイヤーの目に留まり、今まで売り場になかった調理用のジャンルを開拓することで売り場の更なる売上アップへ貢献できるのではと、納品が開始されました。
普通のトマトでソースなどをつくると水っぽくなるのに対して、サンマルツァーノリゼルバだと旨味がある濃いソースができるため喜ばれるなど、お客様からの好評を得ることができ、定期的な取引へ発展いたしました。

マーケティングの結果の狙い通りの展開でしたが、予想を反して、海外で生活していて日本に売っておらず実は探していたという方や、糖度よりも歯ごたえがいいトマトが欲しかったという方など、意外なご意見をいただくことができ、需要の大きさと市場の拡大が狙えるのではと感じることができました。
小売りと生産現場の悩みを解決する「農業法人ハローファーム」
そんな取り組みがきっかけとなり、「こんなのできないのか?」「こんな売り方はどうだろうか」と会話が生まれ、「お客さんにはこんなふうに言われたけど」と売り場の声まで頂けるようになりました。リアルなお客様の声はそのまま生産へ転嫁させることができる絶好の材料です。品目だけでなく「今ある規格」を見直すきっかけにもなりました。最近は外国人技能実習生の増加により若干ですが売れ方に変化の兆しが見えてきています。訪日外国人観光客は、「日本食」を中心に堪能して帰ります。しかし、住むとなれば、どこの国の方でも「里の味」が恋しくなるもの。
福岡では、ネパール、ベトナムと東南アジアからの移住が増えている背景から「空心菜」の需要が、若干ですが伸び始めています。
この情報を掴んだ売り場は、空心菜を売りたいと思っています。
では、この情報を元に「空心菜をつくってください」と、農家さんにお願いするとしたらどうでしょうか?
- 販売価格がわからない。 原価はどのくらいかかるのだろう
- どのくらい生産してもらい、どのくらいのペースで出荷してもらったらいいか?
- つくり方の指導は誰がするのか?
- 売れなかったときはどうするのか?
など、新規需要の野菜を委託生産するにもハードルは高く、受けてくれる農家を見つけるのもひと苦労です。
農家側も頼まれてつくった野菜が、「売れないからいらない」と取り引きを途中で切られたらたまったものではありません。
そこで、2016年に双方の悩みを解決するためのプロジェクト「農業法人ハローファーム犀川圃場」を、福岡県京都郡みやこ町に創設するに至りました。
「採れたて新鮮」「野菜が安い」の実態
「採れたて新鮮」という言葉をキャッチコピーとして掲げる店は多いと思います。ですが実際は、収穫→調整→JA・卸→市場→仲卸→流通センター→店舗と複雑な工程を経て、お客様へと届きます。この期間、収穫から約5日間。
これをハローファーム犀川では、農家で集荷された野菜を、翌朝の店頭で販売ができるように物流の短縮を行いました。
また、ひとつのチャレンジとして、規格と工程を変えることで農家手取りを上げながら、安定した納品ができないかと、農家から「収穫したまま」の姿で仕入れ、自社のパックセンターで梱包し、売り場には「並べるだけ」の姿で納品ができないか検討することにしました。

その過程で農家が感じていた「野菜が安すぎる」の正体も漠然とわかりました。野菜価格の下落なども原因ですが、正しくは「手間に対しての手取り額の少なさ」です。
生産ピークの時は、仕事量は増え、夜遅くまで梱包に追われることがある中で、どこも最盛期のため野菜価格は下落します(いわゆる豊作貧乏状態)。手間と労力は増大するのに、単価が安いのが納得できないと思うのは当然の心理でしょう。
それなら、その手間の部分を取り除き継続した農業を行うことができる取引内容であれば、多くの農家の努力が報われるのではないかと新たなビジネスモデルの姿が漠然と浮かんできました。
生産と梱包を分業化し「農業1.5次産業化モデル」へ
ハローファームでの取り組みは3年間、市場にない野菜の生産や栽培方法の確認。規格の検討などを行ってきました。一定の目的を達したため、グループから独立し株式会社収穫祭を設立することとしました。
「お客様の声」を「生産」に生かし栽培するという本来のハローファームのモデルを生かしながら、さらに生産現場を楽に稼げる分野へ変えるため、生産と梱包の分業化を行い、売上の拡大を行える「農業1.5次産業化」を模索していきたいと思います。
次回は、収穫祭の取り組み「農業1.5次産業化モデル」の紹介をいたします。
【農家コラム】株式会社収穫祭・井中優治の「農業1.5次産業化のススメ」
- 【井中優治の農家コラム 第3回】オランダの花き農園で感じた農作業分業化の効果
- 【井中優治の農家コラム 第2回】新規農業者にも効果的な1.5次元産業化で農業経営を安定させよう
- 【井中優治の農家コラム 第1回】農業の抱える悩みを解決する分業化モデル「株式会社収穫祭」創業に至るまで
SHARE







































