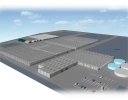農水省、食品ロス削減に向け「おいしい食べきり」「mottECO(もってこ)」など全国キャンペーン中
農林水産省は、消費者庁、環境省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と連携し、2023年12月から2024年1月まで、食品ロス削減の普及啓発のため、外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施している。
残さず食べきることを呼び掛けるための普及啓発資材の提供や、取り組みに参画する事業者や自治体についての情報発信を行う。
 普及啓発資材 卓上ポップ
普及啓発資材 卓上ポップ
出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html
年間約600万トンも発生している食品ロス削減の問題は、事業者・消費者・地方公共団体も含め、国民運動として取り組むべき課題である。
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンは、忘年会や新年会など年末年始の会食等が多くなる時期に、外食時の適量注文による食べきり、テイクアウト時の適量購入、家庭での食べきりを呼び掛けるものだ。
このキャンペーンは毎年12月から翌1月まで実施されており、キャンペーン期間中には、外食事業者等が消費者に残さず食べきることを呼び掛けるために、食品ロス削減国民運動のロゴマーク「ろすのん」を使った卓上ポップやポスターが提供される。
普及啓発資材は農林水産省のページから使用申請するとダウンロードして使用可能だ。
また、外食を楽しみ、残さず食べきるため、ポスター及び卓上ポップを作成するとともに、消費者の向けに家庭でできる食べきる工夫のチラシとして、食材を無駄にしないレシピ(まだ食べられる食材を無駄なく使うレシピ)を提供している。
 「mottECO」ロゴマーク出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html
「mottECO」ロゴマーク出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html
外食時にどうしても食べきれない場合の「mottECO(もってこ)」(食べ残しを持ち帰る行為)を自己責任の範囲で取り組むことも併せて呼び掛けている。
環境省のHPでは、飲食店の方や、自治体の方が利用できる「mottECO(もってこ)」の普及啓発資材が提供されている。申請が必要だが利用は無料。食品ロス削減に向けた普及啓発に活用できる。ただし、食べ残し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で、自己責任の範囲で行うことを伝えることが大切だ。
取り組みにより徐々に食品ロスは減少傾向にあったが、コロナが5類に移行し、はじめての忘年会・新年会シーズン。一気にリバウンドとならないよう、飲食店をはじめ、顧客となる一人一人が「おいしく食べきって食品ロスをださない」ことを心がけていくことが大切である。
年末年始の会食が増えるシーズンは、特に外食産業を中心に食品ロス・フードロスが増加する。外食産業(飲食店)としては具体的にどのような取り組みができるのだろうか。
以下のような飲食店等の食品ロス削減のためのポイントも紹介されている。
食べきりの促進
①子どもや女性、高齢者にも、残さずに食べきれるサイズ(量)の商品開発。
ご飯の大盛、中盛、小盛や、ミニ丼、半ラーメンなど。
②ポスターやテーブル置き三角柱の設置による、客への食べきりの呼びかけ。
③ 宴会等、大量の食事を準備する際には、食べ残しが発生しないよう幹事と食事量やメニューを相談。
④客へ3010(さんまる・いちまる)運動への取り組みを依頼。
3010運動とは、 乾杯後の30分間と終了前10分間は自席について料理を楽しむことにより、食べ残しによる食品ロスを減らす運動のこと。
⑤宴会用パンフレットを通じて啓発し、幹事との打ち合わせ時に具体的に説明。
宴席当日、適宜アナウンスを入れ、ゲストに呼びかける。
⑥宴会等では、お客が食べきったらサービス券を配布するなど、食べきることにインセンティブを持たせる。
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンは、飲食店だけが取り組むものではない。
全国の地方自治体も、省庁内の食堂でのポスター掲示による周知活動や、地元の飲食店への啓蒙、持ち帰り用ドギーバックの配布、食べきり協力店での飲食によるポイント付与など、独自の取り組みを行っている。
2023年度の各自治体の実施予定は、下記リンクより詳細を見ることができる。
外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン実施予定
https://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/network/pdf/R5campaign.pdf
農林水産省「外食店舗での啓発資材」掲載ページhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/170516.html
農林水産省「ろすのん」利用申請ページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227.html
消費者庁の食品ロス削減に向けた取り組み
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/
環境省「mottECO」申請およびダウンロードページ
https://www.env.go.jp/recycle/food/motteco.html
消費者庁 食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2023_food_loss_guide_book_231117_01.pdf
残さず食べきることを呼び掛けるための普及啓発資材の提供や、取り組みに参画する事業者や自治体についての情報発信を行う。
 普及啓発資材 卓上ポップ
普及啓発資材 卓上ポップ出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html
卓上ポップやポスターで適量注文や購入を呼び掛け
年間約600万トンも発生している食品ロス削減の問題は、事業者・消費者・地方公共団体も含め、国民運動として取り組むべき課題である。
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンは、忘年会や新年会など年末年始の会食等が多くなる時期に、外食時の適量注文による食べきり、テイクアウト時の適量購入、家庭での食べきりを呼び掛けるものだ。
このキャンペーンは毎年12月から翌1月まで実施されており、キャンペーン期間中には、外食事業者等が消費者に残さず食べきることを呼び掛けるために、食品ロス削減国民運動のロゴマーク「ろすのん」を使った卓上ポップやポスターが提供される。
普及啓発資材は農林水産省のページから使用申請するとダウンロードして使用可能だ。
また、外食を楽しみ、残さず食べきるため、ポスター及び卓上ポップを作成するとともに、消費者の向けに家庭でできる食べきる工夫のチラシとして、食材を無駄にしないレシピ(まだ食べられる食材を無駄なく使うレシピ)を提供している。
 「mottECO」ロゴマーク出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html
「mottECO」ロゴマーク出典:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/231130.html外食時にどうしても食べきれない場合の「mottECO(もってこ)」(食べ残しを持ち帰る行為)を自己責任の範囲で取り組むことも併せて呼び掛けている。
環境省のHPでは、飲食店の方や、自治体の方が利用できる「mottECO(もってこ)」の普及啓発資材が提供されている。申請が必要だが利用は無料。食品ロス削減に向けた普及啓発に活用できる。ただし、食べ残し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で、自己責任の範囲で行うことを伝えることが大切だ。
取り組みにより徐々に食品ロスは減少傾向にあったが、コロナが5類に移行し、はじめての忘年会・新年会シーズン。一気にリバウンドとならないよう、飲食店をはじめ、顧客となる一人一人が「おいしく食べきって食品ロスをださない」ことを心がけていくことが大切である。
年末年始の会食が増えるシーズンは、特に外食産業を中心に食品ロス・フードロスが増加する。外食産業(飲食店)としては具体的にどのような取り組みができるのだろうか。
以下のような飲食店等の食品ロス削減のためのポイントも紹介されている。
食べきりの促進
①子どもや女性、高齢者にも、残さずに食べきれるサイズ(量)の商品開発。
ご飯の大盛、中盛、小盛や、ミニ丼、半ラーメンなど。
②ポスターやテーブル置き三角柱の設置による、客への食べきりの呼びかけ。
③ 宴会等、大量の食事を準備する際には、食べ残しが発生しないよう幹事と食事量やメニューを相談。
④客へ3010(さんまる・いちまる)運動への取り組みを依頼。
3010運動とは、 乾杯後の30分間と終了前10分間は自席について料理を楽しむことにより、食べ残しによる食品ロスを減らす運動のこと。
⑤宴会用パンフレットを通じて啓発し、幹事との打ち合わせ時に具体的に説明。
宴席当日、適宜アナウンスを入れ、ゲストに呼びかける。
⑥宴会等では、お客が食べきったらサービス券を配布するなど、食べきることにインセンティブを持たせる。
自治体の取り組み
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンは、飲食店だけが取り組むものではない。
全国の地方自治体も、省庁内の食堂でのポスター掲示による周知活動や、地元の飲食店への啓蒙、持ち帰り用ドギーバックの配布、食べきり協力店での飲食によるポイント付与など、独自の取り組みを行っている。
2023年度の各自治体の実施予定は、下記リンクより詳細を見ることができる。
外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン実施予定
https://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/network/pdf/R5campaign.pdf
農林水産省「外食店舗での啓発資材」掲載ページhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/170516.html
農林水産省「ろすのん」利用申請ページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227.html
消費者庁の食品ロス削減に向けた取り組み
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/
環境省「mottECO」申請およびダウンロードページ
https://www.env.go.jp/recycle/food/motteco.html
消費者庁 食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2023_food_loss_guide_book_231117_01.pdf
SHARE