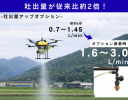植物の健康状態を直接解析する次世代型技術とは
気温、日射量、湿度など、植物の置かれた環境情報を取得し、植物の状態を推測する──農業IoTといえば、こうした方法をとるものがほとんどだ。
そんな中で、植物の生体情報をダイレクトに「見える化」するアグリテック・ベンチャーがある。愛媛大学に拠点を置くPLANT DATA株式会社。植物そのものを解析するという世界的にも珍しい手法が、これまでには考えられなかった高い収量を実現するかもしれない。
 ▲PLANT DATAの開発した植物の生体情報を解析する装置
▲PLANT DATAの開発した植物の生体情報を解析する装置
「これらの苗は全部元気で問題ないように見えますが、実際は健康でないものも混ざっているのです。目で見てもわからない植物の状態を知るために、我々の技術を役立てたいと考えています」
 ▲PLANT DATA CEOの北川寛人さん(愛媛大学農学部の研究拠点で)
▲PLANT DATA CEOの北川寛人さん(愛媛大学農学部の研究拠点で)
国内のトマトの平均収量は10アールあたり15トン程度とされる。簡易なビニールハウスなども含まれるためで、精密農業の先進地オランダの収量70~75トンに比べると大きく引けを取っている。国内でも最新鋭の施設を導入し、オランダの収量レベルに達する農場が現れてきていて、平均の15トンに比べると大変な進歩だ。しかし……。
「トマトの収量は理論上、10アール当たり200~220トン取れると言われているんです。ということは、国内の先進的なトマト農場やオランダの栽培は、しくじっているようには見えないけれども、僕らにはわからない栽培上の瑕疵(かし)がある」(北川さん)
農業IoTというと、通常は植物の置かれた環境のデータを蓄積し、そこから植物の状態を推測するものが主流だ。光量や温度、湿度、養分などを統合的に制御する統合環境制御装置の付いた最新の植物工場も、やはり環境情報を計測し、植物にとって最適な状態を作り出そうとする。
しかし、一つひとつの植物が置かれた状況は微妙に違っているし、個体差もあるため、人工光の植物工場ですら生育ムラが生じる。つまり環境情報のみを参考に気温や日射量、湿度などを調整しても、収量の向上には限界があるのだ。
井関農機と共同開発し、2015年から市販している「植物生育診断装置」だ。植物の診断専用の農機というのは、世界で初だという。
 ▲植物生育診断装置
▲植物生育診断装置
4本の青色LEDとカメラの付いた部分が上下にスライドし、植物に触れないで、つまり植物にストレスを与えないでその状態を測る。トマトのハウスの地上にレールのように張り巡らされた暖房用に湯を流す温湯管の上を移動させ、計測する。
この装置は夜間に青色LEDを照射した状態で植物を撮影し、植物の発する「クロロフィル蛍光」の量を把握する。植物は吸収した光エネルギーのうち、光合成に用いず余ったものの一部をクロロフィル蛍光という赤い光にして発光する。何らかのストレスで光合成が順調にできないと発光量が増えるため、目視ではわからないわずかなストレスや病害虫も検知できる。
 ▲夜間に青色LEDを照射し撮影する
▲夜間に青色LEDを照射し撮影する
トマトのハウス以外でも、天井から吊るしてハウス内のイチゴやレタスを計測したり、車輪付きの台車に載せて露地栽培のブドウを計測したりと、さまざまな用途向けに実証が進められてきた。葉緑素を含むものならナスやパプリカから藻類まで、何でも計測可能だ。
ほかに、光を透過するフィルムで植物をすっぽりと包み込み、植物の光合成と蒸散の速度を計測する「光合成計測チャンバー」という機器がある。気温や日射量、湿度などの外的要因のみならず、蒸散と光合成の速度といった植物そのものの情報がグラフ化され、相関関係を把握することができる。「フォトセル」という名前で2018年中に市販する見込みだ。
 ▲光合成計測チャンバー
▲光合成計測チャンバー
「1ヘクタールあたり1億円の売り上げだとすると、収量を10%改善するだけで売り上げが1千万円上がる。収量増に伴うコスト増は収穫や選果の量の増加に伴う人件費の増加分で、国内の先進的な経営体ならコストの増加分を引いても800万円は粗利で残る。計測装置やサービスを使うコストは吸収できますよね」(北川さん)
機器そのもののコスト低減のためのプロジェクトも進めており、次世代型の技術が農場で使われるようになる日も近いかもしれない。
PLANT DATA株式会社
そんな中で、植物の生体情報をダイレクトに「見える化」するアグリテック・ベンチャーがある。愛媛大学に拠点を置くPLANT DATA株式会社。植物そのものを解析するという世界的にも珍しい手法が、これまでには考えられなかった高い収量を実現するかもしれない。
 ▲PLANT DATAの開発した植物の生体情報を解析する装置
▲PLANT DATAの開発した植物の生体情報を解析する装置オランダですら理論上の収量の3分の1
愛媛大学農学部(松山市)には、日射量や気温、湿度などを一体的に管理する環境制御システムを備えた最新式のガラス温室がある。その入り口に置かれたトマトの苗を指さし、PLANT DATAのCEO、北川寛人さんが言う。「これらの苗は全部元気で問題ないように見えますが、実際は健康でないものも混ざっているのです。目で見てもわからない植物の状態を知るために、我々の技術を役立てたいと考えています」
 ▲PLANT DATA CEOの北川寛人さん(愛媛大学農学部の研究拠点で)
▲PLANT DATA CEOの北川寛人さん(愛媛大学農学部の研究拠点で)国内のトマトの平均収量は10アールあたり15トン程度とされる。簡易なビニールハウスなども含まれるためで、精密農業の先進地オランダの収量70~75トンに比べると大きく引けを取っている。国内でも最新鋭の施設を導入し、オランダの収量レベルに達する農場が現れてきていて、平均の15トンに比べると大変な進歩だ。しかし……。
「トマトの収量は理論上、10アール当たり200~220トン取れると言われているんです。ということは、国内の先進的なトマト農場やオランダの栽培は、しくじっているようには見えないけれども、僕らにはわからない栽培上の瑕疵(かし)がある」(北川さん)
農業IoTというと、通常は植物の置かれた環境のデータを蓄積し、そこから植物の状態を推測するものが主流だ。光量や温度、湿度、養分などを統合的に制御する統合環境制御装置の付いた最新の植物工場も、やはり環境情報を計測し、植物にとって最適な状態を作り出そうとする。
しかし、一つひとつの植物が置かれた状況は微妙に違っているし、個体差もあるため、人工光の植物工場ですら生育ムラが生じる。つまり環境情報のみを参考に気温や日射量、湿度などを調整しても、収量の向上には限界があるのだ。
世界初の植物診断専用農機
では、一体どうやって植物の生体情報を取得するのか。温室の中に鎮座している、高さ3メートルほどの石碑のような形をした機械がその答えだ。井関農機と共同開発し、2015年から市販している「植物生育診断装置」だ。植物の診断専用の農機というのは、世界で初だという。
 ▲植物生育診断装置
▲植物生育診断装置4本の青色LEDとカメラの付いた部分が上下にスライドし、植物に触れないで、つまり植物にストレスを与えないでその状態を測る。トマトのハウスの地上にレールのように張り巡らされた暖房用に湯を流す温湯管の上を移動させ、計測する。
この装置は夜間に青色LEDを照射した状態で植物を撮影し、植物の発する「クロロフィル蛍光」の量を把握する。植物は吸収した光エネルギーのうち、光合成に用いず余ったものの一部をクロロフィル蛍光という赤い光にして発光する。何らかのストレスで光合成が順調にできないと発光量が増えるため、目視ではわからないわずかなストレスや病害虫も検知できる。
 ▲夜間に青色LEDを照射し撮影する
▲夜間に青色LEDを照射し撮影するトマトのハウス以外でも、天井から吊るしてハウス内のイチゴやレタスを計測したり、車輪付きの台車に載せて露地栽培のブドウを計測したりと、さまざまな用途向けに実証が進められてきた。葉緑素を含むものならナスやパプリカから藻類まで、何でも計測可能だ。
ほかに、光を透過するフィルムで植物をすっぽりと包み込み、植物の光合成と蒸散の速度を計測する「光合成計測チャンバー」という機器がある。気温や日射量、湿度などの外的要因のみならず、蒸散と光合成の速度といった植物そのものの情報がグラフ化され、相関関係を把握することができる。「フォトセル」という名前で2018年中に市販する見込みだ。
 ▲光合成計測チャンバー
▲光合成計測チャンバー2020年までに本格普及
植物生育診断装置も光合成計測チャンバーも、導入費用は200万円前後から400万円ほどと安くはない。当面想定するユーザーは、1ヘクタールを超す大規模な生産者や、面積が小さくても高い収益を上げている農家だ。今は大規模生産をしている農業法人などで機器を使ってもらい、収量の向上にどう結び付けるか、実証をしている段階だ。2020年までには本格的な普及に踏み切りたいという。「1ヘクタールあたり1億円の売り上げだとすると、収量を10%改善するだけで売り上げが1千万円上がる。収量増に伴うコスト増は収穫や選果の量の増加に伴う人件費の増加分で、国内の先進的な経営体ならコストの増加分を引いても800万円は粗利で残る。計測装置やサービスを使うコストは吸収できますよね」(北川さん)
機器そのもののコスト低減のためのプロジェクトも進めており、次世代型の技術が農場で使われるようになる日も近いかもしれない。
PLANT DATA株式会社
SHARE