企業と高専がタッグした水田除草ロボット──有限会社エコ・ライス新潟(前編)
有限会社エコ・ライス新潟(新潟県長岡市)は、農薬不使用や農薬使用量削減で稲作をする農家らが、コメの集荷と販売をするために組織した。しかし、会員農家の経営面積が拡大し、化学農薬や化学肥料に頼らない農法を続けるのが大変になってきた。
そこで活用を検討し始めたのがロボット。といってメーカーへの完全依存ではない。全国高等専門学校ロボットコンテスト(通称「ロボコン」)の常連校である地元の長岡工業高等専門学校(以下、長岡高専)と組んで、今年から独自の開発に乗り出した。
水田に囲まれ、収穫したコメの乾燥・籾摺りなどを行うライスセンターを備えた本社で取材に応じてくれたのは、社長の豊永有さん。
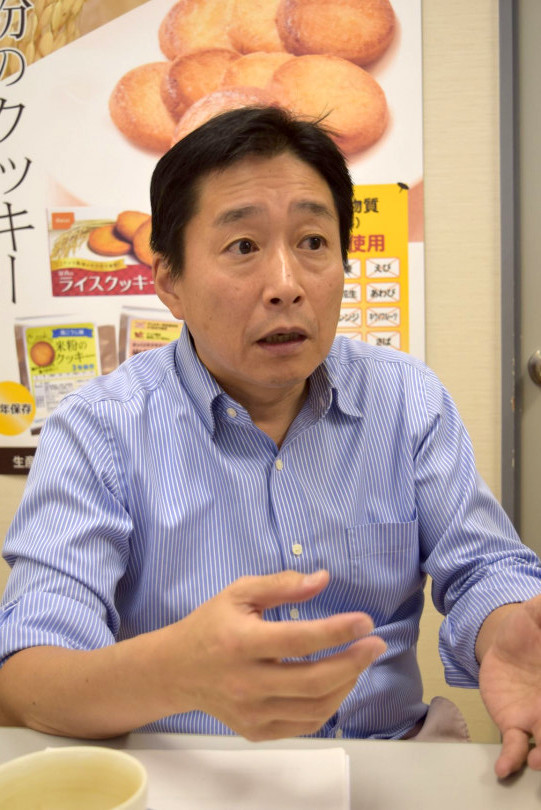
エコ・ライス新潟は、あらゆる産業のロボットビジネスを推進するため、2017年に設立されたNPO法人RobiZy(理事長・東京大学の佐藤知正名誉教授)に加入。同法人は幅広い産業分野を対象とし、産学官のあらゆる組織が加盟している。農業分野を手がけている企業や組織を挙げれば、株式会社オプティムやNPO法人日本プロ農業総合支援機構(J-PAO)など。
ちなみに筆者は同会のアドバイザーであり、同会副理事長の北河博康氏(三井住友海上火災保険株式会社上席課長)の紹介で今回の取材に至った。
さらに学校でポン菓子づくりや稲わらのリースづくりの体験会を、地元だけではなく関東圏の小・中学校で開いている。なぜか。ひと言でいえば、潜在的な顧客の候補をつくっているのだ。販路を広げるという点で面白いので、簡単にふれておきたい。
まずはポン菓子について。体験会を開いている小・中学校ではもともと、学校給食で福島県産のコメを使っていた。それが2011年3月11日の原発事故の影響で同県産を調達できなくなったのを機に、仕入先として選ばれたのがエコ・ライス新潟だった。
おまけに、ポン菓子は爆発音が児童や生徒の印象に残る。「子どもたちって、音とかにおいとかは忘れないんだよね。それを狙っている」と豊永さんは話す。
また、東京家政大学では栄養士の卵である学生らに、米粉を原料にしたロールケーキなどの料理を作る講習会を開いている。
「彼女たちが年齢を重ねて社会で力をつけてくれば、いろいろなイベントに呼んでくれるようになる。コメの売上げは1、2年の短期的なものを追い求めるべきではないと思っている。学校でのイベントは一見お金にならないようだが、決してそんなことはない」
エコ・ライス新潟の会員農家の経営面積は、周囲で離農が相次いでいることから拡大する一方。それに伴って農作業の中でも特に除草がしんどくなってきた。そこで長岡高専と組んで開発を始めたのがラジコンを用いたチェーン除草機だ。
「チェーン除草」は有機稲作の農家には多少普及している技術。新潟県農業総合研究所によると、その概略は次の通り。
作り方は、ホームセンターなどで購入できる長さ2mの角棒に、先がフック状になったヒル釘を使って、80本のチェーンをのれん状に取り付ける。あとは角棒の反対側に人の手で引っ張るヒモを装着するだけ。

使い方は、成苗の移植後2〜4日目から、水田においてこれを人力で引く。以後、5〜7日間隔で4、5回繰り返す。チェーンによって雑草の根が引っこ抜かれるなどして、出穂期の雑草の残存本数が半減するという。
エコ・ライス新潟では、会員農家の一人がラジコンの小型サーフボードを改造し、チェーンを取り付けて除草に役立てていた。長岡高専との共同研究で目指すのは、GPSによる自動運転。あらかじめ設定した経路に沿って、人がリモコンで操縦せずとも、水上を走るようにする。
豊永さんはメーカーが試作しているロボットも積極的に試している。次回はそのうちのひとつ、「アイガモロボット」や、従業員の作業量を軽減するためのさまざまな工夫について紹介する。
<参考URL>
有限会社エコ・ライス新潟
長岡工業高等専門学校
そこで活用を検討し始めたのがロボット。といってメーカーへの完全依存ではない。全国高等専門学校ロボットコンテスト(通称「ロボコン」)の常連校である地元の長岡工業高等専門学校(以下、長岡高専)と組んで、今年から独自の開発に乗り出した。
水田に囲まれ、収穫したコメの乾燥・籾摺りなどを行うライスセンターを備えた本社で取材に応じてくれたのは、社長の豊永有さん。
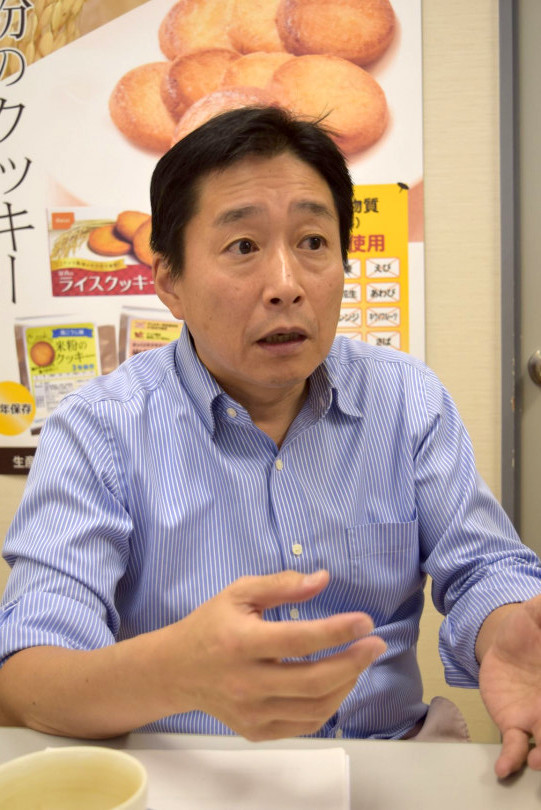
エコ・ライス新潟は、あらゆる産業のロボットビジネスを推進するため、2017年に設立されたNPO法人RobiZy(理事長・東京大学の佐藤知正名誉教授)に加入。同法人は幅広い産業分野を対象とし、産学官のあらゆる組織が加盟している。農業分野を手がけている企業や組織を挙げれば、株式会社オプティムやNPO法人日本プロ農業総合支援機構(J-PAO)など。
ちなみに筆者は同会のアドバイザーであり、同会副理事長の北河博康氏(三井住友海上火災保険株式会社上席課長)の紹介で今回の取材に至った。
将来の顧客候補は「学校」にあり
エコ・ライス新潟の会員農家は130戸で、栽培面積は約2000ヘクタールに及ぶ。農薬不使用や農薬使用量を減らして作っているコメは酒造用や主食用としてだけではなく、災害時の非常食やクッキーなどにも加工し、販売している。さらに学校でポン菓子づくりや稲わらのリースづくりの体験会を、地元だけではなく関東圏の小・中学校で開いている。なぜか。ひと言でいえば、潜在的な顧客の候補をつくっているのだ。販路を広げるという点で面白いので、簡単にふれておきたい。
まずはポン菓子について。体験会を開いている小・中学校ではもともと、学校給食で福島県産のコメを使っていた。それが2011年3月11日の原発事故の影響で同県産を調達できなくなったのを機に、仕入先として選ばれたのがエコ・ライス新潟だった。
おまけに、ポン菓子は爆発音が児童や生徒の印象に残る。「子どもたちって、音とかにおいとかは忘れないんだよね。それを狙っている」と豊永さんは話す。
また、東京家政大学では栄養士の卵である学生らに、米粉を原料にしたロールケーキなどの料理を作る講習会を開いている。
「彼女たちが年齢を重ねて社会で力をつけてくれば、いろいろなイベントに呼んでくれるようになる。コメの売上げは1、2年の短期的なものを追い求めるべきではないと思っている。学校でのイベントは一見お金にならないようだが、決してそんなことはない」
除草のしんどさをロボットが軽減
さて、本題のロボットについて。エコ・ライス新潟の会員農家の経営面積は、周囲で離農が相次いでいることから拡大する一方。それに伴って農作業の中でも特に除草がしんどくなってきた。そこで長岡高専と組んで開発を始めたのがラジコンを用いたチェーン除草機だ。
「チェーン除草」は有機稲作の農家には多少普及している技術。新潟県農業総合研究所によると、その概略は次の通り。
作り方は、ホームセンターなどで購入できる長さ2mの角棒に、先がフック状になったヒル釘を使って、80本のチェーンをのれん状に取り付ける。あとは角棒の反対側に人の手で引っ張るヒモを装着するだけ。

使い方は、成苗の移植後2〜4日目から、水田においてこれを人力で引く。以後、5〜7日間隔で4、5回繰り返す。チェーンによって雑草の根が引っこ抜かれるなどして、出穂期の雑草の残存本数が半減するという。
エコ・ライス新潟では、会員農家の一人がラジコンの小型サーフボードを改造し、チェーンを取り付けて除草に役立てていた。長岡高専との共同研究で目指すのは、GPSによる自動運転。あらかじめ設定した経路に沿って、人がリモコンで操縦せずとも、水上を走るようにする。
豊永さんはメーカーが試作しているロボットも積極的に試している。次回はそのうちのひとつ、「アイガモロボット」や、従業員の作業量を軽減するためのさまざまな工夫について紹介する。
<参考URL>
有限会社エコ・ライス新潟
長岡工業高等専門学校
SHARE
















































