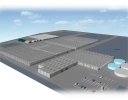第9回高校生科学教育大賞、最優秀賞はゲノム編集で品種開発に挑戦する山形県立置賜農業高等学校
バイテク情報普及会は、高校生による「植物バイオテクノロジー」や「持続可能な農業」に関する科学教育活動を支援する「高校生科学教育大賞」の第9回受賞校を決定した。
最優秀賞には、日本農業遺産に登録されている「最上紅花」の遺伝子解析とゲノム編集による新品種開発に挑戦する山形県立置賜農業高等学校が選ばれ、申請額満額となる100万円の活動費が支援される。

バイテク情報普及会は、植物科学やバイテク作物の開発企業で構成する国際組織「クロップライフ・インターナショナル」傘下の任意団体。2001年10月1日の設立以来、「クロップライフ・インターナショナル」のビジョンである持続可能な農業の実現や食料の安定供給への貢献を念頭に、科学的知見に基づく許認可システムの構築を支援するための活動やバイオテクノロジーに関する広報活動を行っている。
「高校生科学教育大賞」は、次世代を担う高校生が「植物バイオテクノロジー」と「持続可能な農業」について深く学ぶ機会を提供することを目的に2017年に創設された。バイテク情報普及会が全国の高等学校を対象に毎年公募を行い、採択校に最大100万円の活動費支援を行っている。
第9回となる今回は、全国から21件の応募が寄せられた。筑波大学生命環境系准教授 小野道之氏、大阪公立大学大学院農学研究科教授 小泉望氏、食生活ジャーナリストの会・前代表 小島正美氏、農林水産省消費・安全局農産安全管理課審査官 高島賢氏といった有識者に加え、同会会員企業により構成された選考委員会にて審査した結果、以下のとおり受賞校が決定した。
山形県立置賜農業高等学校(山形県川西町)
「山形県の花『最上紅花』の遺伝子解析およびゲノム編集による新品種開発に関する研究~植物バイオテクノロジーを学ぶ高校生の挑戦~」
(選考理由)
・日本農業遺産に登録されている「最上紅花」を題材に、抗酸化成分カルタミンの増加や病害虫耐性の付与を目指してゲノム編集に取り組む意欲的な研究。伝統作物の改良に最先端のバイオ技術を導入し新品種の創出を目指す姿勢は、まるでベンチャー企業のような挑戦精神を感じさせる。
・地域資源の活用や品種改良にとどまらず、加工食品の開発も視野に入れている点も高く評価できる。
・実験の様子を動画にまとめ、SNS等で発信するほか、遺伝子組換えやゲノム編集に関する情報を小中学生やメディアに向けて発信するアウトリーチ活動も計画しており、科学技術の社会的理解を促す取り組みとしても注目に値する。
大分県立大分舞鶴高等学校(大分県大分市)
「植物の防御応答遺伝子の発現解析から広げる生徒主体の中高生バイオテクノロジー講習会」
・生徒が主体的にバイオテクノロジーを学び、その成果を中高生向け研修会で発信する優れたアウトリーチ活動。高校生自身が講師を務めることで、社会的受容の促進にもつながると期待される。
・廃棄パン酵母を活用し、植物の成長促進や病害ワクチンへの応用を目指す独自の発想も高く評価された。
兵庫県立農業高等学校(兵庫県加古川市)
「DNAマーカー技術を利用した酒米新品種の育成と実用化研究」
・DNAマーカー技術を用いて酒米「山田錦」の改良から日本酒醸造までを見据えた実用化への計画を立てた点が高く評価される。育種の本質に向き合い、品種登録を目指す計画的な取り組みは、高校生の柔軟な発想と探究心に富んでいる。
・研究機関との連携による実現性の高さや、普及の難しさに挑む姿勢にも将来性が感じられる、非常に優れた研究である。
津田学園高等学校(三重県桑名市)
「タデ藍栽培におけるインジカンの収量変動に及ぼす要因の解明」
藍染めの原料として知られるタデアイに含まれるインジカンの収量変動要因を探る本研究は、植物のストレス応答や食害耐性の可能性にも迫る学びの広がりを持った取り組みであり、大学と連携した高度な実験の実施に加え、地域とつながり多くの関係者が関わる継続的な活動としても高く評価された。
愛知県立安城農林高等学校(愛知県安城市)
「キンリョウヘンのもつニホンミツバチ誘引物質に関連する遺伝子配列の探索」
ニホンミツバチ誘引物質の合成に関わる遺伝子配列の特定を目指す本研究は、高校生にとって難易度が高いものの意欲的な挑戦であり、RNAシークエンスやPCRなどの分子生物学的手法を取り入れ、計画的に取り組む姿勢が高く評価された。
広尾学園高等学校(東京都港区)
「大腸菌を用いたじゃばら由来ナリルチンの合成による抗アレルギー物質の生産」
遺伝子組み換え技術を用いて、花粉症に効果があるナリルチンの微生物による生合成に挑むという非常に意欲的な研究であり、さらに絵本やアプリを活用した教育・啓発活動も計画するなど、社会への発信力を備えた点も高く評価された。
東京都立科学技術高等学校(東京都江東区)
「『DNAの抽出実験をモデルとした脱出ゲーム』の文化祭への出展」
DNA抽出実験と脱出ゲームを組み合わせた斬新な発想が光る、高校生にも親しみやすいサイエンスコミュニケーション活動であり、文化祭という場を活用して、誰もが楽しみながら科学に触れられるよう工夫された点が秀逸である。
2025年 高校生科学教育大賞 授賞校一覧
https://cbijapan.com/education/
バイテク情報普及会
https://cbijapan.com/
最優秀賞には、日本農業遺産に登録されている「最上紅花」の遺伝子解析とゲノム編集による新品種開発に挑戦する山形県立置賜農業高等学校が選ばれ、申請額満額となる100万円の活動費が支援される。

高校生がゲノム編集で新品種の開発に挑戦
バイテク情報普及会は、植物科学やバイテク作物の開発企業で構成する国際組織「クロップライフ・インターナショナル」傘下の任意団体。2001年10月1日の設立以来、「クロップライフ・インターナショナル」のビジョンである持続可能な農業の実現や食料の安定供給への貢献を念頭に、科学的知見に基づく許認可システムの構築を支援するための活動やバイオテクノロジーに関する広報活動を行っている。
「高校生科学教育大賞」は、次世代を担う高校生が「植物バイオテクノロジー」と「持続可能な農業」について深く学ぶ機会を提供することを目的に2017年に創設された。バイテク情報普及会が全国の高等学校を対象に毎年公募を行い、採択校に最大100万円の活動費支援を行っている。
第9回となる今回は、全国から21件の応募が寄せられた。筑波大学生命環境系准教授 小野道之氏、大阪公立大学大学院農学研究科教授 小泉望氏、食生活ジャーナリストの会・前代表 小島正美氏、農林水産省消費・安全局農産安全管理課審査官 高島賢氏といった有識者に加え、同会会員企業により構成された選考委員会にて審査した結果、以下のとおり受賞校が決定した。
最優秀賞(申請額満額の100万円を支援)
山形県立置賜農業高等学校(山形県川西町)
「山形県の花『最上紅花』の遺伝子解析およびゲノム編集による新品種開発に関する研究~植物バイオテクノロジーを学ぶ高校生の挑戦~」
(選考理由)
・日本農業遺産に登録されている「最上紅花」を題材に、抗酸化成分カルタミンの増加や病害虫耐性の付与を目指してゲノム編集に取り組む意欲的な研究。伝統作物の改良に最先端のバイオ技術を導入し新品種の創出を目指す姿勢は、まるでベンチャー企業のような挑戦精神を感じさせる。
・地域資源の活用や品種改良にとどまらず、加工食品の開発も視野に入れている点も高く評価できる。
・実験の様子を動画にまとめ、SNS等で発信するほか、遺伝子組換えやゲノム編集に関する情報を小中学生やメディアに向けて発信するアウトリーチ活動も計画しており、科学技術の社会的理解を促す取り組みとしても注目に値する。
特別優秀賞(2校、各校に活動費の一部として15万円を支援)
大分県立大分舞鶴高等学校(大分県大分市)
「植物の防御応答遺伝子の発現解析から広げる生徒主体の中高生バイオテクノロジー講習会」
・生徒が主体的にバイオテクノロジーを学び、その成果を中高生向け研修会で発信する優れたアウトリーチ活動。高校生自身が講師を務めることで、社会的受容の促進にもつながると期待される。
・廃棄パン酵母を活用し、植物の成長促進や病害ワクチンへの応用を目指す独自の発想も高く評価された。
兵庫県立農業高等学校(兵庫県加古川市)
「DNAマーカー技術を利用した酒米新品種の育成と実用化研究」
・DNAマーカー技術を用いて酒米「山田錦」の改良から日本酒醸造までを見据えた実用化への計画を立てた点が高く評価される。育種の本質に向き合い、品種登録を目指す計画的な取り組みは、高校生の柔軟な発想と探究心に富んでいる。
・研究機関との連携による実現性の高さや、普及の難しさに挑む姿勢にも将来性が感じられる、非常に優れた研究である。
優秀賞(3校、各校に活動費の一部として5万円を支援)
津田学園高等学校(三重県桑名市)
「タデ藍栽培におけるインジカンの収量変動に及ぼす要因の解明」
藍染めの原料として知られるタデアイに含まれるインジカンの収量変動要因を探る本研究は、植物のストレス応答や食害耐性の可能性にも迫る学びの広がりを持った取り組みであり、大学と連携した高度な実験の実施に加え、地域とつながり多くの関係者が関わる継続的な活動としても高く評価された。
愛知県立安城農林高等学校(愛知県安城市)
「キンリョウヘンのもつニホンミツバチ誘引物質に関連する遺伝子配列の探索」
ニホンミツバチ誘引物質の合成に関わる遺伝子配列の特定を目指す本研究は、高校生にとって難易度が高いものの意欲的な挑戦であり、RNAシークエンスやPCRなどの分子生物学的手法を取り入れ、計画的に取り組む姿勢が高く評価された。
広尾学園高等学校(東京都港区)
「大腸菌を用いたじゃばら由来ナリルチンの合成による抗アレルギー物質の生産」
遺伝子組み換え技術を用いて、花粉症に効果があるナリルチンの微生物による生合成に挑むという非常に意欲的な研究であり、さらに絵本やアプリを活用した教育・啓発活動も計画するなど、社会への発信力を備えた点も高く評価された。
バイテク情報普及会賞(活動費の一部として4万円を支援)
東京都立科学技術高等学校(東京都江東区)
「『DNAの抽出実験をモデルとした脱出ゲーム』の文化祭への出展」
DNA抽出実験と脱出ゲームを組み合わせた斬新な発想が光る、高校生にも親しみやすいサイエンスコミュニケーション活動であり、文化祭という場を活用して、誰もが楽しみながら科学に触れられるよう工夫された点が秀逸である。
2025年 高校生科学教育大賞 授賞校一覧
https://cbijapan.com/education/
バイテク情報普及会
https://cbijapan.com/
SHARE