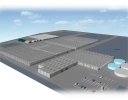ピンポイント農薬散布のセミナーも オンラインイベント「サイエンスアゴラ2020」が11月13日に開幕
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)は、科学と社会の関係を深めるための10日間のオンラインイベント「サイエンスアゴラ2020」を、2020年11月13日(金)〜22日(日)に開催する。参加は無料で、一部セミナーは事前登録が必要。

2020年のテーマは「Life」。新型コロナウイルス感染症により、急速に社会やライフスタイルが変化する中で、明るい未来社会を支えるための科学技術イノベーションについて議論する場となる。
開幕セッションでは、コロナ禍を踏まえた目指すべき未来社会像について、日本電信電話(NTT)取締役会長の篠原 弘道氏、IBM T.J.ワトソン研究所フェローの浅川智恵子氏ら有識者らとともに、デジタルトランスフォーメーションやインクルーシブの観点など、さまざまな角度から考えていく。
また、開幕と同時にいつでも閲覧可能になるオンデマンド配信企画のほか、ライブ配信企画も後日アーカイブでも閲覧可能。公募により集められた約100件もの企画を探すために、AIよるオススメ企画の案内機能もある。
13日〜14日は「プレアゴラ」として、スイス大使館とJSTが共催する国際競技大会サイバスロン(東京会場)のほか、IVRC決勝大会、サイエンスアゴラ前夜祭などを実施予定。本格的な企画は15日からとなっている。
なお、17日の16:00〜16:00にかけて、「AI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術とSDGsへの貢献」というタイトルで株式会社オプティムがピンポイント農薬散布・施肥テクノロジーの事例紹介とSDGsへの貢献について講演を行うほか、農業分野の企画も多数用意されている。
11月17日(火)16:00-16:40
AI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術とSDGsへの貢献(株式会社オプティム) 株式会社オプティムのAI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術「ピンポイント農薬散布・施肥テクノロジー」を活用した生産現場での事例紹介と、 SDGsへの貢献についてのプレゼンテーション。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1703.html
11月18日(水)10:00-12:00
~京都の里山ライフ~SDGsライブ中継(京都超SDGsコンソーシアム)
SDGs・持続可能性にヒントになる様々な知恵や工夫がつまった里山の暮らしを、京都の里山とオンラインでつないで、いくつかの象徴的な場所と人、知恵や工夫を紹介。 これからの働き方、里山での暮らし方(ワーケーション、パラレルワーク等々)へのヒントも。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1801.html
11月19日(木)18:15-19:45
「究極」のイチゴ、量子科学技術でお届けします(量子科学技術研究開発機構)
人の循環器と同様に備わっている、植物の「運ぶ力」を観察可能にした量子科学を駆使した「ミる技術」のRIイメージング。 この「ミる技術」が可視化したイチゴの「運ぶ力」を入り口に、植物の中の動きを追い続ける研究者と、「量子科学技術でつくる私たちの未来」を考える。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1905.html
11月21日(土)13:00-15:00
サステイナブル・バイオテクノロジー(東京薬科大学 生命科学部 生命エネルギー工学研究室)
生物の力をSDGsの実現に役立てていくサステイナブルバイオテクノロジーについて考察。参加者が小グループに分かれて世代横断的ディスカッションを行い、“夢のサステイナブルバイオテクノロジー”を提案する。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2107.html
11月22日(日)13:00-14:30
食べる?食べない?ゲノム編集マダイ(ゲノム編集の未来を考える会)
実用化が近いと言われるゲノム編集食品への向き合い方を継続的に考えていくために、情報提供および意見交換・共有する。 具体例としてゲノム編集技術によって作出された肉厚マダイを紹介し、 ゲノム編集食品の実用化に向けた多方面からの意見や課題の共有を目指す。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2207.html
11月22日(日)15:00-16:30
命の価値 ~生物多様性から考える~(生物多様性保全協会)
持続可能な生活のあり方を「命とは何か?」という原点から考察。外来生物カミツキガメや衛生害虫ゴキブリ、家畜の牛や豚、そして私たち人間など、「生物」の視点で「命の価値」を再考する。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2211.html
11月22日(日)17:30-19:00
分子でアフリカを救う!?魔女の雑草を騙す研究物語(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所)
穀類に寄生し枯らすため「魔女の雑草」と呼ばれるアフリカの寄生植物ストライガ。宿主が出す分子を感知して発芽し寄生する仕組みを逆手にとり、分子で騙して発芽させることに成功した。 この仕組み発見のエピソードや現地の様子を映像を交えて紹介。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2218.html
これら以外にも、毎日研究者向け、子ども向けのさまざまな企画が用意されている。
主催:国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
協賛:旭化成株式会社、エルゼビア・ジャパン株式会社、株式会社学研ホールディングス、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本電気株式会社、日本電信電話株式会社(五十音順)
特別協力:スイス大使館
協力:株式会社東京テレポートセンター、株式会社フジテレビジョン、国立大学法人京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab、Wiley BASE Q
後援:内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省、日本学術会議、一般社団法人 日本経済団体連合会、一般社団法人 国立大学協会、日本私立大学団体連合会、国立研究開発法人 理化学研究所、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、ジャパンSDGsアクション推進協議会、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
サイエンスアゴラ2020
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/

2020年のテーマは「Life」。新型コロナウイルス感染症により、急速に社会やライフスタイルが変化する中で、明るい未来社会を支えるための科学技術イノベーションについて議論する場となる。
開幕セッションでは、コロナ禍を踏まえた目指すべき未来社会像について、日本電信電話(NTT)取締役会長の篠原 弘道氏、IBM T.J.ワトソン研究所フェローの浅川智恵子氏ら有識者らとともに、デジタルトランスフォーメーションやインクルーシブの観点など、さまざまな角度から考えていく。
また、開幕と同時にいつでも閲覧可能になるオンデマンド配信企画のほか、ライブ配信企画も後日アーカイブでも閲覧可能。公募により集められた約100件もの企画を探すために、AIよるオススメ企画の案内機能もある。
13日〜14日は「プレアゴラ」として、スイス大使館とJSTが共催する国際競技大会サイバスロン(東京会場)のほか、IVRC決勝大会、サイエンスアゴラ前夜祭などを実施予定。本格的な企画は15日からとなっている。
なお、17日の16:00〜16:00にかけて、「AI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術とSDGsへの貢献」というタイトルで株式会社オプティムがピンポイント農薬散布・施肥テクノロジーの事例紹介とSDGsへの貢献について講演を行うほか、農業分野の企画も多数用意されている。
主な農業関連企画
11月17日(火)16:00-16:40
AI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術とSDGsへの貢献(株式会社オプティム) 株式会社オプティムのAI・IoT・ロボットを活用したスマート農業技術「ピンポイント農薬散布・施肥テクノロジー」を活用した生産現場での事例紹介と、 SDGsへの貢献についてのプレゼンテーション。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1703.html
11月18日(水)10:00-12:00
~京都の里山ライフ~SDGsライブ中継(京都超SDGsコンソーシアム)
SDGs・持続可能性にヒントになる様々な知恵や工夫がつまった里山の暮らしを、京都の里山とオンラインでつないで、いくつかの象徴的な場所と人、知恵や工夫を紹介。 これからの働き方、里山での暮らし方(ワーケーション、パラレルワーク等々)へのヒントも。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1801.html
11月19日(木)18:15-19:45
「究極」のイチゴ、量子科学技術でお届けします(量子科学技術研究開発機構)
人の循環器と同様に備わっている、植物の「運ぶ力」を観察可能にした量子科学を駆使した「ミる技術」のRIイメージング。 この「ミる技術」が可視化したイチゴの「運ぶ力」を入り口に、植物の中の動きを追い続ける研究者と、「量子科学技術でつくる私たちの未来」を考える。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1905.html
11月21日(土)13:00-15:00
サステイナブル・バイオテクノロジー(東京薬科大学 生命科学部 生命エネルギー工学研究室)
生物の力をSDGsの実現に役立てていくサステイナブルバイオテクノロジーについて考察。参加者が小グループに分かれて世代横断的ディスカッションを行い、“夢のサステイナブルバイオテクノロジー”を提案する。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2107.html
11月22日(日)13:00-14:30
食べる?食べない?ゲノム編集マダイ(ゲノム編集の未来を考える会)
実用化が近いと言われるゲノム編集食品への向き合い方を継続的に考えていくために、情報提供および意見交換・共有する。 具体例としてゲノム編集技術によって作出された肉厚マダイを紹介し、 ゲノム編集食品の実用化に向けた多方面からの意見や課題の共有を目指す。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2207.html
11月22日(日)15:00-16:30
命の価値 ~生物多様性から考える~(生物多様性保全協会)
持続可能な生活のあり方を「命とは何か?」という原点から考察。外来生物カミツキガメや衛生害虫ゴキブリ、家畜の牛や豚、そして私たち人間など、「生物」の視点で「命の価値」を再考する。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2211.html
11月22日(日)17:30-19:00
分子でアフリカを救う!?魔女の雑草を騙す研究物語(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所)
穀類に寄生し枯らすため「魔女の雑草」と呼ばれるアフリカの寄生植物ストライガ。宿主が出す分子を感知して発芽し寄生する仕組みを逆手にとり、分子で騙して発芽させることに成功した。 この仕組み発見のエピソードや現地の様子を映像を交えて紹介。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_2218.html
これら以外にも、毎日研究者向け、子ども向けのさまざまな企画が用意されている。
開催概要
日程:プレアゴラ 2020年11月13日(金)〜 14日(土)/サイエンスアゴラ 2020年11月15(日)〜22日(日)主催:国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
協賛:旭化成株式会社、エルゼビア・ジャパン株式会社、株式会社学研ホールディングス、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本電気株式会社、日本電信電話株式会社(五十音順)
特別協力:スイス大使館
協力:株式会社東京テレポートセンター、株式会社フジテレビジョン、国立大学法人京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab、Wiley BASE Q
後援:内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省、日本学術会議、一般社団法人 日本経済団体連合会、一般社団法人 国立大学協会、日本私立大学団体連合会、国立研究開発法人 理化学研究所、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、ジャパンSDGsアクション推進協議会、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
サイエンスアゴラ2020
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/
SHARE