喫緊の農業の課題を人口減少の視点から考える書籍『人口減少時代の農業と食』発売
筑摩書房は、2023年5月11日にちくま新書より書籍『人口減少時代の農業と食』を発売した。価格は1012円(税込)。
窪田新之助氏は元・日本農業新聞記者の農業ジャーナリスト。農業問題・中国問題に精通するジャーナリストの山口亮子氏との共著として、日本の農政の問題点を現場視点で徹底的に追求している。
本書では、人口減少で日本の農業はどうなっていくのか、農家はもちろん出荷や流通、販売や商品開発など危機と課題、また新たな潮流やアイデアを現場取材し、農業のいまを報告する。
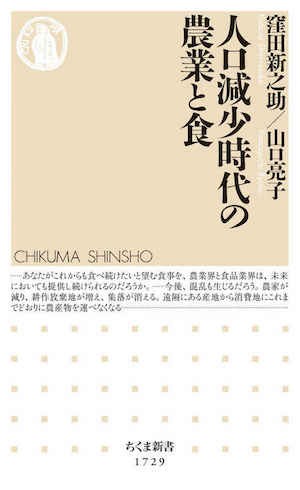
人口減少で日本の農業はどうなるか。農家はもちろん出荷や流通、販売や商品開発など危機と課題、また新たな潮流やアイデアを現場取材、農業のいまを報告する。 日本農業にとって人口減少は諸刃の剣といえる。これまでのあり方を一部で壊してしまう一方で、変革の推進力にもなる。
農産物の生産や流通は、総じて人手不足で、生産者と流通、販売、消費の間の溝やズレも明らかになっている。ピンチをチャンスに変えるべく、こうした課題に立ち向かう現場がある。生産から出荷までの合理化、消費者と直接つながる商品の開発、物流のルール変更への対応……。世間で思われているほど暗くない、日本農業の未来を報告しよう。
はじめに
第一章 データで見る農と食のいまとこれから
1 増え続ける外国人労働者と待ち受ける危機
2 二〇二四年問題──関東で「あまおう」が食べられなくなる!?
3 集出荷施設の老朽化で青果流通に不安
4 多くの農業集落で存続に黄信号
5 耕作放棄地の増加と懸念
6 農家の減少と高齢化
7 一人当たり三倍の農地を耕す未来
8 もはや主食ではないコメ
9 単身世帯の急増で伸びる加工・業務用
10 食い込むべきは世界の食品市場
第二章 危機にある物流
1 積載率を高める保管施設
2 「あまおう」は関東圏に届くのか
3 北海道新幹線延伸に伴う「並行在来線問題」
4 鮮度を保ったまま大消費地に小ネギを届ける物流とは
5 「保管」という物流の新たな価値
6 「やさいバス」、コロナ禍で主な取引先は飲食店から小売店にシフト
第三章 待ったなしの農業関連施設の再整備
1 農家とドライバーの負担を減らす「東洋一」の選果場
2 イチゴの選果と調製を請け負うパッケージセンター
3 共同選果と産地づくりをセットで
第四章 大規模化への備え
1 集落営農の将来像
2 いま兼業農家を育てる理由
3 農業法人が稲作専門の作業管理アプリを開発した理由とは
4 労働生産性の向上に不可欠なデータ
5 規模拡大の前提となる働きやすい環境づくり
第五章 外国人、都市住民からロボットまで
1 頼みは外国人技能実習生
2 都市住民を産地に呼び込む
3 「アグリナジカン」の試み
4 障害者の就労支援と農業
5 北海道から広がるロボット農機の可能性
6 除草の現在地
第六章 消費者が迫る変化、日本文化を世界へ
1 市場を奪われる国産
2 調理しない未来を予想する農業生産法人
3 不調のコメ、好調のパックライス、冷凍米飯
4 民間発の小麦国産化
5 人口減少でも増えるチーズの需要
6 日本酒の味を変えた輸出の波
7 魅力的な品種、ガタガタの輸出戦略
おわりに
著者:窪田新之助、山口亮子
発売日:5月11日
造本:新書
本体定価:1012円(税込)
発行:筑摩書房
URL:https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480075543/
窪田新之助氏は元・日本農業新聞記者の農業ジャーナリスト。農業問題・中国問題に精通するジャーナリストの山口亮子氏との共著として、日本の農政の問題点を現場視点で徹底的に追求している。
本書では、人口減少で日本の農業はどうなっていくのか、農家はもちろん出荷や流通、販売や商品開発など危機と課題、また新たな潮流やアイデアを現場取材し、農業のいまを報告する。
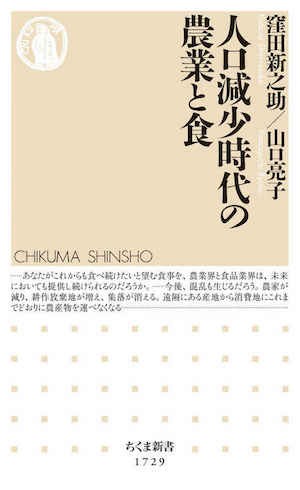
書籍概要
人口減少で日本の農業はどうなるか。農家はもちろん出荷や流通、販売や商品開発など危機と課題、また新たな潮流やアイデアを現場取材、農業のいまを報告する。 日本農業にとって人口減少は諸刃の剣といえる。これまでのあり方を一部で壊してしまう一方で、変革の推進力にもなる。
農産物の生産や流通は、総じて人手不足で、生産者と流通、販売、消費の間の溝やズレも明らかになっている。ピンチをチャンスに変えるべく、こうした課題に立ち向かう現場がある。生産から出荷までの合理化、消費者と直接つながる商品の開発、物流のルール変更への対応……。世間で思われているほど暗くない、日本農業の未来を報告しよう。
「人口減少時代の農業と食」目次
はじめに
第一章 データで見る農と食のいまとこれから
1 増え続ける外国人労働者と待ち受ける危機
2 二〇二四年問題──関東で「あまおう」が食べられなくなる!?
3 集出荷施設の老朽化で青果流通に不安
4 多くの農業集落で存続に黄信号
5 耕作放棄地の増加と懸念
6 農家の減少と高齢化
7 一人当たり三倍の農地を耕す未来
8 もはや主食ではないコメ
9 単身世帯の急増で伸びる加工・業務用
10 食い込むべきは世界の食品市場
第二章 危機にある物流
1 積載率を高める保管施設
2 「あまおう」は関東圏に届くのか
3 北海道新幹線延伸に伴う「並行在来線問題」
4 鮮度を保ったまま大消費地に小ネギを届ける物流とは
5 「保管」という物流の新たな価値
6 「やさいバス」、コロナ禍で主な取引先は飲食店から小売店にシフト
第三章 待ったなしの農業関連施設の再整備
1 農家とドライバーの負担を減らす「東洋一」の選果場
2 イチゴの選果と調製を請け負うパッケージセンター
3 共同選果と産地づくりをセットで
第四章 大規模化への備え
1 集落営農の将来像
2 いま兼業農家を育てる理由
3 農業法人が稲作専門の作業管理アプリを開発した理由とは
4 労働生産性の向上に不可欠なデータ
5 規模拡大の前提となる働きやすい環境づくり
第五章 外国人、都市住民からロボットまで
1 頼みは外国人技能実習生
2 都市住民を産地に呼び込む
3 「アグリナジカン」の試み
4 障害者の就労支援と農業
5 北海道から広がるロボット農機の可能性
6 除草の現在地
第六章 消費者が迫る変化、日本文化を世界へ
1 市場を奪われる国産
2 調理しない未来を予想する農業生産法人
3 不調のコメ、好調のパックライス、冷凍米飯
4 民間発の小麦国産化
5 人口減少でも増えるチーズの需要
6 日本酒の味を変えた輸出の波
7 魅力的な品種、ガタガタの輸出戦略
おわりに
「人口減少時代の農業と食」書籍情報
著者:窪田新之助、山口亮子
発売日:5月11日
造本:新書
本体定価:1012円(税込)
発行:筑摩書房
URL:https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480075543/
SHARE

















































