ロボットトラクター1台でばれいしょの無人収穫を実証 収穫労務費を4割削減
帯広畜産大学の佐藤禎稔教授とヤンマーが、無人で走行するロボットトラクター(ロボトラ)によるばれいしょの収穫を実験して成功した。
2019年には佐藤教授に、「ロボットトラクターは畑作では使えない」という主旨のインタビューを行っているが、それが1年経って解決したかたちだ。
ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】
https://smartagri-jp.com/smartagri/883
ロボットトラクターはなぜ畑作で使えないのか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<後編>【特集・北の大地の挑戦 第9回】
https://smartagri-jp.com/smartagri/884
これで耕うんから種イモの植え付け、農薬の散布まで含めた一貫体系を、1台のロボトラでできることを確かめたことになる。ロボトラを使いこなせば労務費の4割削減が可能とみている。
佐藤禎稔(さとう ただとし)
帯広畜産大学 畜産学部 教授
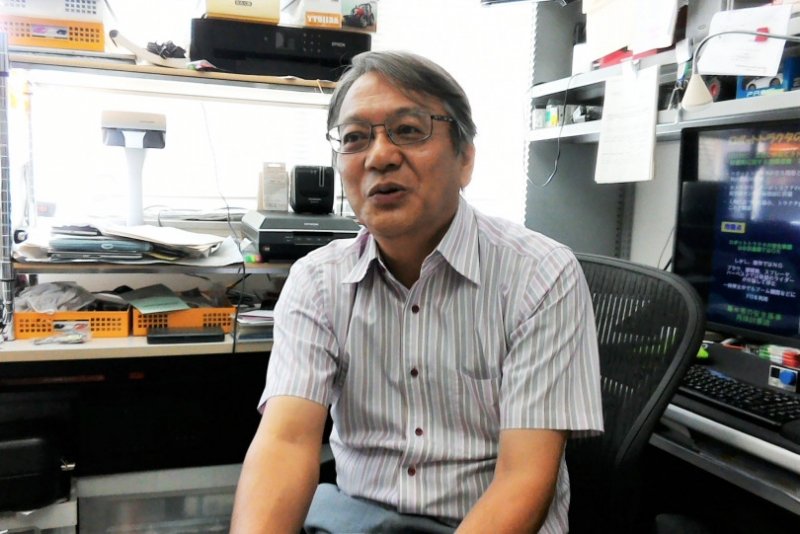
過去の連載で紹介したように、ロボトラを畑作で利用するうえで課題となるのは、リバーシブルプラウとブームスプレーヤー、ポテトハーベスターという3つの作業機と連携できないことである。両者は、このうちリバーシブルプラウとブームスプレーヤーの2つについては、2018年度までの実験で課題を克服した。
残るポテトハーベスターについては、ロボトラだとけん引バックができないのが課題だった。ばれいしょの収穫時に畦数が少ないと、旋回ができないので全面収穫ができない。結果、取り残しが出てしまう。

そこで今回の実験ではけん引バックをしなくても、ある手法を使えば全面収穫ができるようになった。あいにく「ある手法」については特許の絡みで現時点では公にできないそうだ。
※けん引車両でのバック操作は、乗車しているトラクターに加えて、けん引車両の動きもコントロールしなければならない。ロボットトラクターではけん引車両のサイズなども含めてバック操作が行えない。
今回の実験でもう一つ試したのは、ロボトラではなくポテトハーベスターの選別ステージにタブレット端末を取り付けて、堀取りの稼働や停止のほか、走行速度や経路の設定などの操作である。
ばれいしょの収穫でロボトラによる無人のけん引作業を目指した理由は、トラクターのオペレーターの削減と安全確保のためである。
タブレット端末をロボトラに取り付けていると、枕地旋回などで操作の必要が生じるたびに、走行中にもかかわらず人がポテトハーベスターから降りてロボトラに向かわねばならない。
北海道の畑作地帯では、従来のトラクターでポテトハーベスターをけん引している最中、人がトラクターから乗り降りした際にひかれる事故が後を絶たない。
実験ではポテトハーベスターからの操作も支障はなく、佐藤教授は「作業精度も良く、完璧に収穫できました」と語る。
ロボトラによる作業の一貫体系をつくるにあたって、北海道の畑作4品目の中でばれいしょを実験の対象に選んだのは「畑作の中で作業が一番難しいし、回数も種類も多いため」(佐藤教授)。
ばれいしょでトラクターを使うのは、ブロードキャスターでの肥料の散布やリバーシブルプラウ、ディスクハロー、ロータリーハローで耕うんと砕土、整地をするなど合計すれば20回にも及ぶ。
「ばれいしょでロボトラによる作業の一貫体系ができればビートや麦、豆類でも問題なく使える」
佐藤教授らは共同研究で北海道の畑作4品目にかかる労務費の4割削減を目指してきた。ポテトハーベスターの実験に成功し、その達成にめどをつけた。
ロボトラの監視を圃場ごとに行わなければならないとすると、GPSガイダンストラクターと同様に労働者の削減はほとんど期待できない。費用対効果が見合う活用をするうえで前提となるのは、遠隔監視によって1人が複数台のロボトラの作業の監視と制御を同時にすることである。
遠隔地のモニター画面で複数のロボトラを同時に監視し、制御する実験も始まっている。しかし、北海道の畑作地帯では府県と違って分散錯圃ではなく、個々の農家が耕作する農地はおおむねまとまっている。
この利点を生かして、例えば一人が畑の真ん中の位置にいて監視しながら、隣接する4つの畑で同時に4台のロボトラを走行させることを想定している。
ロボトラはその可能性が広く社会的に注目されているが、生産現場に落とし込むという点ではいろいろと課題が残されている。
それを丹念につぶしてきた佐藤教授とヤンマーの今回の研究は高く評価されるべきである。加えて北海道の農業現場は府県以上に労働力不足が深刻であることから、早く実装されることを願いたい。
2019年には佐藤教授に、「ロボットトラクターは畑作では使えない」という主旨のインタビューを行っているが、それが1年経って解決したかたちだ。
ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】
https://smartagri-jp.com/smartagri/883
ロボットトラクターはなぜ畑作で使えないのか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<後編>【特集・北の大地の挑戦 第9回】
https://smartagri-jp.com/smartagri/884
これで耕うんから種イモの植え付け、農薬の散布まで含めた一貫体系を、1台のロボトラでできることを確かめたことになる。ロボトラを使いこなせば労務費の4割削減が可能とみている。
佐藤禎稔(さとう ただとし)
帯広畜産大学 畜産学部 教授
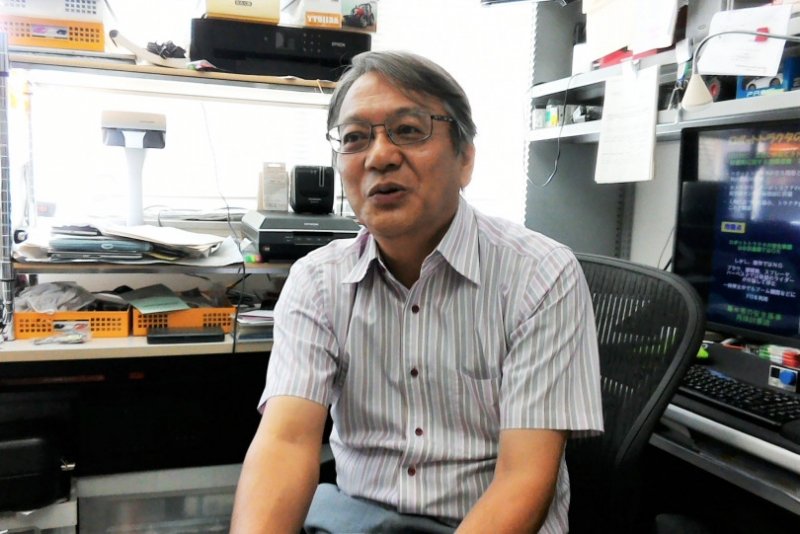
けん引バックなしでも全面収穫可能に
過去の連載で紹介したように、ロボトラを畑作で利用するうえで課題となるのは、リバーシブルプラウとブームスプレーヤー、ポテトハーベスターという3つの作業機と連携できないことである。両者は、このうちリバーシブルプラウとブームスプレーヤーの2つについては、2018年度までの実験で課題を克服した。
残るポテトハーベスターについては、ロボトラだとけん引バックができないのが課題だった。ばれいしょの収穫時に畦数が少ないと、旋回ができないので全面収穫ができない。結果、取り残しが出てしまう。

そこで今回の実験ではけん引バックをしなくても、ある手法を使えば全面収穫ができるようになった。あいにく「ある手法」については特許の絡みで現時点では公にできないそうだ。
※けん引車両でのバック操作は、乗車しているトラクターに加えて、けん引車両の動きもコントロールしなければならない。ロボットトラクターではけん引車両のサイズなども含めてバック操作が行えない。
タブレット端末は作業機側に設置
今回の実験でもう一つ試したのは、ロボトラではなくポテトハーベスターの選別ステージにタブレット端末を取り付けて、堀取りの稼働や停止のほか、走行速度や経路の設定などの操作である。
ばれいしょの収穫でロボトラによる無人のけん引作業を目指した理由は、トラクターのオペレーターの削減と安全確保のためである。
タブレット端末をロボトラに取り付けていると、枕地旋回などで操作の必要が生じるたびに、走行中にもかかわらず人がポテトハーベスターから降りてロボトラに向かわねばならない。
北海道の畑作地帯では、従来のトラクターでポテトハーベスターをけん引している最中、人がトラクターから乗り降りした際にひかれる事故が後を絶たない。
実験ではポテトハーベスターからの操作も支障はなく、佐藤教授は「作業精度も良く、完璧に収穫できました」と語る。
労務費の4割削減にめど
ロボトラによる作業の一貫体系をつくるにあたって、北海道の畑作4品目の中でばれいしょを実験の対象に選んだのは「畑作の中で作業が一番難しいし、回数も種類も多いため」(佐藤教授)。
ばれいしょでトラクターを使うのは、ブロードキャスターでの肥料の散布やリバーシブルプラウ、ディスクハロー、ロータリーハローで耕うんと砕土、整地をするなど合計すれば20回にも及ぶ。
「ばれいしょでロボトラによる作業の一貫体系ができればビートや麦、豆類でも問題なく使える」
佐藤教授らは共同研究で北海道の畑作4品目にかかる労務費の4割削減を目指してきた。ポテトハーベスターの実験に成功し、その達成にめどをつけた。
ロボトラの監視を圃場ごとに行わなければならないとすると、GPSガイダンストラクターと同様に労働者の削減はほとんど期待できない。費用対効果が見合う活用をするうえで前提となるのは、遠隔監視によって1人が複数台のロボトラの作業の監視と制御を同時にすることである。
遠隔地のモニター画面で複数のロボトラを同時に監視し、制御する実験も始まっている。しかし、北海道の畑作地帯では府県と違って分散錯圃ではなく、個々の農家が耕作する農地はおおむねまとまっている。
この利点を生かして、例えば一人が畑の真ん中の位置にいて監視しながら、隣接する4つの畑で同時に4台のロボトラを走行させることを想定している。
ロボトラはその可能性が広く社会的に注目されているが、生産現場に落とし込むという点ではいろいろと課題が残されている。
それを丹念につぶしてきた佐藤教授とヤンマーの今回の研究は高く評価されるべきである。加えて北海道の農業現場は府県以上に労働力不足が深刻であることから、早く実装されることを願いたい。
SHARE















































