「技術ありきのスマート農業」になってはいないか──700haを束ねるある稲作農家の箴言
山形県三川町の株式会社まいすたぁは13ヘクタールで最新技術を使った稲作を展開する。
トラクターを自動操舵に対応させたり、高速で乾田直播(乾いた田んぼに種もみをまくこと)ができる機械を使ったり、水位や水温、気象データのとれる水田用センサーを38枚の田んぼすべてに設置したり。
ただ、1俵(60kg)当たりの生産費が1万円を切る低コストの稲作を目指す立場からすると、今のスマート農業に物足りなさを感じるという。
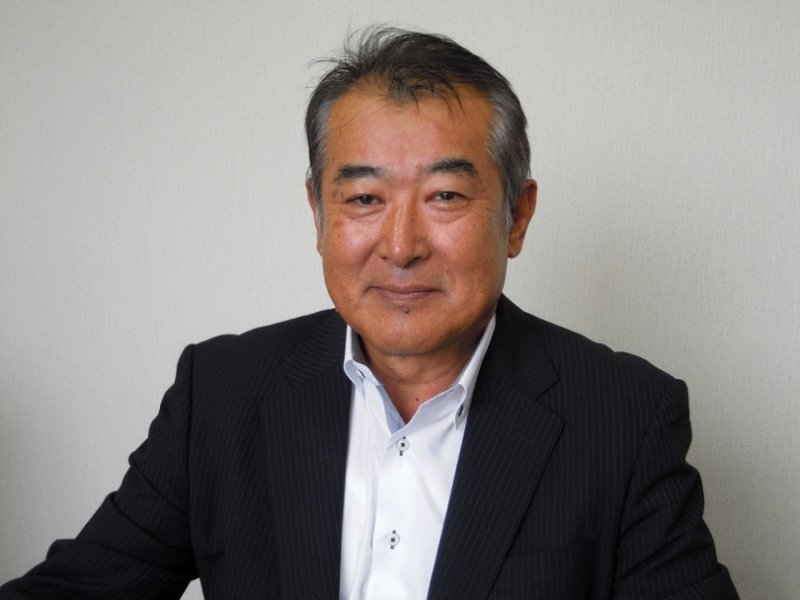 まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さん(写真提供:まいすたぁ)
まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さん(写真提供:まいすたぁ)
まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さんはこう話す。齋藤さんは集荷業を営む株式会社庄内こめ工房(山形県鶴岡市)の代表取締役を兼ねており、約90の生産者から約700ヘクタール分のコメを集荷する。面積を拡大しても効率化が進まなくなる「壁」の存在に生産者は頭を悩ませている。
「肥料・農薬といった物財費は、面積が広がってまとめ買いするようになっても、値段はほとんど変わらない。スケールメリットによるコストダウンは、稲作ではほとんどない。面積が広がると収量が落ちるので、逆にコストアップになってしまう」
問題を解決すべく、まいすたぁを2009年に設立した。積極的に新技術を採用し、同社の圃場を実証の場として企業や研究機関に提供する。同社で試したのを見て「これはいい」と思う生産者がいれば、出向いて作業したり、技術や機械を導入してもらったりしている。
 まいすたぁで所持するドローン
まいすたぁで所持するドローン
具体的には、株式会社マゼックスという国内メーカーのドローン1基を保有し、肥料や農薬をまく。ドローンの効率の良さはほかの生産者からも認められていて、自社の圃場だけでなく、作業を請け負ってほかの圃場でまくこともある。トラクターはハンドルを自動操舵対応のものに付け替え、誤差がわずかに1.5センチ程度という精度の高い作業が可能になった。圃場の均平に使うレーザーレベラーも自動操舵に対応している。
自前でこうした技術を取り入れるのはもちろん、民間企業や研究機関に実証の場を提供してもいる。今年の田植えでは、農研機構が開発した高速で乾田直播をする技術で播種した。山形大学農学部で開発中の各種センサーを搭載した4輪のロボットが、時おり田んぼの中を走っている。ほかに植生の分布状況や活性度を測るNDVIカメラを使って稲の葉色から生育具合を判断し、施肥に生かす試みもしている。
 乾田直播のようす
乾田直播のようす
コスト削減と省力化で期待を寄せるのが直播だ。鉄粉をコーティングした種子などを直播機で水を張った田んぼにまく湛水直播を試してきたが、あまりコスト削減の効果が感じられなかった。そのため、湛水直播をするのであれば、ドローンやヘリコプターを使った空中からの散布の方が効率的だと感じている。「ドリルシーダー」という播種専用のアタッチメントを使った乾田直播ならば、除草剤対策と水管理をきちんとすれば効果が高いという。
直播をするうえでは、圃場1枚あたりの面積を広げることが効率化にあたっては必須と指摘する。高速で作業するドリルシーダーで乾田直播をするに当たり、1枚30アールの田んぼ7枚を合わせて2.1ヘクタールの田んぼにした。これで効率は格段に上がる。
スマート農業に関して、国内メーカーが開発する稲作向けの製品には不満もあるという。作業スピードが遅く、応用が利きにくくて使いづらいのに値段は高いものが多いと感じるからだ。駆動力が不足していて、ぬかるんだ田んぼでは使えないロボット農機や、費用対効果が不明のセンサーなども中にはある。「海外製品と同じように高速で高精度の作業ができないと、農家が食えるようにはならない」と話す。
 まいすたぁが使用する水田用センサー
まいすたぁが使用する水田用センサー
「今のスマート農業は、技術系の人たちがフィーバーしているだけで、現場じゃ使えないというものが多い。これから目指すべきスマート農業とは違うし、しかも段々本来目指すべきものから離れていっている。工学系の人間には『古典的なことをやっている農家のために私の能力を提供しよう』という考えがあるようだけれども、開発したほとんどのものは使い物にならない」
開発には、農学と工学の研究者の連携が欠かせないと考えている。農学研究者がどのデータを使ってどの時期にどんな作業をして収量を上げるか、どんなアラームを発して病害の損失を減らすかというソフトの部分を作り、工学研究者が駆動力と応用力のあるハードを作る。このように双方向から開発を進めなければ、実用化までこぎつける製品がなかなか生まれてこないと指摘する。
営農支援ソフトにしても、使うことで収量が確実に上がる水準まで持っていくには、自然環境や投入資材と作業時期などの情報を総合して判断することが必要だと考えている。農学の中でも環境や土壌、植物生理、生態系といった広範な学問領域の研究者に情報をデータベース化してもらい、それに基づいていつ何をすべきかアドバイスできるようになれば、ベテラン農家が使えるものになると期待する。
「温暖化で日本の気候自体が変わっているために、雑草一つとっても、これまで自分の地域で出ていた雑草と全く違うものが見つかる。そういうものはベテラン農家でもさっぱりわからないから、写真を撮ってどこかに送れば、これは何でどういう対策が必要かという回答がもらえたりしたら、と思う」
海外には農家が直接専門家に質問できるサービスがあり、そうしたものが国内の稲作向けにできればぜひ使いたいという。
世にあふれる多様な技術の中から、いかにして適切なものを選び出し、農業の革新に貢献できる商品やサービスを作り出すのか。いくつかの学問分野にまたがった研究と開発、そして農家と専門家の連携こそ必要だというのが、齋藤さんの達した結論だ。
株式会社まいすたぁ-山形県三川町-最先端農業の実践
株式会社庄内こめ工房
トラクターを自動操舵に対応させたり、高速で乾田直播(乾いた田んぼに種もみをまくこと)ができる機械を使ったり、水位や水温、気象データのとれる水田用センサーを38枚の田んぼすべてに設置したり。
ただ、1俵(60kg)当たりの生産費が1万円を切る低コストの稲作を目指す立場からすると、今のスマート農業に物足りなさを感じるという。
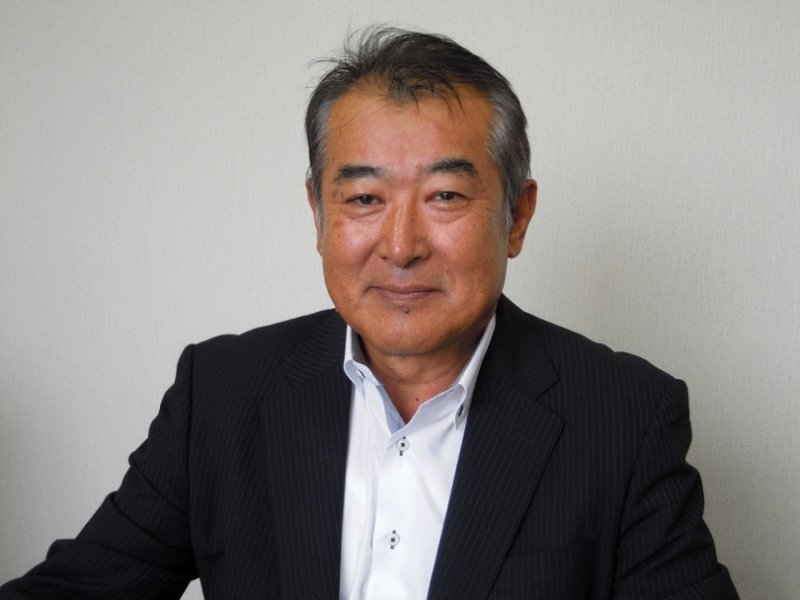 まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さん(写真提供:まいすたぁ)
まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さん(写真提供:まいすたぁ)稲作の面積拡大と効率化には限界がある
「規模拡大で20~30ヘクタールまでは効率化が進んでも、それを超えるとどんどん収量が落ちて、効率化が進まなくなる。離農で面積が増え続ける現場が、このままでは破綻してしまう。大面積で効率よく生産するための実験をしている」まいすたぁ代表取締役の齋藤一志さんはこう話す。齋藤さんは集荷業を営む株式会社庄内こめ工房(山形県鶴岡市)の代表取締役を兼ねており、約90の生産者から約700ヘクタール分のコメを集荷する。面積を拡大しても効率化が進まなくなる「壁」の存在に生産者は頭を悩ませている。
「肥料・農薬といった物財費は、面積が広がってまとめ買いするようになっても、値段はほとんど変わらない。スケールメリットによるコストダウンは、稲作ではほとんどない。面積が広がると収量が落ちるので、逆にコストアップになってしまう」
問題を解決すべく、まいすたぁを2009年に設立した。積極的に新技術を採用し、同社の圃場を実証の場として企業や研究機関に提供する。同社で試したのを見て「これはいい」と思う生産者がいれば、出向いて作業したり、技術や機械を導入してもらったりしている。
 まいすたぁで所持するドローン
まいすたぁで所持するドローン具体的には、株式会社マゼックスという国内メーカーのドローン1基を保有し、肥料や農薬をまく。ドローンの効率の良さはほかの生産者からも認められていて、自社の圃場だけでなく、作業を請け負ってほかの圃場でまくこともある。トラクターはハンドルを自動操舵対応のものに付け替え、誤差がわずかに1.5センチ程度という精度の高い作業が可能になった。圃場の均平に使うレーザーレベラーも自動操舵に対応している。
自前でこうした技術を取り入れるのはもちろん、民間企業や研究機関に実証の場を提供してもいる。今年の田植えでは、農研機構が開発した高速で乾田直播をする技術で播種した。山形大学農学部で開発中の各種センサーを搭載した4輪のロボットが、時おり田んぼの中を走っている。ほかに植生の分布状況や活性度を測るNDVIカメラを使って稲の葉色から生育具合を判断し、施肥に生かす試みもしている。
高速で高精度でないと使えない
 乾田直播のようす
乾田直播のようすコスト削減と省力化で期待を寄せるのが直播だ。鉄粉をコーティングした種子などを直播機で水を張った田んぼにまく湛水直播を試してきたが、あまりコスト削減の効果が感じられなかった。そのため、湛水直播をするのであれば、ドローンやヘリコプターを使った空中からの散布の方が効率的だと感じている。「ドリルシーダー」という播種専用のアタッチメントを使った乾田直播ならば、除草剤対策と水管理をきちんとすれば効果が高いという。
直播をするうえでは、圃場1枚あたりの面積を広げることが効率化にあたっては必須と指摘する。高速で作業するドリルシーダーで乾田直播をするに当たり、1枚30アールの田んぼ7枚を合わせて2.1ヘクタールの田んぼにした。これで効率は格段に上がる。
スマート農業に関して、国内メーカーが開発する稲作向けの製品には不満もあるという。作業スピードが遅く、応用が利きにくくて使いづらいのに値段は高いものが多いと感じるからだ。駆動力が不足していて、ぬかるんだ田んぼでは使えないロボット農機や、費用対効果が不明のセンサーなども中にはある。「海外製品と同じように高速で高精度の作業ができないと、農家が食えるようにはならない」と話す。
スマート農業には農学と工学の双方向開発が必要
 まいすたぁが使用する水田用センサー
まいすたぁが使用する水田用センサー「今のスマート農業は、技術系の人たちがフィーバーしているだけで、現場じゃ使えないというものが多い。これから目指すべきスマート農業とは違うし、しかも段々本来目指すべきものから離れていっている。工学系の人間には『古典的なことをやっている農家のために私の能力を提供しよう』という考えがあるようだけれども、開発したほとんどのものは使い物にならない」
開発には、農学と工学の研究者の連携が欠かせないと考えている。農学研究者がどのデータを使ってどの時期にどんな作業をして収量を上げるか、どんなアラームを発して病害の損失を減らすかというソフトの部分を作り、工学研究者が駆動力と応用力のあるハードを作る。このように双方向から開発を進めなければ、実用化までこぎつける製品がなかなか生まれてこないと指摘する。
営農支援ソフトにしても、使うことで収量が確実に上がる水準まで持っていくには、自然環境や投入資材と作業時期などの情報を総合して判断することが必要だと考えている。農学の中でも環境や土壌、植物生理、生態系といった広範な学問領域の研究者に情報をデータベース化してもらい、それに基づいていつ何をすべきかアドバイスできるようになれば、ベテラン農家が使えるものになると期待する。
「温暖化で日本の気候自体が変わっているために、雑草一つとっても、これまで自分の地域で出ていた雑草と全く違うものが見つかる。そういうものはベテラン農家でもさっぱりわからないから、写真を撮ってどこかに送れば、これは何でどういう対策が必要かという回答がもらえたりしたら、と思う」
海外には農家が直接専門家に質問できるサービスがあり、そうしたものが国内の稲作向けにできればぜひ使いたいという。
世にあふれる多様な技術の中から、いかにして適切なものを選び出し、農業の革新に貢献できる商品やサービスを作り出すのか。いくつかの学問分野にまたがった研究と開発、そして農家と専門家の連携こそ必要だというのが、齋藤さんの達した結論だ。
株式会社まいすたぁ-山形県三川町-最先端農業の実践
株式会社庄内こめ工房
SHARE















































