令和の米騒動の原因は? お米ライター 柏木智帆さんの書籍『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』重版出来!
年間400種以上のお米を食べながら、“お米ライター”としてお米の魅力を発信している柏木智帆さんの書籍『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』が、2025年5月15日に発売。この度、重版が決定しました。
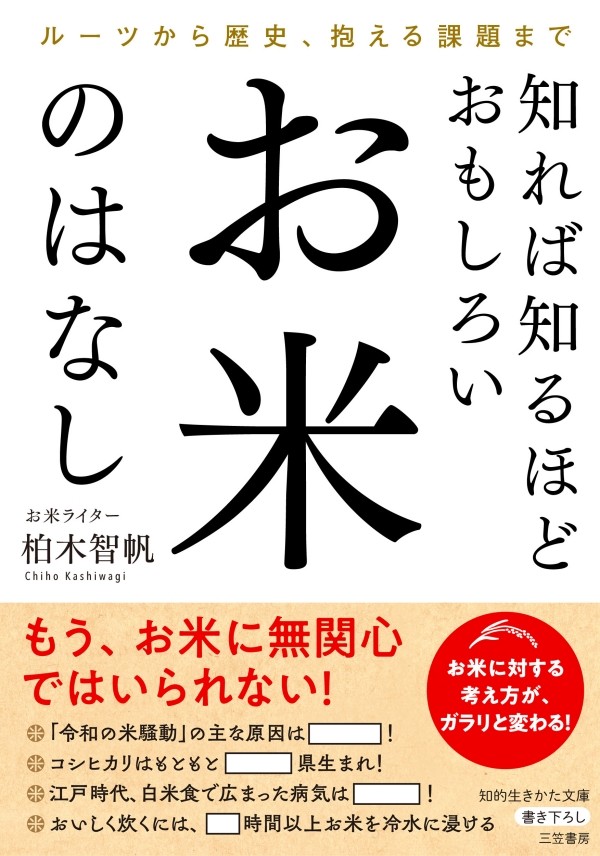
米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライターとして活躍する柏木智帆さん。
神奈川新聞の記者を経て、福島県の米農家と結婚。年間400種以上の米を試食しながら「お米の消費アップ」をライフワークに、執筆やイベント、講演活動など、お米の魅力を伝える活動を行っています。
SMART AGRIでは、お米をもっと楽しむヒントを教えていただく連載「お米沼にようこそ」を執筆いただいています。
そんな柏木さんが、お米の歴史から文化、経済、食べ方までを、さまざまなエピソードとともに解説する1冊が『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』です。
日本にお米が伝来した経緯や、減反政策の真実、「令和の米騒動」の背景など、お米の歴史や政治の影響をわかりやすく紹介。コシヒカリが人気を誇る理由、戦国武将が好んだ食べ方、かつては農家自身も輸入米を食べていた話など、思わず誰かに話したくなるようなトピックもあり、楽しく知識が深まります。
また、おいしいごはんの炊き方やたまご農家直伝の卵かけごはんの食べ方など、日常の役立ち情報まで掲載されており、お米をさまざまな角度から楽しめます。
今回柏木さんに、著書で伝えたいことや執筆の感想などメッセージをいただきました。

──ご著書に込めた思いをお聞かせください。
お米の消費量は減少し続けています。総需要量は1963年をピークに下がり続け、お米が余るようになりました。
この騒動の引き金となった米不足は、日本人がご飯を食べなくなったことと無関係ではありません。一部で減反が批判されていますが、そもそも減反が行われていたのはお米が余っていたから。米価が下落しないようにお米を作る量を減らすよう調整していたのです。
毎日食べるものだからこそ、価格に敏感になる気持ちはわかります。でも、当然ながらお米を作る人がいなければ、ご飯を食べることができません。「安ければ安いほどいい」では、お米を作る農家も田んぼもなくなってしまいます。
気づけばお米はあって当たり前の存在となっていますが、お米のルーツや歴史、現在抱える課題などを知ることで、お米に対する見方や考え方が変わるきっかけになればという思いを込めて、この本を書きました。
ご飯を食べるすべての人に読んでいただきたい1冊です。
──特に注目してほしいトピックはありますか?
明治時代には、毎年大量のお米を恒常的に海外から輸入・移入していた一方で、お米が神戸港の輸出額第一位になるほど輸出が活発だった年もあったそうです。
こうした状況に対して、国内での暴風雨による水害、輸入米の産地での洪水や干ばつがそれぞれどういった事態を引き起こしたかという歴史からは、普遍的な問いを投げかけられたように感じています。
──今回の執筆を通して、ご自身の価値観にも変化はありましたか?
稲作や米食の歴史を知るほどに、改めて戦後のアメリカの小麦戦略による日本人の食生活への影響の大きさと深刻さを実感しました。
この本を読んだ方がどう感じるかはそれぞれだとは思いますが、食卓は過去や未来につながっているということを心に留めながら、何を食べるか選んでいく必要があると感じます。
──昨今のコメ価格高騰によって、私たちが「お米とどう向き合うか」が問われているようにも感じました。柏木さんはこの状況をどのように捉えていますか? また、今後どのような変化や対策が必要だと感じますか?
これまで消費者や識者などからは「農業への補助金は競争力を衰えさせる」「補助金をなくして国際競争力をつけるべきだ」という批判もありました。
しかしながら、近年では30年ほど前の大冷害前後を除けば米価は安すぎる状況が続いてきました。国による減反補助金がなければ、もっと早いスピードで農家は激減して、田んぼも減っていたのではないでしょうか。
米価が安ければ離農は進み後継者はいなくなり、たとえ一部で集約化が進んだとしても、100%自給可能だったはずのお米が自給しきれなくなり、田んぼや多様な稲作が減少してしまう可能性があります。
お米を自給しきれずに輸入に頼る状況は、極めて脆弱です。海外の政治情勢のほか、産地の水害や干ばつなどによって、価格が高騰する可能性や、輸入が突然断ち切られるリスクだってあるのです。私たちの命をつなぐ穀物であるお米は、食料安全保障の要です。
また、田んぼの減少は、土砂崩れ防止や川の氾濫防止といった田んぼが持つ機能の減少にもつながり、多様な稲作の減少は天候などによる栽培リスクの増大、お米の魅力や米食文化の乏しさにもつながると感じます。
稲作を持続していくためには、やはりお米の「適正価格」は重要です。米農家が持続可能に経営を続けられる価格、稲作に希望を抱いて後継者が増える価格はいったいいくらなのか。一方で、お腹いっぱいご飯を食べ続けられる価格はいくらなのか。そして、これまでお米にどのくらいの価値を置いてきたのか、これからはお米の価値についてどう考えていくべきか。
「令和の米騒動」は、私たち消費者にお米の「適正価格」について改めて真剣に考えるきっかけを投げかけているようにも感じます。
この本をご一読いただいた方に、何か一つでも新たなお米の見え方・考え方が生まれたら嬉しく思います。
米不足や価格高騰が社会問題として注目されている昨今。あらためて、「お米の価値」を見つめ直すのにぴったりな1冊となっています。
柏木智帆さんのインタビューはこちら
柏木智帆さんの連載はこちら
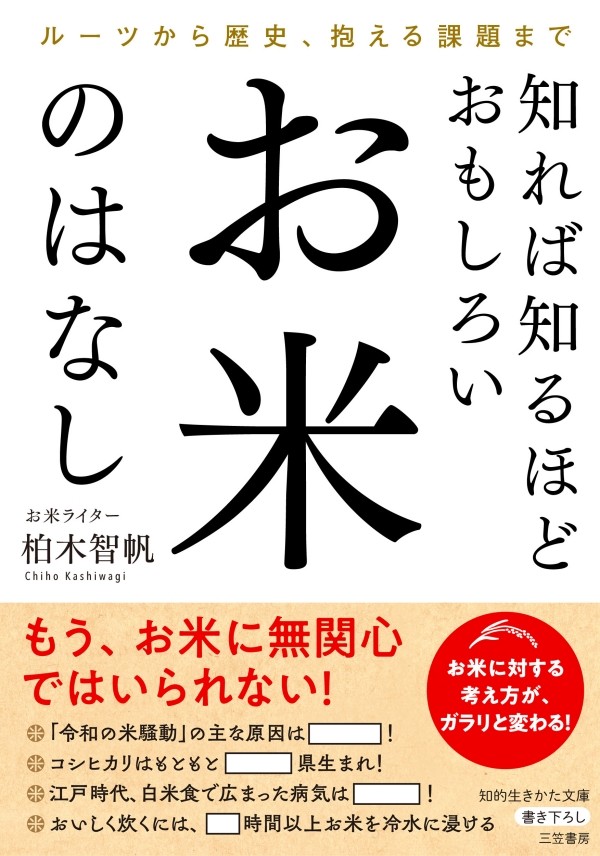
「令和の米騒動」はなぜ起きたのか?
読めば思わず誰かに話したくなる知識と発見が満載!
●コシヒカリが圧倒的な人気を誇る理由とは?
●武士や戦国武将が好んだお米の食べ方は?
●「減反廃止」は本当だったのか? 制度の裏側に迫る
●年末にお米が売れないのはなぜ? 知られざる意外な要因
さらに驚きのエピソードも!
●北海道でコシヒカリが栽培されない理由とは?
●かつて農家も輸入米を食べていた?
●「日本最古のおにぎり」は本当におにぎりだったのか?
お米を偏愛する著者が、お米の歴史・品種・文化の世界を語る!
柏木智帆『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』(三笠書房) 847円(税込)
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837989233/amakinmikasas-22/ref=nosim
三笠書房 書籍ページ
https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100892300
著者紹介
柏木智帆(かしわぎ・ちほ)
1982年、神奈川県生まれ。大学卒業後、神奈川新聞社に入社、編集局報道部に配属。新聞記者として様々な取材活動を行うなかで、稲作を取り巻く現状や日本文化の根っこである「お米」について興味を持ち始める。農業の経験がない立場で記事を書くことに疑問を抱くようになり、農業の現場に立つ人間になりたいと就農を決意、8年間勤めた新聞社を退職。無農薬・無肥料での稲作に取り組むと同時に、キッチンカーでおむすびの販売やケータリング事業も運営。2014年秋より都内に拠点を移し、お米ライターとして活動を開始。2017年に取材で知り合った米農家の男性と結婚し、福島県へ移住。夫と娘と共に田んぼに触れる生活を送りながら、お米の消費アップをライフワークに、様々なメディアでお米の魅力を伝えている。また、米食を通した食育にも目を向けている。
執筆記事は「お米沼にようこそ」(SMART AGRI)など多数。また、NHK「あしたも晴れ!人生レシピ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などの各種メディアにも出演。米・食味鑑定士としてお米の各種コンテストの審査員も務める。2021年から「おむすび権米衛」のアドバイザーに就任。
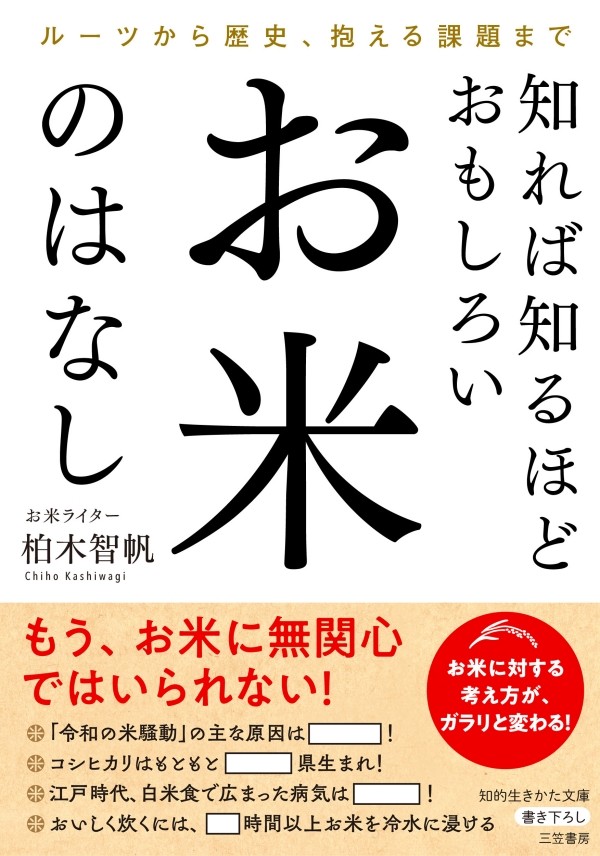
米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライターとして活躍する柏木智帆さん。
神奈川新聞の記者を経て、福島県の米農家と結婚。年間400種以上の米を試食しながら「お米の消費アップ」をライフワークに、執筆やイベント、講演活動など、お米の魅力を伝える活動を行っています。
SMART AGRIでは、お米をもっと楽しむヒントを教えていただく連載「お米沼にようこそ」を執筆いただいています。
そんな柏木さんが、お米の歴史から文化、経済、食べ方までを、さまざまなエピソードとともに解説する1冊が『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』です。
日本にお米が伝来した経緯や、減反政策の真実、「令和の米騒動」の背景など、お米の歴史や政治の影響をわかりやすく紹介。コシヒカリが人気を誇る理由、戦国武将が好んだ食べ方、かつては農家自身も輸入米を食べていた話など、思わず誰かに話したくなるようなトピックもあり、楽しく知識が深まります。
また、おいしいごはんの炊き方やたまご農家直伝の卵かけごはんの食べ方など、日常の役立ち情報まで掲載されており、お米をさまざまな角度から楽しめます。
今回柏木さんに、著書で伝えたいことや執筆の感想などメッセージをいただきました。

──ご著書に込めた思いをお聞かせください。
お米の消費量は減少し続けています。総需要量は1963年をピークに下がり続け、お米が余るようになりました。
この騒動の引き金となった米不足は、日本人がご飯を食べなくなったことと無関係ではありません。一部で減反が批判されていますが、そもそも減反が行われていたのはお米が余っていたから。米価が下落しないようにお米を作る量を減らすよう調整していたのです。
毎日食べるものだからこそ、価格に敏感になる気持ちはわかります。でも、当然ながらお米を作る人がいなければ、ご飯を食べることができません。「安ければ安いほどいい」では、お米を作る農家も田んぼもなくなってしまいます。
気づけばお米はあって当たり前の存在となっていますが、お米のルーツや歴史、現在抱える課題などを知ることで、お米に対する見方や考え方が変わるきっかけになればという思いを込めて、この本を書きました。
ご飯を食べるすべての人に読んでいただきたい1冊です。
──特に注目してほしいトピックはありますか?
明治時代には、毎年大量のお米を恒常的に海外から輸入・移入していた一方で、お米が神戸港の輸出額第一位になるほど輸出が活発だった年もあったそうです。
こうした状況に対して、国内での暴風雨による水害、輸入米の産地での洪水や干ばつがそれぞれどういった事態を引き起こしたかという歴史からは、普遍的な問いを投げかけられたように感じています。
──今回の執筆を通して、ご自身の価値観にも変化はありましたか?
稲作や米食の歴史を知るほどに、改めて戦後のアメリカの小麦戦略による日本人の食生活への影響の大きさと深刻さを実感しました。
この本を読んだ方がどう感じるかはそれぞれだとは思いますが、食卓は過去や未来につながっているということを心に留めながら、何を食べるか選んでいく必要があると感じます。
──昨今のコメ価格高騰によって、私たちが「お米とどう向き合うか」が問われているようにも感じました。柏木さんはこの状況をどのように捉えていますか? また、今後どのような変化や対策が必要だと感じますか?
これまで消費者や識者などからは「農業への補助金は競争力を衰えさせる」「補助金をなくして国際競争力をつけるべきだ」という批判もありました。
しかしながら、近年では30年ほど前の大冷害前後を除けば米価は安すぎる状況が続いてきました。国による減反補助金がなければ、もっと早いスピードで農家は激減して、田んぼも減っていたのではないでしょうか。
米価が安ければ離農は進み後継者はいなくなり、たとえ一部で集約化が進んだとしても、100%自給可能だったはずのお米が自給しきれなくなり、田んぼや多様な稲作が減少してしまう可能性があります。
お米を自給しきれずに輸入に頼る状況は、極めて脆弱です。海外の政治情勢のほか、産地の水害や干ばつなどによって、価格が高騰する可能性や、輸入が突然断ち切られるリスクだってあるのです。私たちの命をつなぐ穀物であるお米は、食料安全保障の要です。
また、田んぼの減少は、土砂崩れ防止や川の氾濫防止といった田んぼが持つ機能の減少にもつながり、多様な稲作の減少は天候などによる栽培リスクの増大、お米の魅力や米食文化の乏しさにもつながると感じます。
稲作を持続していくためには、やはりお米の「適正価格」は重要です。米農家が持続可能に経営を続けられる価格、稲作に希望を抱いて後継者が増える価格はいったいいくらなのか。一方で、お腹いっぱいご飯を食べ続けられる価格はいくらなのか。そして、これまでお米にどのくらいの価値を置いてきたのか、これからはお米の価値についてどう考えていくべきか。
「令和の米騒動」は、私たち消費者にお米の「適正価格」について改めて真剣に考えるきっかけを投げかけているようにも感じます。
この本をご一読いただいた方に、何か一つでも新たなお米の見え方・考え方が生まれたら嬉しく思います。
※※※
米不足や価格高騰が社会問題として注目されている昨今。あらためて、「お米の価値」を見つめ直すのにぴったりな1冊となっています。
柏木智帆さんのインタビューはこちら
柏木智帆さんの連載はこちら
書籍情報
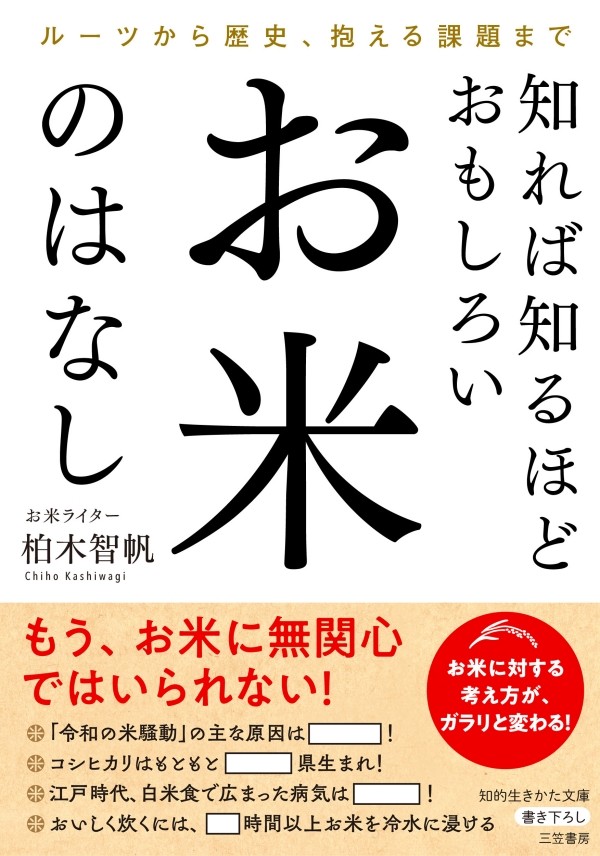
「令和の米騒動」はなぜ起きたのか?
読めば思わず誰かに話したくなる知識と発見が満載!
●コシヒカリが圧倒的な人気を誇る理由とは?
●武士や戦国武将が好んだお米の食べ方は?
●「減反廃止」は本当だったのか? 制度の裏側に迫る
●年末にお米が売れないのはなぜ? 知られざる意外な要因
さらに驚きのエピソードも!
●北海道でコシヒカリが栽培されない理由とは?
●かつて農家も輸入米を食べていた?
●「日本最古のおにぎり」は本当におにぎりだったのか?
お米を偏愛する著者が、お米の歴史・品種・文化の世界を語る!
柏木智帆『知れば知るほどおもしろい お米のはなし』(三笠書房) 847円(税込)
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4837989233/amakinmikasas-22/ref=nosim
三笠書房 書籍ページ
https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100892300
著者紹介
柏木智帆(かしわぎ・ちほ)
1982年、神奈川県生まれ。大学卒業後、神奈川新聞社に入社、編集局報道部に配属。新聞記者として様々な取材活動を行うなかで、稲作を取り巻く現状や日本文化の根っこである「お米」について興味を持ち始める。農業の経験がない立場で記事を書くことに疑問を抱くようになり、農業の現場に立つ人間になりたいと就農を決意、8年間勤めた新聞社を退職。無農薬・無肥料での稲作に取り組むと同時に、キッチンカーでおむすびの販売やケータリング事業も運営。2014年秋より都内に拠点を移し、お米ライターとして活動を開始。2017年に取材で知り合った米農家の男性と結婚し、福島県へ移住。夫と娘と共に田んぼに触れる生活を送りながら、お米の消費アップをライフワークに、様々なメディアでお米の魅力を伝えている。また、米食を通した食育にも目を向けている。
執筆記事は「お米沼にようこそ」(SMART AGRI)など多数。また、NHK「あしたも晴れ!人生レシピ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などの各種メディアにも出演。米・食味鑑定士としてお米の各種コンテストの審査員も務める。2021年から「おむすび権米衛」のアドバイザーに就任。
SHARE













































