“コシヒカリ一強”がもたらす影響とは? 私たちがいろいろな品種を食べる意味を考える【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第9回】
お米ライターの柏木智帆です。
「コシヒカリ」は1979(昭和54)年から半世紀近くにわたってお米の生産量のトップの座を独走し続けています。うるち米は300品種以上あるにもかかわらず、消費者側の「お米といえばコシヒカリ」といった感覚も根強く、現在のコシヒカリの作付面積はうるち米の約3割を占めます。
今回は“コシヒカリ偏重”とも言える作付け割合や消費者の嗜好について考えていきます。

コシヒカリは北海道と沖縄県以外の全国各地で栽培されています。
2023(令和5)年産の主食用うるち玄米の検査数量は441万7000トン。このうちコシヒカリの生産量は127万7800トン超と3割近くを占めました。
中でもコシヒカリを最も多く生産しているのは、お米全体の生産量もトップの新潟県。県内の作付面積の6割をコシヒカリが占め、日本全体のコシヒカリの2割以上にあたる29万5000トン超を生産しました。
この年、全国的な高温に見舞われたことは記憶に新しいでしょう。
特に新潟県は、夏場の高温と渇水の影響を受けたほか、コシヒカリの出穂時期に受けたフェーン現象による高温と乾燥によって、収穫量の減少だけでなく品質も低下し、この年の新潟県産コシヒカリの一等米比率は過去最低の4.3%に。平年値75.3%に比べると、その低さが際立ちます。
全国的にも一等米比率は60.9%と例年よりも低い結果となりましたが、新潟県産コシヒカリのダメージは顕著だったことがわかります。
当時、新潟コシヒカリのみならず、お米に白く濁った「白未熟粒」が多いと報道されました。
等級検査は人間が目視で行うため、一等米がなかなか出ないと徐々に基準が甘くなったり、生産者と顔見知りの業者が等級を上げたりといったことも行われていたため、実際の一等米比率はさらに低かったとみられます。
こうしたお米は精米前に選別機で取り除かれ、さらに精米すると割れやすく、歩留まりの悪さは流通量の減少につながりました。
高温耐性品種に比べるとコシヒカリは暑さへの耐性は不十分で、気候変動によってコシヒカリが合わなくなってきていると感じている生産者は少なくありません。
この年のコシヒカリ以外の一等米比率を見ると、「新之助」95%(平年値95%)、「ゆきん子舞」62%(平年値83%)、「こしいぶき」13%(平年値74%)で、高温耐性が強い新之助は一等米比率が変動なく高いまま。
しかしながら、新之助の2023(令和5)年産の作付け割合は4%程度で、作付け割合が60%を占めるコシヒカリには到底及びません。
コシヒカリ一強の現状がお米の流通量の減少につながった面もあると言えそうです。
新潟県ではじわじわとコシヒカリの作付けが減っている一方で新之助の作付けが増えていますが、生産者からは「新之助はいもち病にかかりやすい」という声もあります。
新潟県のコシヒカリは2005(平成17)年からいもち病に強い「コシヒカリBL」が主流です。BLとは、「ブラスト・レジスタンス・ラインズ」の略。つまり、コシヒカリBLは、「いもち病抵抗性が強いコシヒカリ」です。
いもち病抵抗性が弱い新之助は防除のコストや手間がかかる一方で、コシヒカリよりも買い取り価格が安く、「病気に弱い新之助」よりも、「暑さに弱いコシヒカリ」が選ばれやすい側面もあるようです。
また、「新潟米=コシヒカリ」のイメージが強すぎて、新之助に限らず「コシヒカリ以外の品種が売りにくい」といった悩みも聞きます。
こうした状況の中、新潟県は高温耐性が強いコシヒカリBLの開発を進めていますが、ある品種が作付け割合の多くを占める状況は、気候変動や自然災害などによるリスクが高いと言えるでしょう。

コシヒカリの登場をきっかけに、日本のお米の品種は多様性を失ってきた面もあります。
日本では現在うるち米だけでも約300品種が作られていますが、作付け割合の上位20位はすべてコシヒカリの親戚品種。さらに、上位20位だけで全体の約8割を占めるなど、品種の多様性は小さくなっています。
この状況について、「コシヒカリの血を受け継いでいるからおいしいという風潮があり、育種がマーケットに勝てない」と指摘するのは、稲に詳しい農学者・佐藤洋一郎さん。そして、この状況を「私たちは赤い絵の具と青い絵の具しか持っていない」と表現します。
「この2色を混ぜるといろいろな紫色になるけど、結局は紫色であることは変わりありません。それが近年の品種改良で、いかに嗜好が均一化されたかということです」
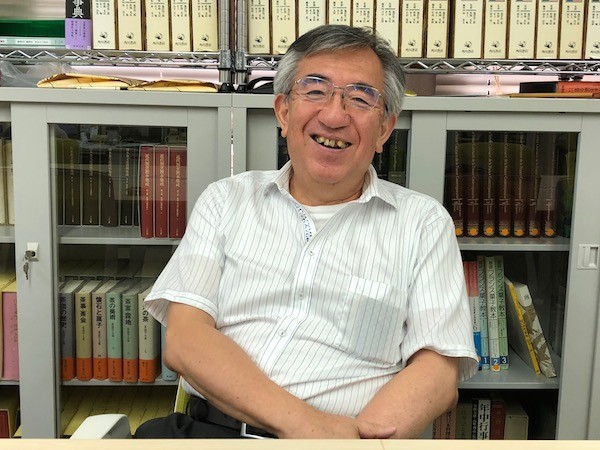
明治時代には、気候風土や用途によって農家たちが生み出したお米が3500品種もあったと言われています。「品種」の概念が緩かった面もあるようですが、かつては1軒の農家が多品種を栽培していました。しかし、現在は地域によってはコシヒカリ一辺倒と言える状況です。
鶏が先か卵が先かですが、私たちがコシヒカリばかりを食べると、コシヒカリばかりの作付けになりますが、多様な品種を食べるようになれば、今よりも多様な品種の栽培が広がりやすくなるでしょう。
最近ではさまざまな高温耐性品種も生まれているほか、コシヒカリ誕生以前の品種が見直されている動きもあります。気候変動や自然災害へのリスクヘッジという意味でも、もっと多様な品種を楽しんでみてはいかがでしょうか。
<参照元>
農林水産省「令和5年産米の農産物検査結果(確定値)」
新潟県「令和5年産新潟米の1等級比率低下要因と対応について ~ 令和5年産米に関する研究会報告書 ~」
長時間の浸水や水加減など、何かと手間のかかる玄米の炊飯。玄米ごはんを無理なく続けたい方や玄米初心者の方は、炊きやすく加工した「無洗米玄米」がおすすめです。
SMART AGRI FOODから発売しているスマート米の「無洗米玄米」は、玄米の栄養価はほとんどそのままに、浸水時間もなく炊飯器の白米モードで炊ける玄米です。
いつでもふっくらおいしい玄米が炊けるので忙しい方にもおすすめです。
SMART AGRI FOODのパックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」は、電子レンジで約2分温めるだけでもちもち食感のおいしい玄米が食べられるレトルトごはんです。
圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米®」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。
忙しい方や、お弁当に持っていく方、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。
玄米パックごはんが毎月届く!おトクな定期便
パックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」が毎月届く定期便もございます。
初回は50%OFF、2カ月目以降も定期便だけのお得な特別価格でお届け!
定期便なら買い忘れなくお得に玄米食を続けられます。
「スマート米」とは
全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てたお米です。玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米がそろいます。
各地の人気銘柄から、あまり見かけない貴重な銘柄をラインナップ。
お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。
「コシヒカリ」は1979(昭和54)年から半世紀近くにわたってお米の生産量のトップの座を独走し続けています。うるち米は300品種以上あるにもかかわらず、消費者側の「お米といえばコシヒカリ」といった感覚も根強く、現在のコシヒカリの作付面積はうるち米の約3割を占めます。
今回は“コシヒカリ偏重”とも言える作付け割合や消費者の嗜好について考えていきます。

コシヒカリといえば新潟県
コシヒカリは北海道と沖縄県以外の全国各地で栽培されています。
2023(令和5)年産の主食用うるち玄米の検査数量は441万7000トン。このうちコシヒカリの生産量は127万7800トン超と3割近くを占めました。
中でもコシヒカリを最も多く生産しているのは、お米全体の生産量もトップの新潟県。県内の作付面積の6割をコシヒカリが占め、日本全体のコシヒカリの2割以上にあたる29万5000トン超を生産しました。
この年、全国的な高温に見舞われたことは記憶に新しいでしょう。
特に新潟県は、夏場の高温と渇水の影響を受けたほか、コシヒカリの出穂時期に受けたフェーン現象による高温と乾燥によって、収穫量の減少だけでなく品質も低下し、この年の新潟県産コシヒカリの一等米比率は過去最低の4.3%に。平年値75.3%に比べると、その低さが際立ちます。
全国的にも一等米比率は60.9%と例年よりも低い結果となりましたが、新潟県産コシヒカリのダメージは顕著だったことがわかります。
当時、新潟コシヒカリのみならず、お米に白く濁った「白未熟粒」が多いと報道されました。
等級検査は人間が目視で行うため、一等米がなかなか出ないと徐々に基準が甘くなったり、生産者と顔見知りの業者が等級を上げたりといったことも行われていたため、実際の一等米比率はさらに低かったとみられます。
こうしたお米は精米前に選別機で取り除かれ、さらに精米すると割れやすく、歩留まりの悪さは流通量の減少につながりました。
「コシヒカリ以外の品種が売りにくい」
高温耐性品種に比べるとコシヒカリは暑さへの耐性は不十分で、気候変動によってコシヒカリが合わなくなってきていると感じている生産者は少なくありません。
この年のコシヒカリ以外の一等米比率を見ると、「新之助」95%(平年値95%)、「ゆきん子舞」62%(平年値83%)、「こしいぶき」13%(平年値74%)で、高温耐性が強い新之助は一等米比率が変動なく高いまま。
しかしながら、新之助の2023(令和5)年産の作付け割合は4%程度で、作付け割合が60%を占めるコシヒカリには到底及びません。
コシヒカリ一強の現状がお米の流通量の減少につながった面もあると言えそうです。
新潟県ではじわじわとコシヒカリの作付けが減っている一方で新之助の作付けが増えていますが、生産者からは「新之助はいもち病にかかりやすい」という声もあります。
新潟県のコシヒカリは2005(平成17)年からいもち病に強い「コシヒカリBL」が主流です。BLとは、「ブラスト・レジスタンス・ラインズ」の略。つまり、コシヒカリBLは、「いもち病抵抗性が強いコシヒカリ」です。
いもち病抵抗性が弱い新之助は防除のコストや手間がかかる一方で、コシヒカリよりも買い取り価格が安く、「病気に弱い新之助」よりも、「暑さに弱いコシヒカリ」が選ばれやすい側面もあるようです。
また、「新潟米=コシヒカリ」のイメージが強すぎて、新之助に限らず「コシヒカリ以外の品種が売りにくい」といった悩みも聞きます。
こうした状況の中、新潟県は高温耐性が強いコシヒカリBLの開発を進めていますが、ある品種が作付け割合の多くを占める状況は、気候変動や自然災害などによるリスクが高いと言えるでしょう。

「育種がマーケットに勝てない」
コシヒカリの登場をきっかけに、日本のお米の品種は多様性を失ってきた面もあります。
日本では現在うるち米だけでも約300品種が作られていますが、作付け割合の上位20位はすべてコシヒカリの親戚品種。さらに、上位20位だけで全体の約8割を占めるなど、品種の多様性は小さくなっています。
この状況について、「コシヒカリの血を受け継いでいるからおいしいという風潮があり、育種がマーケットに勝てない」と指摘するのは、稲に詳しい農学者・佐藤洋一郎さん。そして、この状況を「私たちは赤い絵の具と青い絵の具しか持っていない」と表現します。
「この2色を混ぜるといろいろな紫色になるけど、結局は紫色であることは変わりありません。それが近年の品種改良で、いかに嗜好が均一化されたかということです」
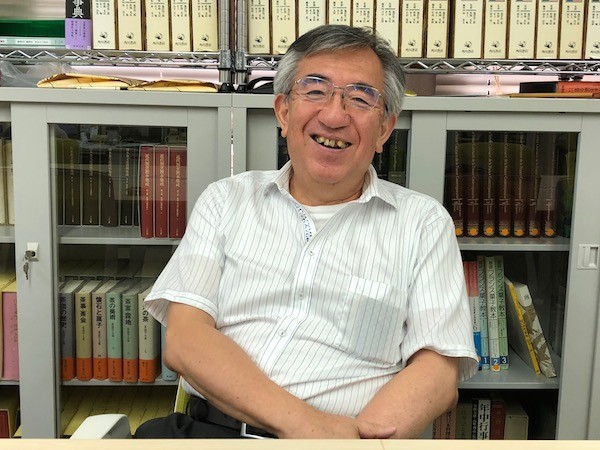
佐藤洋一郎さんふじのくに地球環境史ミュージアム・館長 / Awaji Chef's Sucuola 校長
明治時代には、気候風土や用途によって農家たちが生み出したお米が3500品種もあったと言われています。「品種」の概念が緩かった面もあるようですが、かつては1軒の農家が多品種を栽培していました。しかし、現在は地域によってはコシヒカリ一辺倒と言える状況です。
鶏が先か卵が先かですが、私たちがコシヒカリばかりを食べると、コシヒカリばかりの作付けになりますが、多様な品種を食べるようになれば、今よりも多様な品種の栽培が広がりやすくなるでしょう。
最近ではさまざまな高温耐性品種も生まれているほか、コシヒカリ誕生以前の品種が見直されている動きもあります。気候変動や自然災害へのリスクヘッジという意味でも、もっと多様な品種を楽しんでみてはいかがでしょうか。
<参照元>
農林水産省「令和5年産米の農産物検査結果(確定値)」
新潟県「令和5年産新潟米の1等級比率低下要因と対応について ~ 令和5年産米に関する研究会報告書 ~」
柏木智帆
米・食味鑑定士/ごはんソムリエ/お米ライター
神奈川新聞の記者を経て、福島県の米農家と結婚。年間400種以上の米を試食しながら「お米の消費アップ」をライフワークに、執筆やイベント、講演活動など、お米の魅力を伝える活動を行っている。また、4歳の娘の食事やお弁当づくりを通して、食育にも目を向けている。
米・食味鑑定士/ごはんソムリエ/お米ライター
神奈川新聞の記者を経て、福島県の米農家と結婚。年間400種以上の米を試食しながら「お米の消費アップ」をライフワークに、執筆やイベント、講演活動など、お米の魅力を伝える活動を行っている。また、4歳の娘の食事やお弁当づくりを通して、食育にも目を向けている。
■家族みんなにあんしん・安全なお米を選ぼう!
■白米のように炊ける「無洗米玄米」もおすすめ!
長時間の浸水や水加減など、何かと手間のかかる玄米の炊飯。玄米ごはんを無理なく続けたい方や玄米初心者の方は、炊きやすく加工した「無洗米玄米」がおすすめです。
SMART AGRI FOODから発売しているスマート米の「無洗米玄米」は、玄米の栄養価はほとんどそのままに、浸水時間もなく炊飯器の白米モードで炊ける玄米です。
いつでもふっくらおいしい玄米が炊けるので忙しい方にもおすすめです。
■パックごはん「寝かせ玄米ごはん」
SMART AGRI FOODのパックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」は、電子レンジで約2分温めるだけでもちもち食感のおいしい玄米が食べられるレトルトごはんです。
圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米®」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。
忙しい方や、お弁当に持っていく方、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。
玄米パックごはんが毎月届く!おトクな定期便
パックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」が毎月届く定期便もございます。
初回は50%OFF、2カ月目以降も定期便だけのお得な特別価格でお届け!
定期便なら買い忘れなくお得に玄米食を続けられます。
「スマート米」とは
全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てたお米です。玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米がそろいます。
各地の人気銘柄から、あまり見かけない貴重な銘柄をラインナップ。
お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。
【連載】年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」
- お米は価格だけではない! おいしさや味わいを言葉化してみる【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第10回】
- “コシヒカリ一強”がもたらす影響とは? 私たちがいろいろな品種を食べる意味を考える【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第9回】
- いま注目の新品種のお米とは?お米好きなら一度は食べたい品種を紹介!!【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第8回】
- おむすびは太らない?心置きなく食べるためのお米基礎知識【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第7回】
- お酒を飲むとお米を食べない人に伝えたい「おむすび×日本酒」の魅力【ライター柏木の「お米沼にようこそ」第6回】
- たったこれだけ!おいしくごはんを炊くコツ4つ【年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」 第5回】
- 夏休みごはんの悩みはおにぎりで解決!子どもの米食のススメ【年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」 第4回】
- ごはんを食べるのがより楽しくなる炊飯道具たち【年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」 第3回】
- お米の持ち味を楽しむ炊飯のポイント【年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」 第2回】
- ごはんを味わう7つのポイント!【年間400種のお米を楽しむライター柏木の「お米沼にようこそ」 第1回】
SHARE





 【パックご飯】 国産スマート米寝かせ玄米ごはん160グラム×12パック入り
【パックご飯】 国産スマート米寝かせ玄米ごはん160グラム×12パック入り 国産スマート米 寝かせ玄米パックごはん 定期便
国産スマート米 寝かせ玄米パックごはん 定期便








































