「塩」にそんな楽しみ方があるなんて! ソルトコーディネーター青山志穂さんに聞きました【食の達人インタビュー】
SMART AGRIでこれまで塩に関する記事を執筆いただいてきた青山志穂さん。日本ソルトコーディネーター協会を立ち上げ、講座やメディア出演等を通じて、塩の魅力を発信しています。
そもそもソルトコーディネーターってどんな人……? 塩をもっと楽しむ方法を教えて欲しい……!
ということで、私たちがまだ知らない食の魅力を聞く「食の達人インタビュー」シリーズ。今回は、ソルトコーディネーター・青山志穂さんに、ご自身のことや塩の魅力・楽しみ方をうかがいました!

──青山さんは大学卒業後、大手食品メーカーに就職。その後、沖縄に移住して塩の専門店に就職されていますが、もともと塩が好きだったんですか?
「塩がたくさんあるから沖縄に移住したのですか? とよく聞かれますが、残念ながらそうではなくて。働きすぎて体を壊したのもあり、のんびりしようと沖縄に移住したんです。そのときに出会ったのがお塩の専門店でした。そこから塩のおもしろさに気づいてしまって、塩の沼にずぶずぶ……と(笑)」

──最初から塩が好きだったわけではないんですね! そこからソルトコーディネーター協会を立ち上げるまでになったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
「ひとつが、山形のイタリアン、アル・ケッチァーノの奥田政行シェフとの出会い。君の知識はこういう理論にのっとってやると合う食材が導き出せるよと教えてくださって、自分が持ってる塩の知識の使い道がわかるようになったんです。
それから、全国の製塩所にも行くようになったんですが、塩って誰がどこでどういう思いで作ってるか、まだほとんど知られてない状態ですよね。生産者さんたちの思いを知ってもらえたらファンがもっと増えるんじゃないかと思ったんです」

「塩の専門店でもスタッフに知識を持たせて店頭でお客様にお伝えしていましたが、聞いたことって覚えきれないと思うんです。塩は売れてるしお店も順調だったんですけど、売ってるだけじゃダメなんだなって思い始めて……。
塩の業界は生産者さんも小規模事業者の集まりなので業界的に情報発信がとにかく弱い。店頭で伝えるだけだともしかしたら業界の根本的な問題や課題の解決にならないかもと思い、私が知識の啓蒙の方をやります! と独立しました」
──そもそも「ソルトコーディネーター」に馴染みがない方も多いと思いますが、どんなことをしているのでしょうか?
「ソルトコーディネーターは、生産者さんと消費者の間に立つ翻訳者のような役割だと思っています。取材して情報を引き出して、消費者ニーズに合わせた塩を提案をしたり。間に立ってコーディネートする人だから『ソルトコーディネーター』と名前を付けて、民間資格として一般社団法人で提供しています。
私1人ができることは限られているので、だったら塩仲間を育成してしまおうと作りました。そう、塩沼に引き込むための協会でもあるんです(笑) 」


──製塩所巡りなどで全国を飛び回っていますが、お家にはさぞかしたくさんの塩があるのではないでしょうか?
「2400種類ぐらいあります。出会う塩を片っ端から買っていくので、気づいたらこんな数に……。今も増殖中なのでこの後どこまで行くのか自分でもわかってないですね(笑)」

 講演会や取材で全国を回るため、その時のテーマなどに合わせて塩をセレクトして持ち歩くそう。これだけでもかなりの数!
講演会や取材で全国を回るため、その時のテーマなどに合わせて塩をセレクトして持ち歩くそう。これだけでもかなりの数!
──そもそもそんなに塩の種類があることに結構びっくりです!
「国内の製塩所は600カ所ぐらいありますが、同じ窯を使っても、結晶の育て方や収穫のタイミングで違う塩になるので1つの製塩所で多いところだと5種類ぐらい作ったりしています。そこに海外産の塩やシーズニングソルトも入れたら星の数ほどになりますよ」
──味や食感もそんなに違うものでしょうか?
「見た目がまずかなり違うのと、味は正直、繊細な違いではありますが、すごくしょっぱい塩とすごくまろやかな塩は誰が舐めてもわかるぐらい違います」
──そんな世界中の塩を楽しむ青山さんが思う、塩の魅力はどんなところにありますか?
「やはり食べ物との組み合わせですよね。塩は“隠れている味を前面に引き出す”のが一番得意! お醤油を混ぜておにぎりを握ったらおいしいですが、お醤油の味になりますよね。お塩はお塩の味だけど、主役ではなく引き立て役として、食材のいろんなところにスポットライトを当てて、いいところを引き出してくれます」
──調味料の中でも、素材の味を一番感じられるのがお塩なんですね。
「塩は好みの量をかけるだけなので、難しい技術もいらないですし、日常で誰でも簡単に楽しめるのも魅力です。何も味をつけないおにぎりを用意して、お塩を3種類ぐらいかけて食べ比べてみると、これだけでお米の味わいが変わるのでぜひやってみてほしいです」

──一般家庭で塩を楽しもうと思ったとき、まず買うとしたらどんな塩がおすすめですか?
「すごくしょっぱいお塩と、すごくまろやかなお塩、真ん中ぐらいの最低3種類ぐらいそろえておくと食べ比べが楽しくなります」
──スーパーなどで気軽にそろえられるものですか?
「スーパーのお塩の棚って結構充実していて、タイプの違う塩がいろいろ置いてありますよ。
選ぶときは商品は開けられないので、パッケージ裏の栄養成分の『食塩相当量』を見てみてください。その数値が高いのはしょっぱくて低いのはまろやかな塩になります。まずは家にあるお塩をチェックしてみて、持っていないしょっぱさのお塩を選んでみてください。
塩は賞味期限もないので、コスパもいいですよ!」
塩選びはこちらの記事も参考に
新米シーズン! 塩むすびにおすすめの「お塩」8選<お米タイプ別>


──まだあまり知られていないけどぜひやってみてほしい塩の使い方はありますか?
「おにぎりを手塩にして握るのが苦手な人、結構いらっしゃると思いますが、最初に20%ぐらいの塩水を作って手水の代わりにシュッシュってやってから握ると、ムラなく握れますよ。お米の重さの0.6%ぐらいの濃度で塩をパッとかけて混ぜてから握るのもおすすめです」
──最初から混ぜてしまえばたしかに失敗しないですね。おすすめの食材との組み合わせもありますか?
「ソースや醤油で食べるのが当たり前だと思われてるものも、塩で食べると意外な発見があります。一番簡単でおすすめしたいのは、納豆! 納豆好きさんはぜひタレはかけずに塩と一緒に食べてみてください!
同じようにお豆腐も実は塩で食べると、大豆の味やお豆腐の舌触り、香りがすごく出てきますよ。バニラアイスにも、塩とオリーブオイルをちょっとかけると大人な味になります!」
──塩×納豆は納豆本来の味を引き出してくれそうですね、ぜひやってみたいです!
また、これはあるあるだと思うのですが、塩が固まってしまったときの対処法もありますか?
「湿気で固くなってしまった塩はお風呂にドバっと入れればバスソルトになりますよ。発汗作用があるので汗が出ておすすめです。水を入れて溶かして、ペースト状にして味付けに使うのもいいですね。腐ってはいないですし、生産者さんが一生懸命作ってくれているものなので、捨てないで最後まで活用してもらえたら嬉しいです」


「もう1つ食べ方でおすすめしたいのが、最初は無塩もしくはごく少量の塩を使い、料理を食べるときに追加でかける方法。この方法ならいろんな種類の塩を楽しめて食卓も盛り上がりますし、各々が好きな量、適切な量の塩が取れるので健康上も一番いいですよね」
──なるほど、あとからかける方法は盲点でした! 料理の時に火にかける前がいいなど、順番はあまり気にしなくてもいいんでしょうか?
「調理工程でのタイミングは大事ですが、味付けという面で言うとあまり違いはありません。それに、溶かしてしまうと塩角が取れて味がまろやかになってしまうので、いずれの塩も量を減らしたり、薄味か無塩で仕上げ、食べる時にかけた方が舌に直接塩が当たるので少量でも塩を感じられますよ」
──塩分が気になる方にとっても賢い塩の楽しみ方ですね。
「塩は人ぞれぞれ生活スタイルによっても必要な量が違います。あとがけが1番楽しくて賢いやり方だと思います。
いま、減塩という言葉も“適塩”に変わってきていますよね。自治体も減塩メニュー推奨ではなく、適塩メニューになっています。適塩という考え方で、おいしく健康的に塩を楽しんでほしいですね」


パンよりお米派
──SMART AGRIではお米と塩に関する記事を書いていただきましたが、青山さん自身はお米は好きですか?
「実は塩が好きになる前からお米は大好きで、パンよりお米派なんです! おいしく炊きたいので、うちでは長谷園さんの土鍋『かまどさん』を使っていますし、農家さんからいただいたり買ったりで常に3種類ぐらいお米が家にあるので、その日の気分に合わせて選んでますね。
食べるときも、基本的には白米で食べるのが好きで、濃いおかずのときでも必ず綺麗な白い部分を残しておいて最後に食べるんです(笑)」
──白米だけ残しておく……お話を聞いていると、結構なお米好きですね(笑)
「そうなんです! おかずはおかず、お米はお米の味で楽しみたいんです。いまって、お米自体も気分によって選べるくらい選択肢がたくさんあるのはすごくありがたいですよね」

──玄米や雑穀なども召し上がりますか?
「実は玄米はあんまり食べなくて……食感が気になるのでおかゆで楽しんでいます。玄米の生米の状態から出汁と一緒に何時間もコトコト煮ると、食感も気にならないのでおすすめです。食べ終わったチキンの骨を冷凍して取っておいて、ねぎの青い部分と一緒に超弱火で3時間ぐらいほったらかしで煮て塩で味を調えるだけで、おいしい中華粥が出来上がりますよ」
──簡単でおいしそうです! 玄米の食感が気になる方はぜひお試しを。
「お米が日本で食文化として根付いているように、世界の塩作りと比較しても日本の塩作りはすごく特殊で、 海水しか資源がないので製法が進化してるんですよ。
その独特さみたいなものを海外の人が見にきて、そんなめんどくさいことをしないと塩は出来ないのか、日本人クレイジーだぜ! とおもしろい発見として捉えてもらえて、観光資源になったりもします。
せっかくの独自の文化なので、潰さずに継続させていきたいですね。塩仲間はいつでも大募集中です!」


スーパーなどで手軽に購入でき、毎日の食卓に欠かせない「塩」。いつも身近にあるものだからこそ、決まった使い方しかしてきませんでした。
これからは青山さんに紹介いただいた方法で、塩の魅力を余すことなく生かしていきたいですね。まずはスーパーで塩の棚をじっくりチェックすることから始めてみましょう!
取材:編集部
青山志穂さん撮影:齋藤 葵
そもそもソルトコーディネーターってどんな人……? 塩をもっと楽しむ方法を教えて欲しい……!
ということで、私たちがまだ知らない食の魅力を聞く「食の達人インタビュー」シリーズ。今回は、ソルトコーディネーター・青山志穂さんに、ご自身のことや塩の魅力・楽しみ方をうかがいました!

なぜ沖縄の塩の専門店に?
──青山さんは大学卒業後、大手食品メーカーに就職。その後、沖縄に移住して塩の専門店に就職されていますが、もともと塩が好きだったんですか?
「塩がたくさんあるから沖縄に移住したのですか? とよく聞かれますが、残念ながらそうではなくて。働きすぎて体を壊したのもあり、のんびりしようと沖縄に移住したんです。そのときに出会ったのがお塩の専門店でした。そこから塩のおもしろさに気づいてしまって、塩の沼にずぶずぶ……と(笑)」

──最初から塩が好きだったわけではないんですね! そこからソルトコーディネーター協会を立ち上げるまでになったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
「ひとつが、山形のイタリアン、アル・ケッチァーノの奥田政行シェフとの出会い。君の知識はこういう理論にのっとってやると合う食材が導き出せるよと教えてくださって、自分が持ってる塩の知識の使い道がわかるようになったんです。
それから、全国の製塩所にも行くようになったんですが、塩って誰がどこでどういう思いで作ってるか、まだほとんど知られてない状態ですよね。生産者さんたちの思いを知ってもらえたらファンがもっと増えるんじゃないかと思ったんです」

「塩の専門店でもスタッフに知識を持たせて店頭でお客様にお伝えしていましたが、聞いたことって覚えきれないと思うんです。塩は売れてるしお店も順調だったんですけど、売ってるだけじゃダメなんだなって思い始めて……。
塩の業界は生産者さんも小規模事業者の集まりなので業界的に情報発信がとにかく弱い。店頭で伝えるだけだともしかしたら業界の根本的な問題や課題の解決にならないかもと思い、私が知識の啓蒙の方をやります! と独立しました」
──そもそも「ソルトコーディネーター」に馴染みがない方も多いと思いますが、どんなことをしているのでしょうか?
「ソルトコーディネーターは、生産者さんと消費者の間に立つ翻訳者のような役割だと思っています。取材して情報を引き出して、消費者ニーズに合わせた塩を提案をしたり。間に立ってコーディネートする人だから『ソルトコーディネーター』と名前を付けて、民間資格として一般社団法人で提供しています。
私1人ができることは限られているので、だったら塩仲間を育成してしまおうと作りました。そう、塩沼に引き込むための協会でもあるんです(笑) 」


コレクションは2400種類以上! 青山さんが思う塩の魅力とは?
──製塩所巡りなどで全国を飛び回っていますが、お家にはさぞかしたくさんの塩があるのではないでしょうか?
「2400種類ぐらいあります。出会う塩を片っ端から買っていくので、気づいたらこんな数に……。今も増殖中なのでこの後どこまで行くのか自分でもわかってないですね(笑)」

 講演会や取材で全国を回るため、その時のテーマなどに合わせて塩をセレクトして持ち歩くそう。これだけでもかなりの数!
講演会や取材で全国を回るため、その時のテーマなどに合わせて塩をセレクトして持ち歩くそう。これだけでもかなりの数!──そもそもそんなに塩の種類があることに結構びっくりです!
「国内の製塩所は600カ所ぐらいありますが、同じ窯を使っても、結晶の育て方や収穫のタイミングで違う塩になるので1つの製塩所で多いところだと5種類ぐらい作ったりしています。そこに海外産の塩やシーズニングソルトも入れたら星の数ほどになりますよ」
──味や食感もそんなに違うものでしょうか?
「見た目がまずかなり違うのと、味は正直、繊細な違いではありますが、すごくしょっぱい塩とすごくまろやかな塩は誰が舐めてもわかるぐらい違います」
──そんな世界中の塩を楽しむ青山さんが思う、塩の魅力はどんなところにありますか?
「やはり食べ物との組み合わせですよね。塩は“隠れている味を前面に引き出す”のが一番得意! お醤油を混ぜておにぎりを握ったらおいしいですが、お醤油の味になりますよね。お塩はお塩の味だけど、主役ではなく引き立て役として、食材のいろんなところにスポットライトを当てて、いいところを引き出してくれます」
──調味料の中でも、素材の味を一番感じられるのがお塩なんですね。
「塩は好みの量をかけるだけなので、難しい技術もいらないですし、日常で誰でも簡単に楽しめるのも魅力です。何も味をつけないおにぎりを用意して、お塩を3種類ぐらいかけて食べ比べてみると、これだけでお米の味わいが変わるのでぜひやってみてほしいです」

一般家庭でまず買っておきたい塩は?
──一般家庭で塩を楽しもうと思ったとき、まず買うとしたらどんな塩がおすすめですか?
「すごくしょっぱいお塩と、すごくまろやかなお塩、真ん中ぐらいの最低3種類ぐらいそろえておくと食べ比べが楽しくなります」
──スーパーなどで気軽にそろえられるものですか?
「スーパーのお塩の棚って結構充実していて、タイプの違う塩がいろいろ置いてありますよ。
選ぶときは商品は開けられないので、パッケージ裏の栄養成分の『食塩相当量』を見てみてください。その数値が高いのはしょっぱくて低いのはまろやかな塩になります。まずは家にあるお塩をチェックしてみて、持っていないしょっぱさのお塩を選んでみてください。
塩は賞味期限もないので、コスパもいいですよ!」
塩選びはこちらの記事も参考に
新米シーズン! 塩むすびにおすすめの「お塩」8選<お米タイプ別>


納豆に塩!? おすすめの塩の楽しみ方
──まだあまり知られていないけどぜひやってみてほしい塩の使い方はありますか?
「おにぎりを手塩にして握るのが苦手な人、結構いらっしゃると思いますが、最初に20%ぐらいの塩水を作って手水の代わりにシュッシュってやってから握ると、ムラなく握れますよ。お米の重さの0.6%ぐらいの濃度で塩をパッとかけて混ぜてから握るのもおすすめです」
──最初から混ぜてしまえばたしかに失敗しないですね。おすすめの食材との組み合わせもありますか?
「ソースや醤油で食べるのが当たり前だと思われてるものも、塩で食べると意外な発見があります。一番簡単でおすすめしたいのは、納豆! 納豆好きさんはぜひタレはかけずに塩と一緒に食べてみてください!
同じようにお豆腐も実は塩で食べると、大豆の味やお豆腐の舌触り、香りがすごく出てきますよ。バニラアイスにも、塩とオリーブオイルをちょっとかけると大人な味になります!」
──塩×納豆は納豆本来の味を引き出してくれそうですね、ぜひやってみたいです!
また、これはあるあるだと思うのですが、塩が固まってしまったときの対処法もありますか?
「湿気で固くなってしまった塩はお風呂にドバっと入れればバスソルトになりますよ。発汗作用があるので汗が出ておすすめです。水を入れて溶かして、ペースト状にして味付けに使うのもいいですね。腐ってはいないですし、生産者さんが一生懸命作ってくれているものなので、捨てないで最後まで活用してもらえたら嬉しいです」


塩分が気になる方必見! 賢い塩の食べ方
「もう1つ食べ方でおすすめしたいのが、最初は無塩もしくはごく少量の塩を使い、料理を食べるときに追加でかける方法。この方法ならいろんな種類の塩を楽しめて食卓も盛り上がりますし、各々が好きな量、適切な量の塩が取れるので健康上も一番いいですよね」
──なるほど、あとからかける方法は盲点でした! 料理の時に火にかける前がいいなど、順番はあまり気にしなくてもいいんでしょうか?
「調理工程でのタイミングは大事ですが、味付けという面で言うとあまり違いはありません。それに、溶かしてしまうと塩角が取れて味がまろやかになってしまうので、いずれの塩も量を減らしたり、薄味か無塩で仕上げ、食べる時にかけた方が舌に直接塩が当たるので少量でも塩を感じられますよ」
──塩分が気になる方にとっても賢い塩の楽しみ方ですね。
「塩は人ぞれぞれ生活スタイルによっても必要な量が違います。あとがけが1番楽しくて賢いやり方だと思います。
いま、減塩という言葉も“適塩”に変わってきていますよね。自治体も減塩メニュー推奨ではなく、適塩メニューになっています。適塩という考え方で、おいしく健康的に塩を楽しんでほしいですね」


パンよりお米派
──SMART AGRIではお米と塩に関する記事を書いていただきましたが、青山さん自身はお米は好きですか?
「実は塩が好きになる前からお米は大好きで、パンよりお米派なんです! おいしく炊きたいので、うちでは長谷園さんの土鍋『かまどさん』を使っていますし、農家さんからいただいたり買ったりで常に3種類ぐらいお米が家にあるので、その日の気分に合わせて選んでますね。
食べるときも、基本的には白米で食べるのが好きで、濃いおかずのときでも必ず綺麗な白い部分を残しておいて最後に食べるんです(笑)」
──白米だけ残しておく……お話を聞いていると、結構なお米好きですね(笑)
「そうなんです! おかずはおかず、お米はお米の味で楽しみたいんです。いまって、お米自体も気分によって選べるくらい選択肢がたくさんあるのはすごくありがたいですよね」

──玄米や雑穀なども召し上がりますか?
「実は玄米はあんまり食べなくて……食感が気になるのでおかゆで楽しんでいます。玄米の生米の状態から出汁と一緒に何時間もコトコト煮ると、食感も気にならないのでおすすめです。食べ終わったチキンの骨を冷凍して取っておいて、ねぎの青い部分と一緒に超弱火で3時間ぐらいほったらかしで煮て塩で味を調えるだけで、おいしい中華粥が出来上がりますよ」
──簡単でおいしそうです! 玄米の食感が気になる方はぜひお試しを。
日本だからこその塩作りを応援していきたい
「お米が日本で食文化として根付いているように、世界の塩作りと比較しても日本の塩作りはすごく特殊で、 海水しか資源がないので製法が進化してるんですよ。
その独特さみたいなものを海外の人が見にきて、そんなめんどくさいことをしないと塩は出来ないのか、日本人クレイジーだぜ! とおもしろい発見として捉えてもらえて、観光資源になったりもします。
せっかくの独自の文化なので、潰さずに継続させていきたいですね。塩仲間はいつでも大募集中です!」


スーパーなどで手軽に購入でき、毎日の食卓に欠かせない「塩」。いつも身近にあるものだからこそ、決まった使い方しかしてきませんでした。
これからは青山さんに紹介いただいた方法で、塩の魅力を余すことなく生かしていきたいですね。まずはスーパーで塩の棚をじっくりチェックすることから始めてみましょう!
青山志穂
(社)日本ソルトコーディネーター協会代表理事。食品メーカーの開発等を経て塩の重要性に気がつき、塩の道へ。講座やメディア出演等を通じて、中立の立場であらゆる塩の最適な使い方を提案している。
青山志穂 Official Site
https://shiho-aoyama.com/
青山さんの著書『免疫力を高める塩レシピ』『日本と世界の塩の図鑑』(あさ出版)が全国書店で好評発売中です。塩のことがもっと知りたい方はぜひ手に取ってみてくださいね。
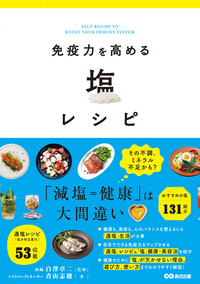
『免疫力を高める塩レシピ』
塩が足りないと、身体のさまざまなところにダメージが出てしまい、免疫力が低下する。だからこそ、適正な質の、適正な量の塩を摂る「適塩生活」が大事。いま、注目の「塩」の働きをきちんと理解し、生活に取り入れることで免疫力を高めるレシピ&健康・美容に役立つ知識を紹介した1冊!
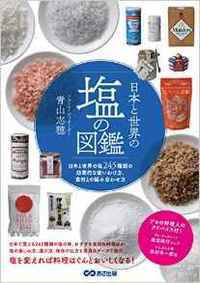
『日本と世界の塩の図鑑』
毎日使う塩なのに、知らないことって意外と多いですよね。本書では、日本で買える245種類の塩の味、塩と合うおすすめ食材&料理、塩の楽しみ方、選び方を写真&データで紹介します。また、塩には賞味期限がない、知られざる塩の使い方、健康法をお伝えします。
(社)日本ソルトコーディネーター協会代表理事。食品メーカーの開発等を経て塩の重要性に気がつき、塩の道へ。講座やメディア出演等を通じて、中立の立場であらゆる塩の最適な使い方を提案している。
青山志穂 Official Site
https://shiho-aoyama.com/
青山さんの著書『免疫力を高める塩レシピ』『日本と世界の塩の図鑑』(あさ出版)が全国書店で好評発売中です。塩のことがもっと知りたい方はぜひ手に取ってみてくださいね。
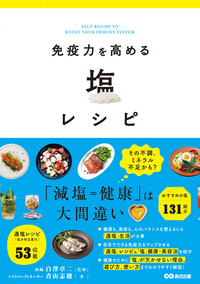
『免疫力を高める塩レシピ』
塩が足りないと、身体のさまざまなところにダメージが出てしまい、免疫力が低下する。だからこそ、適正な質の、適正な量の塩を摂る「適塩生活」が大事。いま、注目の「塩」の働きをきちんと理解し、生活に取り入れることで免疫力を高めるレシピ&健康・美容に役立つ知識を紹介した1冊!
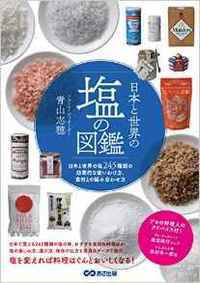
『日本と世界の塩の図鑑』
毎日使う塩なのに、知らないことって意外と多いですよね。本書では、日本で買える245種類の塩の味、塩と合うおすすめ食材&料理、塩の楽しみ方、選び方を写真&データで紹介します。また、塩には賞味期限がない、知られざる塩の使い方、健康法をお伝えします。
取材:編集部
青山志穂さん撮影:齋藤 葵
SHARE













































