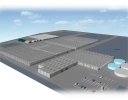日本の農業政策の課題に切り込む書籍「誰が農業を殺すのか」発売
新潮社は、12月20日に書籍『誰が農業を殺すのか』を発売した。価格は946円(税込)。
窪田新之助氏は元・日本農業新聞記者の農業ジャーナリスト。農業問題・中国問題に精通するジャーナリストの山口亮子氏との共著として、日本の農政の問題点を現場視点で徹底的に追求している。
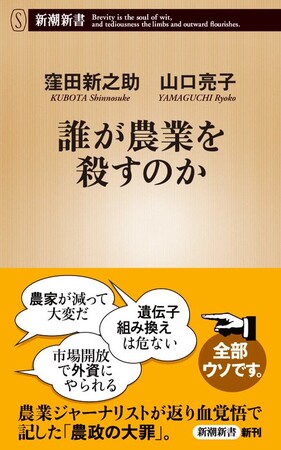
日本の農政は「弱者である農業と農家は保護すべき」という観念に凝り固まっており、産業として独り立ちさせようという発想が全くありません。あらゆる政策がそうした発想から作られているため、しばしば相互に矛盾した政策が繰り出されることになります。
農政の界隈では、「農家の減少は大問題だ」「耕作放棄地が増えて大変だ」という議論が常に言われていますが、日本の主要作物であるコメについては減反政策をとっているわけですから、農家の減少も耕作放棄地の増加もその当たり前の結果に過ぎません。それどころか、「やる気のある農家」が耕作地を担うようになれば、農業の効率性も生産性もあがります。実際、やる気のある農家が耕作地をどんどん引き受け「大規模化」するという流れは続いています。「産業」としての農業にとっては、農家の減少は「いいこと」のはずなのです。なのに、いまでも補助金を出して就農者を支援するような政策があちこちで行われ、農業の「産業化」の邪魔をしています。
日本政府は農産物の輸出額を2030年までに5兆円にするという目標も掲げていますが、もしこうした目標に本気で取り組むなら「減反」なんてやっている場合ではない。輸出振興のベースになるのは、産業を特定の方向に誘導するような政策ではなく、農家の自由な創意を引き出し、産業として独り立ちさせる環境の整備でしょう。しかし、農政が実際にやっているのは、チョコレートやらソースやらといった加工品までも「農林水産物・食品」というカテゴリーにカウントして、「2021年には輸出1兆円を達成しました!」と騒ぎたてることだけ。しかも、輸出振興策の現場を見ると、パックご飯を上海の高級料理店に売り込むような「ズレすぎ」の対応の連続なのです。
日本の農政が国際的な流れと隔絶した対応を続けている中、実は米価が今後、中国の先物市場で決まっていくかも知れない未来も見えてきました。日本ではコメの先物市場はJAなどの反対によって潰されましたが、中国の先物市場は中国のみならず、東アジア全体の米価の基準を示す場になっていく可能性が高いからです。
本書では徹底的に現場の様子を活写することによって、農業政策の矛盾、ズレ、非効率、現実離れした言説のウソ、などをあぶり出していきます。ご一読頂ければ幸いです。
はじめに
第一章 中韓に略奪されっぱなしの知的財産
1 中国の“フルーツのトップスター”はなぜ愛媛生まれなのか
2 “意識高い系”が反対した種苗法改正
3 知的財産権を軽視する農業界の重鎮たち
4 種苗は海外展開で守れ
第二章 「農産物輸出5兆円」の幻想
1 農水省が自賛する「輸出1兆円」の呆れた実態
2 ズレすぎ! 上海の高級料理店でパックご飯をアピール
3 輸出すべきは農産物より知的財産
第三章 農家と農地はこれ以上いらない
1 農家が減れば農業は強くなる
2 減反政策で失われた国際競争力
3 耕作放棄地問題は農水省のマッチポンプ
第四章 「過剰な安心」が農業をダメにする
1 「有機25%」というありえない国家目標
2 「有機0・6%」の現状には理由がある
3 遺伝子組み換え作物こそ、最も安全な食べ物である
第五章 日本のコメの値段が中国で決まる日
1 JAに潰されたコメの先物市場
2 先物市場を国策として推進する中国
第六章 弄ばれる種子
1 「日本の農業がグローバル企業に乗っ取られる」という大ウソ
2 「奨励品種」という排除の論理
第七章 農業政策のブーム「園芸振興」の落とし穴
1 コメを敵視してきた秋田県知事の変節
2 高知県がうまくいっている理由
第八章 「スマート農業」はスマートに進まない
1 農業アプリの開発責任者が利益相反で解任されたスキャンダル
2 「スマート農業」の本質はデータにあり
3 ロボットを使うと効果がマイナスの場合も
おわりに

窪田新之助
「『農業のため』。日頃からそう口にしている人や組織の欺瞞に満ちた姿を描きました。本書を通して、農業の先行きを曇らせている『農政の大罪』を知っていただければ幸いです」
農業ジャーナリスト。日本農業新聞記者を経て、二〇一二年よりフリー。著書に『農協の闇』『データ農業が日本を救う』『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』など。

山口亮子
「原油価格や資材の高騰、コロナ禍による消費の減退など、農業の危機が叫ばれています。今すべきことは、手当たり次第に予算を付けることではなく、産業構造そのものを強くすることではないか。そんな思いで執筆しました」
ジャーナリスト。京都大学文学部卒、中国・北京大学修士課程(歴史学)修了。時事通信記者を経てフリー。執筆テーマは農業や中国。雑誌や広告などの企画編集やコンサルティングを手掛ける株式会社ウロ代表取締役。
著者:窪田新之助、山口亮子
発売日:12月20日
造本:新書
本体定価:946円(税込)
発行:新潮社
URL:https://www.shinchosha.co.jp/book/610976/
窪田新之助氏は元・日本農業新聞記者の農業ジャーナリスト。農業問題・中国問題に精通するジャーナリストの山口亮子氏との共著として、日本の農政の問題点を現場視点で徹底的に追求している。
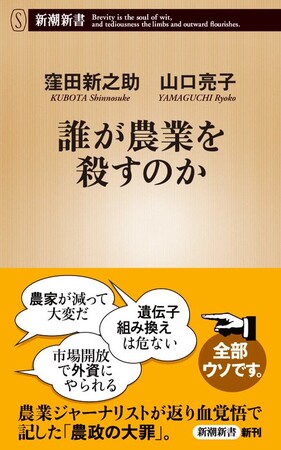
書籍概要
日本の農政は「弱者である農業と農家は保護すべき」という観念に凝り固まっており、産業として独り立ちさせようという発想が全くありません。あらゆる政策がそうした発想から作られているため、しばしば相互に矛盾した政策が繰り出されることになります。
農政の界隈では、「農家の減少は大問題だ」「耕作放棄地が増えて大変だ」という議論が常に言われていますが、日本の主要作物であるコメについては減反政策をとっているわけですから、農家の減少も耕作放棄地の増加もその当たり前の結果に過ぎません。それどころか、「やる気のある農家」が耕作地を担うようになれば、農業の効率性も生産性もあがります。実際、やる気のある農家が耕作地をどんどん引き受け「大規模化」するという流れは続いています。「産業」としての農業にとっては、農家の減少は「いいこと」のはずなのです。なのに、いまでも補助金を出して就農者を支援するような政策があちこちで行われ、農業の「産業化」の邪魔をしています。
日本政府は農産物の輸出額を2030年までに5兆円にするという目標も掲げていますが、もしこうした目標に本気で取り組むなら「減反」なんてやっている場合ではない。輸出振興のベースになるのは、産業を特定の方向に誘導するような政策ではなく、農家の自由な創意を引き出し、産業として独り立ちさせる環境の整備でしょう。しかし、農政が実際にやっているのは、チョコレートやらソースやらといった加工品までも「農林水産物・食品」というカテゴリーにカウントして、「2021年には輸出1兆円を達成しました!」と騒ぎたてることだけ。しかも、輸出振興策の現場を見ると、パックご飯を上海の高級料理店に売り込むような「ズレすぎ」の対応の連続なのです。
日本の農政が国際的な流れと隔絶した対応を続けている中、実は米価が今後、中国の先物市場で決まっていくかも知れない未来も見えてきました。日本ではコメの先物市場はJAなどの反対によって潰されましたが、中国の先物市場は中国のみならず、東アジア全体の米価の基準を示す場になっていく可能性が高いからです。
本書では徹底的に現場の様子を活写することによって、農業政策の矛盾、ズレ、非効率、現実離れした言説のウソ、などをあぶり出していきます。ご一読頂ければ幸いです。
「誰が農業を殺すのか」目次
はじめに
第一章 中韓に略奪されっぱなしの知的財産
1 中国の“フルーツのトップスター”はなぜ愛媛生まれなのか
2 “意識高い系”が反対した種苗法改正
3 知的財産権を軽視する農業界の重鎮たち
4 種苗は海外展開で守れ
第二章 「農産物輸出5兆円」の幻想
1 農水省が自賛する「輸出1兆円」の呆れた実態
2 ズレすぎ! 上海の高級料理店でパックご飯をアピール
3 輸出すべきは農産物より知的財産
第三章 農家と農地はこれ以上いらない
1 農家が減れば農業は強くなる
2 減反政策で失われた国際競争力
3 耕作放棄地問題は農水省のマッチポンプ
第四章 「過剰な安心」が農業をダメにする
1 「有機25%」というありえない国家目標
2 「有機0・6%」の現状には理由がある
3 遺伝子組み換え作物こそ、最も安全な食べ物である
第五章 日本のコメの値段が中国で決まる日
1 JAに潰されたコメの先物市場
2 先物市場を国策として推進する中国
第六章 弄ばれる種子
1 「日本の農業がグローバル企業に乗っ取られる」という大ウソ
2 「奨励品種」という排除の論理
第七章 農業政策のブーム「園芸振興」の落とし穴
1 コメを敵視してきた秋田県知事の変節
2 高知県がうまくいっている理由
第八章 「スマート農業」はスマートに進まない
1 農業アプリの開発責任者が利益相反で解任されたスキャンダル
2 「スマート農業」の本質はデータにあり
3 ロボットを使うと効果がマイナスの場合も
おわりに
著者・コメント紹介

窪田新之助
「『農業のため』。日頃からそう口にしている人や組織の欺瞞に満ちた姿を描きました。本書を通して、農業の先行きを曇らせている『農政の大罪』を知っていただければ幸いです」
農業ジャーナリスト。日本農業新聞記者を経て、二〇一二年よりフリー。著書に『農協の闇』『データ農業が日本を救う』『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』など。

山口亮子
「原油価格や資材の高騰、コロナ禍による消費の減退など、農業の危機が叫ばれています。今すべきことは、手当たり次第に予算を付けることではなく、産業構造そのものを強くすることではないか。そんな思いで執筆しました」
ジャーナリスト。京都大学文学部卒、中国・北京大学修士課程(歴史学)修了。時事通信記者を経てフリー。執筆テーマは農業や中国。雑誌や広告などの企画編集やコンサルティングを手掛ける株式会社ウロ代表取締役。
「誰が農業を殺すのか」書籍情報
著者:窪田新之助、山口亮子
発売日:12月20日
造本:新書
本体定価:946円(税込)
発行:新潮社
URL:https://www.shinchosha.co.jp/book/610976/
SHARE