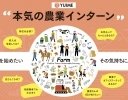お米の販売を通して芽生えた「できることからやろう」という思い【藤本一志の就農コラム 第15回】
こんにちは。岡山県真庭市の兼業農家、藤本一志です。

前回は2020年の新米を食べた感想と、そこから考えたことについて書かせていただきました。これで今年の米作りも終わりかと思いきや、最後に1つ、販売が残っています。
今まではほぼ全量をJAさんに出荷していたのですが、数年前から少しだけ、私の友人・知人にも販売していました。今年も同様にさせていただいたのですが、今までとは異なる印象を受けました。
その販売について、今回は綴らせていただきます。
しかし、あまりにも多い注文をいただいてしまうと対応できません。これは、私の時間的余裕がない、直売への体制が整っていないという理由があるためです。
そこで、今年は試験的な意味合いを込めて、各種SNSの特性をつかむこと・自分の動きを把握することに重点を置くことにしました。販売目標は10件ほど注文をいただければいいと考えていました。
さて、具体的に何をしたかといいますと……今まではFacebookのみで発信してきましたが、新しくInstagramと公式LINEを開始。Facebookで広く発信し、そこから公式LINEに呼び込む。Instagramでは写真を用いた視覚的な情報発信を行い、日々の作業の様子を発信する。そして、実際に人と会う中でも少し話をしてみる。
すると、少しずつ注文の声をいただくようになりました。
去年までは100kgに満たなかった販売量ですが、今年は200kgを超えました。大学時代の友人や恩師だけでなく、真庭市内の方々からも注文をいただきました。特に、仕事を通して新しく知り合えた真庭市内の方々に購入していただけたのは、日々の発信が実ったのかなと思いました。
さらに、真庭市勝山地区で飲食店を営む方からも注文がありました。まさか自分たちの作ったお米がお店で出されるなんて考えてもいなかったので、何とも言えない嬉しさを覚えました。
このように販売に関して発信したのはわずか1カ月程度でしたが、予想以上のご注文をいただくことができました。岡山県内にお住いの方には直接お届けしたのですが、行く先々で「ありがとう」と声をかけられ、非常に嬉しかったです。
それと同時に、今後期待にしっかりと応えて、来年はさらにおいしいお米を届けたい。そして、私自身の考えや取り組みをアップデートしていこうという決意が生まれました。
 以前取材させていただいた景山さんも購入してくれました
以前取材させていただいた景山さんも購入してくれました
また、「おいしかったよ」「来年もまた買いたい」というお声もいただき、なんとも言い難い嬉しい気持ちになりました。まさか、自分たちが作ったものでここまで言ってもらえるなんて……。宣伝方法や営業次第で、もっと直売を拡大できるという手ごたえを感じました。
しかし、動いていく中で見えてくるものをありました。
まずはスケジュール管理。
岡山市と真庭市は車で2時間弱。直売用のお米を準備するためには真庭市から岡山市へ向かう必要がありますが、真庭市での仕事の関係で、毎日のように往復できるわけではありません。
今年の注文は、収穫前の事前予約と籾摺りが終わってからのものが半々でした。注文を受けて、ある程度まとまってから岡山市に向かい、精米や袋詰めなどの作業をする。
真庭市での仕事はシフト制で出勤日が決まっていますが、お米の注文に関してはいつ入るか分からない。まずは予約注文をまとめて対応し、その後はポツポツいただくご注文に対応。どのように動くかある程度想像していましたが、実際にやってみると大変です。
遠くのお客様へ向けた発送の手続き、直接お届けする方との日程調整、そして「満足していただけるか」というプレッシャー。体力的な面よりも、精神的に気を遣いました。
また、計りや冷蔵庫などの設備に関しても課題を感じました。
わが家で使っている計りは昭和初期から使っていると思われるレトロなもの。重りを乗せて釣り合いを見ながら重さを量ります。使い慣れてはいるものの、やはり何袋も計量するには時間がかかります。そのため、デジタル計り、または自動で計量してくれる計りが欲しくなりました。そして冷蔵庫に関しては、お客様からのご要望で必要だと感じました。
注文の中では「年間通してお米を買いたい。」というありがたい声もいただきました。ご希望されたのは1人だったので対応させていただきましたが、今の冷蔵庫の容量だと5人すら年間注文には対応できません。そのため、今後直売を増やしていくためにも、自動で5kg、10kgといった少量を計測できる計りと、大型の冷蔵庫は必要不可欠です。
また、年間お届けのようなメニューも用意して、販売方法にバリエーションを増やしていくことも考えていく必要があると感じます。
 購入していただいたお米
購入していただいたお米
来年はもっといいものを届けたい。そのために、今年感じた課題は何か1つでも乗り越えよう。
そう思いました。
今年の収量は262俵(ヒノヒカリ52俵、アケボノ210俵)。例年より20俵ほど少なくなりました。梅雨の長雨・高温障害・害虫の大量発生により収量が減少したためです(全体的な売り上げは例年と比べて大きな変化はありません。しかし、直販の数は増加しました)。
味は、おそらく例年とあまり変わりません。しかし、籾摺りの段階で「高温障害があったから二等米だろう」ということを聞いていたためか、少し落ちていたような気がします。
それでも、私は今年の米の落ち着いていて好きだと感じました。そして、販売を通して多くの方からお声をかけていただく中で、私の考えにも変化が生じてきました。
それは、「来年は私にしかできないことを伸ばそう」というものです。
今までは、早く生産技術を身に着けて、自分なりの生産方法に変えたいとばかり考えていました。しかし、肥料や農薬の使用などの生産方法全般は、祖父が現役の間はきっと変わることはないでしょう。この道50年以上続けているのですから、そう簡単には変わりません。
しかし、情報発信や販路拡大は、私にしかできない。岡山市から離れた真庭市で、人に関わる仕事をしている私に適任だと思いました。
生産現場に立ち、技術の習得に励む。この姿勢を変えることはありません。だからこそ、生産現場で感じたことやそこで見た風景を、もっと胸を張って発信していこうと思いました。
楽しいこと、苦労したこと、私の思い……いろいろなことを、もっともっと伝えていく。「日本の農業を」なんて大きなことは語れませんが、小さな米農家の考えや生き方を少しでもたくさんの人に知ってほしい。そうやって発信することで、応援してくれる人を増やす。そのうちに、自然と販路の拡大につながるのではないかと思います。
まずは原点に立ち返って、自分が大切にしたい思いを見つめ直す。そして、その思いを元に発信する。
これは今日からできることです。
農業の情報をキャッチすることだけがすべてじゃない。写真を整理するとか、SNSを更新するといった小さなことでいい。来年は「今の自分にできることはやり切った」と言えるように、日々の生活の中で、農業について考える時間を少し増やしたい。そして、さらなるファンの獲得・販路の拡大につなげられればと思います。
 Instagramにアップした写真。こういった農家ならではの写真などを発信していきたい
Instagramにアップした写真。こういった農家ならではの写真などを発信していきたい
次回の記事では、今年1年の振り返りをしようと思います。そして、来年取り組むべき課題について整理しようと思います。
15回コラムを書かせていただく中で、課題だと感じたことはたくさんありました。
1度にすべて解決しようとすると、結局どれも中途半端に終わるでしょう。何個かに絞って、自分にできることを全力で楽しみながら取り組む。
できることからコツコツと。1歩1歩踏みしめながら、農家としての階段を上っていきます。

前回は2020年の新米を食べた感想と、そこから考えたことについて書かせていただきました。これで今年の米作りも終わりかと思いきや、最後に1つ、販売が残っています。
今まではほぼ全量をJAさんに出荷していたのですが、数年前から少しだけ、私の友人・知人にも販売していました。今年も同様にさせていただいたのですが、今までとは異なる印象を受けました。
その販売について、今回は綴らせていただきます。
小さな目標とその結果
SMART AGRIで記事を書かせいただいていること、いつもの年よりSNSで多めに発信していたためか、今年はいつもより「お米を買いたい」という声を多くいただいていました。私としても、今年はやっと自分の理想の生活を始められたので、いつもよりは多めに直売したいと思っていました。しかし、あまりにも多い注文をいただいてしまうと対応できません。これは、私の時間的余裕がない、直売への体制が整っていないという理由があるためです。
そこで、今年は試験的な意味合いを込めて、各種SNSの特性をつかむこと・自分の動きを把握することに重点を置くことにしました。販売目標は10件ほど注文をいただければいいと考えていました。
さて、具体的に何をしたかといいますと……今まではFacebookのみで発信してきましたが、新しくInstagramと公式LINEを開始。Facebookで広く発信し、そこから公式LINEに呼び込む。Instagramでは写真を用いた視覚的な情報発信を行い、日々の作業の様子を発信する。そして、実際に人と会う中でも少し話をしてみる。
すると、少しずつ注文の声をいただくようになりました。
去年までは100kgに満たなかった販売量ですが、今年は200kgを超えました。大学時代の友人や恩師だけでなく、真庭市内の方々からも注文をいただきました。特に、仕事を通して新しく知り合えた真庭市内の方々に購入していただけたのは、日々の発信が実ったのかなと思いました。
さらに、真庭市勝山地区で飲食店を営む方からも注文がありました。まさか自分たちの作ったお米がお店で出されるなんて考えてもいなかったので、何とも言えない嬉しさを覚えました。
このように販売に関して発信したのはわずか1カ月程度でしたが、予想以上のご注文をいただくことができました。岡山県内にお住いの方には直接お届けしたのですが、行く先々で「ありがとう」と声をかけられ、非常に嬉しかったです。
それと同時に、今後期待にしっかりと応えて、来年はさらにおいしいお米を届けたい。そして、私自身の考えや取り組みをアップデートしていこうという決意が生まれました。
 以前取材させていただいた景山さんも購入してくれました
以前取材させていただいた景山さんも購入してくれました動く中で見えてきたもの
短期間の発信にもかかわらず、十数件の注文。販売量も、例年の3倍に増えました。思っていたよりも注文量が多く、少し焦ったところもありましたが、無事にお届けすることができました。また、「おいしかったよ」「来年もまた買いたい」というお声もいただき、なんとも言い難い嬉しい気持ちになりました。まさか、自分たちが作ったものでここまで言ってもらえるなんて……。宣伝方法や営業次第で、もっと直売を拡大できるという手ごたえを感じました。
しかし、動いていく中で見えてくるものをありました。
まずはスケジュール管理。
岡山市と真庭市は車で2時間弱。直売用のお米を準備するためには真庭市から岡山市へ向かう必要がありますが、真庭市での仕事の関係で、毎日のように往復できるわけではありません。
今年の注文は、収穫前の事前予約と籾摺りが終わってからのものが半々でした。注文を受けて、ある程度まとまってから岡山市に向かい、精米や袋詰めなどの作業をする。
真庭市での仕事はシフト制で出勤日が決まっていますが、お米の注文に関してはいつ入るか分からない。まずは予約注文をまとめて対応し、その後はポツポツいただくご注文に対応。どのように動くかある程度想像していましたが、実際にやってみると大変です。
遠くのお客様へ向けた発送の手続き、直接お届けする方との日程調整、そして「満足していただけるか」というプレッシャー。体力的な面よりも、精神的に気を遣いました。
また、計りや冷蔵庫などの設備に関しても課題を感じました。
わが家で使っている計りは昭和初期から使っていると思われるレトロなもの。重りを乗せて釣り合いを見ながら重さを量ります。使い慣れてはいるものの、やはり何袋も計量するには時間がかかります。そのため、デジタル計り、または自動で計量してくれる計りが欲しくなりました。そして冷蔵庫に関しては、お客様からのご要望で必要だと感じました。
注文の中では「年間通してお米を買いたい。」というありがたい声もいただきました。ご希望されたのは1人だったので対応させていただきましたが、今の冷蔵庫の容量だと5人すら年間注文には対応できません。そのため、今後直売を増やしていくためにも、自動で5kg、10kgといった少量を計測できる計りと、大型の冷蔵庫は必要不可欠です。
また、年間お届けのようなメニューも用意して、販売方法にバリエーションを増やしていくことも考えていく必要があると感じます。
 購入していただいたお米
購入していただいたお米喜びから得られた考えの変化
いろいろと課題を感じたものの、自分たちが作ったもので喜んでくれる人たちがいてくれて、私としてはとても嬉しかったです。来年はもっといいものを届けたい。そのために、今年感じた課題は何か1つでも乗り越えよう。
そう思いました。
今年の収量は262俵(ヒノヒカリ52俵、アケボノ210俵)。例年より20俵ほど少なくなりました。梅雨の長雨・高温障害・害虫の大量発生により収量が減少したためです(全体的な売り上げは例年と比べて大きな変化はありません。しかし、直販の数は増加しました)。
味は、おそらく例年とあまり変わりません。しかし、籾摺りの段階で「高温障害があったから二等米だろう」ということを聞いていたためか、少し落ちていたような気がします。
それでも、私は今年の米の落ち着いていて好きだと感じました。そして、販売を通して多くの方からお声をかけていただく中で、私の考えにも変化が生じてきました。
それは、「来年は私にしかできないことを伸ばそう」というものです。
今までは、早く生産技術を身に着けて、自分なりの生産方法に変えたいとばかり考えていました。しかし、肥料や農薬の使用などの生産方法全般は、祖父が現役の間はきっと変わることはないでしょう。この道50年以上続けているのですから、そう簡単には変わりません。
しかし、情報発信や販路拡大は、私にしかできない。岡山市から離れた真庭市で、人に関わる仕事をしている私に適任だと思いました。
生産現場に立ち、技術の習得に励む。この姿勢を変えることはありません。だからこそ、生産現場で感じたことやそこで見た風景を、もっと胸を張って発信していこうと思いました。
楽しいこと、苦労したこと、私の思い……いろいろなことを、もっともっと伝えていく。「日本の農業を」なんて大きなことは語れませんが、小さな米農家の考えや生き方を少しでもたくさんの人に知ってほしい。そうやって発信することで、応援してくれる人を増やす。そのうちに、自然と販路の拡大につながるのではないかと思います。
まずは原点に立ち返って、自分が大切にしたい思いを見つめ直す。そして、その思いを元に発信する。
これは今日からできることです。
農業の情報をキャッチすることだけがすべてじゃない。写真を整理するとか、SNSを更新するといった小さなことでいい。来年は「今の自分にできることはやり切った」と言えるように、日々の生活の中で、農業について考える時間を少し増やしたい。そして、さらなるファンの獲得・販路の拡大につなげられればと思います。
 Instagramにアップした写真。こういった農家ならではの写真などを発信していきたい
Instagramにアップした写真。こういった農家ならではの写真などを発信していきたい次回は今年の米作りの振り返りを
今回の内容で、今年の米作りは終わりました。1年間を通して、実に多くの発見がありました。今年は、これまでで一番田んぼにいる時間が長かったです。だからこそ、感じることが今まで以上に多かったのだと思います。次回の記事では、今年1年の振り返りをしようと思います。そして、来年取り組むべき課題について整理しようと思います。
15回コラムを書かせていただく中で、課題だと感じたことはたくさんありました。
1度にすべて解決しようとすると、結局どれも中途半端に終わるでしょう。何個かに絞って、自分にできることを全力で楽しみながら取り組む。
できることからコツコツと。1歩1歩踏みしめながら、農家としての階段を上っていきます。
【農家コラム】地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム
- 兼業農家就農から3年間で感じた、農業の難しさと楽しさ【藤本一志の就農コラム 第27回】
- 米の反収激減の突破口に……兼業農家が導入できそうな「環境モニタリングシステム」を調べてみた【藤本一志の就農コラム 第26回】
- 兼業農家でも使える水管理システムがないか、調べたり聞いたりしてみた【藤本一志の就農コラム 第25回】
- 最新の「側条施肥田植機」のいいところ・気になったところ【藤本一志の就農コラム 第24回】
- 最新の「側条施肥田植機」のコストパフォーマンスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第23回】
- 移住支援員が紹介する、地方移住を成功させるための3つのポイント【藤本一志の就農コラム 第22回】
- 農家にとって理想の通信販売サービスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第20回】
- 「BASE」で通販サイトを立ち上げました! 【藤本一志の就農コラム 第19回】
- 麦を作りたいから調べてみた・その2【藤本一志の就農コラム 第18回】
- 麦を作りたいから調べてみた・その1【藤本一志の就農コラム 第17回】
- 2020年の振り返りと2021年にやりたいこと【藤本一志の就農コラム 第16回】
- お米の販売を通して芽生えた「できることからやろう」という思い【藤本一志の就農コラム 第15回】
- 消費者、生産者、それぞれが感じる新米の“調味料”【藤本一志の就農コラム 第14回】
- 収穫の秋と新たな課題【藤本一志の就農コラム 第13回】
- 農薬の使用も、結局はバランスが大切【藤本一志の就農コラム 第12回】
- ドローン実演会への参加と新たな決意【藤本一志の就農コラム 第11回】
- 兼業農家にはどんなスマート農業機器が必要か【藤本一志の就農コラム 第10回】
- 防除作業を通して考えた農薬の是非~私が農薬を受け入れられるようになるまで~【藤本一志の就農コラム 第9回】
- 人とのつながりで開く就農への道 ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第8回】
- とある20代の若者が就農に至るまで ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第7回】
- 「遺伝的多様性」に学ぶ、日本の農業の多様性【藤本一志の就農コラム 第6回】
- 都会と田舎での「二拠点生活」の実態【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第5回】
- 家族総出の苗床づくりで感じる農業の魅力【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第4回】
- 農業が地域に果たす役割【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第3回】
- 転職、移住に至った理由と目指す農業像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第2回】
- 26歳の新規就農農家が目指す農家像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第1回】
SHARE