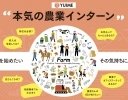人とのつながりで開く就農への道 ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第8回】
岡山県真庭市の兼業農家、藤本一志です。

第7回に引き続き、岡山県久米南町地域おこし協力隊の景山さんのインタビューをお送りします。
前回は、景山さんの地域おこし協力隊になるまでの経験や思いについて紹介しました。
はじめは「人に褒められたい」という純粋な思いから。そして、周りの人に農家になることを応援されながら成長し、人とのつながりの中で、地域おこし協力隊として農家を目指す道を見つけました。
さて、無事に協力隊となった景山さんは、現在どのような活動に取り組んでいるのでしょうか。また、目指す農業とは?
景山さんの協力隊活動の目標は「農業分野から久米南町の関係人口を増やすこと」です。
関係人口とは、移住や観光ではなく、継続的に地域や地域の人々と多様に関わる人口のことです。例えば、私は学生時代に真庭市に通いながら地域活動をしていたので、当時は関係人口にカウントされていました。
景山さんは定住人口を増やすのではなく、農業を通して久米南町に継続的に関わる人を増やすことを目標に、協力隊活動に取り組んでいます。
要するに、「人と町とをつなげる活動」です。
「久米南町って、いろんな形の農業があるんです。ブドウやキュウリの専業農家さん、有機農業の農家さん、自家菜園をされている方。農家さんには、アルバイトが欲しかったり、イベントで一緒に農業を楽しみたかったりと、いろんな要望があります」
協力隊として久米南町全体の農家を見ているからこその言葉です。自分の憧れていた「農家」がこれほどまで多様なことがおもしろいと言わんばかりに、彼女の目は輝いていました。
「農業に関わりたいと思ったときに、いきなりアルバイトで本格的な作業をすることが合わない人もいるじゃないですか。でも収穫してバーベキューしましょうとか、野菜や果物を使ったお菓子作りを作りましょうって形だったら、料理に興味ある人も来てくれるかなと思って。それで、ほかにも農業やってみたいってなれば、町内の農家さんにつなげられるなと思って活動しています。
久米南町は農業の形が多様だから、しっかり関わりたい人はアルバイト、少し興味がある人は収穫体験などの楽しい体験をしてもらうなど、その人にあった農業の形を提供して、農業に関わるきっかけを作りたいと思います」
このように、多様な農業の形と、多様な農業へのニーズを掛け合わせて、農業に関わる人が少しでも増えるよう、彼女は活動しています。
実際に、彼女自身も3反ほどの畑を借りて野菜を栽培しています。
 景山さんが管理する畑。この日はズッキーニの受粉・収穫をしていました
景山さんが管理する畑。この日はズッキーニの受粉・収穫をしていました
畑に行くと、ナスやピーマン、ズッキーニ、カボチャなど、たくさんの野菜が見事に育っていました。昨年はこの畑に、岡山市内から大学生が2人、定期的に作業に訪れていたそうです。
「関係人口、2人ゲットです(笑)」
照れ臭そうな表情から、少しずつ活動が前進しているといううれしさが感じられました。
一方で、ブドウ農家に関しては、ご主人がメインで取り組んでいます。3月に前職を退職し、農業研修生となりました。現在は久米南町のブドウ農家のもとで修行に励む日々です。
当初は、景山さんは協力隊、ご主人は前職を続け、資金が貯まってからブドウ農家になろうと考えていました。しかし、地元農家の集まりに景山さんが参加したところ、
「『お金が貯まってから農家になるなんて遅い』って言われました。1年でも2年でも早く苗を植えたほうがその後の収入が増えるんだから、ローンを組めばいいんだ。これは借金じゃなくて投資なんだから。どうせお金に代わるんだから、早くやればやるほどいいぞって、言われました。だから夫を説得しました(笑)」
それまで穏やかに話していた景山さんが、急に熱くなるのを感じました。
それほど地域の農家さんが、親身になって景山さんを応援しようとしてくれていたんだと、感じました。
そして、急遽方向転換。ご主人を説得し、景山さんは協力隊として活動、ご主人は研修生として修行し、現在の形でブドウ農家を目指すことにしたのです。
「お金のことなど、乗り越えないといけない課題はたくさんあります。でもありがたいことに、地域の皆さんが本当に親身になってアドバイスしてくれるんです。久米南町に通っていたから、いろんな人を紹介され、その人たちに支えられて農家への道を歩めています」
久米南町のブドウ農家の平均耕地面積は78a。ブドウ農家としては広すぎます。そのため、人を雇うことが前提となっています。
そんな地域で、何度も何度も言われたことが「できるだけローンを組んで、現金を手元に残せ」ということ。
現金を使うのは人件費のみ、あとの必要資材などは、ほとんどローンを組んでしまうのが久米南町のブドウ農家さんのやり方だそうです。
景山さんご自身も、現在はローンを組んで、将来のために「投資」をしています。
私は、久米南町は地域ぐるみで若い夫婦の挑戦を応援する、素敵な町だと感じました。景山さんの嬉しそうな姿を見ていると、彼女の思いと行動力が、地域の方々から応援される理由なのだと感じます。
 ブドウの様子をチェックする景山さん
ブドウの様子をチェックする景山さん
では、景山さん自身は、どのような将来を描いているのでしょうか。
「ブドウ農家になっても、現在協力隊として取り組んでいる、人つなぎの活動は続けたいと考えています。当然、その時には協力隊ではありませんが、『農家』として、関係人口を増やせたらな、と。今は協力隊活動の比率が大きいですが、将来的にはブドウ農家と協力隊活動の比率を9:1くらいにしたいと思っています」
そのうえで、久米南町への思いも口にします。
「農業を通していろんな人とつながれば、その人に合った久米南町の農家さんを紹介できます。例えば、しっかり農作業がしたい人はアルバイトを募集している農家さんへ、農作物や土にさわって楽しみたい人には農業のイベントを紹介するといったように、農業に関わる人つなぎをして久米南町に貢献したいと思っています」
ブドウ農家だけではなく、久米南町全体の農業のサポートもする、プラットフォーマーのような取り組みを視野に入れているそう。
「私もですけど、農家さんって人が来てくれるとうれしいんです。今関わりのある農家さんも、新しい人を連れて行くと喜ばれます。私がブドウ農家になっても、新しい人が来てくれたらうれしく感じるんだと思います。そうやって新しい風をどんどん入れていきたいです」
彼女を通じて、農業に関わりたいと思っている人が1歩を踏み出すきっかけを作れる、そして久米南町の農業が盛り上がる。ゆくゆくは久米南町で、またはほかの土地で、農業に取り組む人が増える。
景山さんが小学生の時に感じた「農業の高齢化」という問題を、みんなを巻き込むことで解決しようとしているように感じました。私は、彼女の原点とリンクしていることが不思議でした。
「確かにそうですね。でも、近い年代の人を呼びたいって思いが強いです。農業をしていると、どうしても同じ人とばかり話すようになるので。高齢化の解決というよりも、『息抜きになる』って意味合いの方が強いです」
どうやら、「今を楽しむ」というスタンスが、現在の彼女の原動力のようだです。
 景山さんの育てたズッキーニ。畑の中で元気よく輝いていました
景山さんの育てたズッキーニ。畑の中で元気よく輝いていました
2回にわたって、久米南町地域おこし協力隊、景山美香さんのインタビューをお届けしました。
彼女から感じたのは、ぶれない軸と素直な心。
ずっと「農家になりたい」と言い続ける。
ゆるゆると歩んできたかと思えば、気づけば農家への道を見つける。
久米南町という町を知り、行ってみる。
現地の農家と知り合い、通う。
そして、人とのつながりの中で、自らの夢を叶えようとしています。
私は移住に関する仕事をしていますが、そこで実感するのは「もともと移住先の人とつながっている方が、移住後の生活はうまくいくことが多い」ということです。
景山さんのお話から、農業も同じだと感じました。
景山さんのように、自分が就農しようと考えている地域の人々とつながっておけば、いろいろとサポートをしていただけます。そこには、「チャレンジを応援しよう」という気持ちや、「地域農業の後継者となってくれ」といった思いがあるのでしょう。
そして、人とのつながり作りにおいて、地域おこし協力隊はとても最適な仕事といえます。
景山さんが「いろんな農家さんに行ける」と話していたように、自分が就農する地域だけでなく、もっと大きな「自治体」という意味での地域を見て、そこに住む人々とつながれます。
そして、そのつながりは就農をサポートしてくれる強力な味方となるでしょう。
農業を始めようと思っても、一人では難しいのが現状です。
しかし、人とつながって、信頼関係を築くことができれば、道は開けるでしょう。
目指す農業の形は違えど、生き生きと嬉しそうにしゃべる彼女を見て、私も農業と地域づくりをもっと楽しもうと感じた取材でした。
 彼女が作るブドウが楽しみです
彼女が作るブドウが楽しみです
久米南町地域おこし協力隊 - Facebook
https://www.facebook.com/kumenan

第7回に引き続き、岡山県久米南町地域おこし協力隊の景山さんのインタビューをお送りします。
前回は、景山さんの地域おこし協力隊になるまでの経験や思いについて紹介しました。
はじめは「人に褒められたい」という純粋な思いから。そして、周りの人に農家になることを応援されながら成長し、人とのつながりの中で、地域おこし協力隊として農家を目指す道を見つけました。
さて、無事に協力隊となった景山さんは、現在どのような活動に取り組んでいるのでしょうか。また、目指す農業とは?
関係人口を増やす
景山さんの協力隊活動の目標は「農業分野から久米南町の関係人口を増やすこと」です。
関係人口とは、移住や観光ではなく、継続的に地域や地域の人々と多様に関わる人口のことです。例えば、私は学生時代に真庭市に通いながら地域活動をしていたので、当時は関係人口にカウントされていました。
景山さんは定住人口を増やすのではなく、農業を通して久米南町に継続的に関わる人を増やすことを目標に、協力隊活動に取り組んでいます。
要するに、「人と町とをつなげる活動」です。
「久米南町って、いろんな形の農業があるんです。ブドウやキュウリの専業農家さん、有機農業の農家さん、自家菜園をされている方。農家さんには、アルバイトが欲しかったり、イベントで一緒に農業を楽しみたかったりと、いろんな要望があります」
協力隊として久米南町全体の農家を見ているからこその言葉です。自分の憧れていた「農家」がこれほどまで多様なことがおもしろいと言わんばかりに、彼女の目は輝いていました。
「農業に関わりたいと思ったときに、いきなりアルバイトで本格的な作業をすることが合わない人もいるじゃないですか。でも収穫してバーベキューしましょうとか、野菜や果物を使ったお菓子作りを作りましょうって形だったら、料理に興味ある人も来てくれるかなと思って。それで、ほかにも農業やってみたいってなれば、町内の農家さんにつなげられるなと思って活動しています。
久米南町は農業の形が多様だから、しっかり関わりたい人はアルバイト、少し興味がある人は収穫体験などの楽しい体験をしてもらうなど、その人にあった農業の形を提供して、農業に関わるきっかけを作りたいと思います」
このように、多様な農業の形と、多様な農業へのニーズを掛け合わせて、農業に関わる人が少しでも増えるよう、彼女は活動しています。
実際に、彼女自身も3反ほどの畑を借りて野菜を栽培しています。
 景山さんが管理する畑。この日はズッキーニの受粉・収穫をしていました
景山さんが管理する畑。この日はズッキーニの受粉・収穫をしていました畑に行くと、ナスやピーマン、ズッキーニ、カボチャなど、たくさんの野菜が見事に育っていました。昨年はこの畑に、岡山市内から大学生が2人、定期的に作業に訪れていたそうです。
「関係人口、2人ゲットです(笑)」
照れ臭そうな表情から、少しずつ活動が前進しているといううれしさが感じられました。
ブドウ農家への道
一方で、ブドウ農家に関しては、ご主人がメインで取り組んでいます。3月に前職を退職し、農業研修生となりました。現在は久米南町のブドウ農家のもとで修行に励む日々です。
当初は、景山さんは協力隊、ご主人は前職を続け、資金が貯まってからブドウ農家になろうと考えていました。しかし、地元農家の集まりに景山さんが参加したところ、
「『お金が貯まってから農家になるなんて遅い』って言われました。1年でも2年でも早く苗を植えたほうがその後の収入が増えるんだから、ローンを組めばいいんだ。これは借金じゃなくて投資なんだから。どうせお金に代わるんだから、早くやればやるほどいいぞって、言われました。だから夫を説得しました(笑)」
それまで穏やかに話していた景山さんが、急に熱くなるのを感じました。
それほど地域の農家さんが、親身になって景山さんを応援しようとしてくれていたんだと、感じました。
そして、急遽方向転換。ご主人を説得し、景山さんは協力隊として活動、ご主人は研修生として修行し、現在の形でブドウ農家を目指すことにしたのです。
「お金のことなど、乗り越えないといけない課題はたくさんあります。でもありがたいことに、地域の皆さんが本当に親身になってアドバイスしてくれるんです。久米南町に通っていたから、いろんな人を紹介され、その人たちに支えられて農家への道を歩めています」
久米南町のブドウ農家の平均耕地面積は78a。ブドウ農家としては広すぎます。そのため、人を雇うことが前提となっています。
そんな地域で、何度も何度も言われたことが「できるだけローンを組んで、現金を手元に残せ」ということ。
現金を使うのは人件費のみ、あとの必要資材などは、ほとんどローンを組んでしまうのが久米南町のブドウ農家さんのやり方だそうです。
景山さんご自身も、現在はローンを組んで、将来のために「投資」をしています。
私は、久米南町は地域ぐるみで若い夫婦の挑戦を応援する、素敵な町だと感じました。景山さんの嬉しそうな姿を見ていると、彼女の思いと行動力が、地域の方々から応援される理由なのだと感じます。
 ブドウの様子をチェックする景山さん
ブドウの様子をチェックする景山さんブドウ農家×プラットフォーマー
では、景山さん自身は、どのような将来を描いているのでしょうか。
「ブドウ農家になっても、現在協力隊として取り組んでいる、人つなぎの活動は続けたいと考えています。当然、その時には協力隊ではありませんが、『農家』として、関係人口を増やせたらな、と。今は協力隊活動の比率が大きいですが、将来的にはブドウ農家と協力隊活動の比率を9:1くらいにしたいと思っています」
そのうえで、久米南町への思いも口にします。
「農業を通していろんな人とつながれば、その人に合った久米南町の農家さんを紹介できます。例えば、しっかり農作業がしたい人はアルバイトを募集している農家さんへ、農作物や土にさわって楽しみたい人には農業のイベントを紹介するといったように、農業に関わる人つなぎをして久米南町に貢献したいと思っています」
ブドウ農家だけではなく、久米南町全体の農業のサポートもする、プラットフォーマーのような取り組みを視野に入れているそう。
「私もですけど、農家さんって人が来てくれるとうれしいんです。今関わりのある農家さんも、新しい人を連れて行くと喜ばれます。私がブドウ農家になっても、新しい人が来てくれたらうれしく感じるんだと思います。そうやって新しい風をどんどん入れていきたいです」
彼女を通じて、農業に関わりたいと思っている人が1歩を踏み出すきっかけを作れる、そして久米南町の農業が盛り上がる。ゆくゆくは久米南町で、またはほかの土地で、農業に取り組む人が増える。
景山さんが小学生の時に感じた「農業の高齢化」という問題を、みんなを巻き込むことで解決しようとしているように感じました。私は、彼女の原点とリンクしていることが不思議でした。
「確かにそうですね。でも、近い年代の人を呼びたいって思いが強いです。農業をしていると、どうしても同じ人とばかり話すようになるので。高齢化の解決というよりも、『息抜きになる』って意味合いの方が強いです」
どうやら、「今を楽しむ」というスタンスが、現在の彼女の原動力のようだです。
 景山さんの育てたズッキーニ。畑の中で元気よく輝いていました
景山さんの育てたズッキーニ。畑の中で元気よく輝いていました言い続けること、行ってみること、通うこと
2回にわたって、久米南町地域おこし協力隊、景山美香さんのインタビューをお届けしました。
彼女から感じたのは、ぶれない軸と素直な心。
ずっと「農家になりたい」と言い続ける。
ゆるゆると歩んできたかと思えば、気づけば農家への道を見つける。
久米南町という町を知り、行ってみる。
現地の農家と知り合い、通う。
そして、人とのつながりの中で、自らの夢を叶えようとしています。
私は移住に関する仕事をしていますが、そこで実感するのは「もともと移住先の人とつながっている方が、移住後の生活はうまくいくことが多い」ということです。
景山さんのお話から、農業も同じだと感じました。
景山さんのように、自分が就農しようと考えている地域の人々とつながっておけば、いろいろとサポートをしていただけます。そこには、「チャレンジを応援しよう」という気持ちや、「地域農業の後継者となってくれ」といった思いがあるのでしょう。
そして、人とのつながり作りにおいて、地域おこし協力隊はとても最適な仕事といえます。
景山さんが「いろんな農家さんに行ける」と話していたように、自分が就農する地域だけでなく、もっと大きな「自治体」という意味での地域を見て、そこに住む人々とつながれます。
そして、そのつながりは就農をサポートしてくれる強力な味方となるでしょう。
農業を始めようと思っても、一人では難しいのが現状です。
しかし、人とつながって、信頼関係を築くことができれば、道は開けるでしょう。
目指す農業の形は違えど、生き生きと嬉しそうにしゃべる彼女を見て、私も農業と地域づくりをもっと楽しもうと感じた取材でした。
 彼女が作るブドウが楽しみです
彼女が作るブドウが楽しみです久米南町地域おこし協力隊 - Facebook
https://www.facebook.com/kumenan
【農家コラム】地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム
- 兼業農家就農から3年間で感じた、農業の難しさと楽しさ【藤本一志の就農コラム 第27回】
- 米の反収激減の突破口に……兼業農家が導入できそうな「環境モニタリングシステム」を調べてみた【藤本一志の就農コラム 第26回】
- 兼業農家でも使える水管理システムがないか、調べたり聞いたりしてみた【藤本一志の就農コラム 第25回】
- 最新の「側条施肥田植機」のいいところ・気になったところ【藤本一志の就農コラム 第24回】
- 最新の「側条施肥田植機」のコストパフォーマンスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第23回】
- 移住支援員が紹介する、地方移住を成功させるための3つのポイント【藤本一志の就農コラム 第22回】
- 農家にとって理想の通信販売サービスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第20回】
- 「BASE」で通販サイトを立ち上げました! 【藤本一志の就農コラム 第19回】
- 麦を作りたいから調べてみた・その2【藤本一志の就農コラム 第18回】
- 麦を作りたいから調べてみた・その1【藤本一志の就農コラム 第17回】
- 2020年の振り返りと2021年にやりたいこと【藤本一志の就農コラム 第16回】
- お米の販売を通して芽生えた「できることからやろう」という思い【藤本一志の就農コラム 第15回】
- 消費者、生産者、それぞれが感じる新米の“調味料”【藤本一志の就農コラム 第14回】
- 収穫の秋と新たな課題【藤本一志の就農コラム 第13回】
- 農薬の使用も、結局はバランスが大切【藤本一志の就農コラム 第12回】
- ドローン実演会への参加と新たな決意【藤本一志の就農コラム 第11回】
- 兼業農家にはどんなスマート農業機器が必要か【藤本一志の就農コラム 第10回】
- 防除作業を通して考えた農薬の是非~私が農薬を受け入れられるようになるまで~【藤本一志の就農コラム 第9回】
- 人とのつながりで開く就農への道 ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第8回】
- とある20代の若者が就農に至るまで ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第7回】
- 「遺伝的多様性」に学ぶ、日本の農業の多様性【藤本一志の就農コラム 第6回】
- 都会と田舎での「二拠点生活」の実態【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第5回】
- 家族総出の苗床づくりで感じる農業の魅力【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第4回】
- 農業が地域に果たす役割【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第3回】
- 転職、移住に至った理由と目指す農業像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第2回】
- 26歳の新規就農農家が目指す農家像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第1回】
SHARE