海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】
こんにちは。日本農業サポート研究所の福田浩一です。
今年5月、インドネシアの農業とスマート農業の概要について
「インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由」という記事をインタビュー形式で書きました。
私は2005~2006年、インドネシアで開催されたAPECのワークショップに派遣され、日本の農業や普及活動でのIT活用について講演したことがあります。さらに、2017~2018年には農林水産省が進めている農業情報標準化調査をタイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンのASEAN(東南アジア諸国連合)4カ国で実施しました。
ここ10年間で、ASEAN諸国の農業分野はICTを利用した、スマート農業が普及しています。その普及スピードは私の予想より進んでおり、日本が学べる点も多くあるのではないかと考えています。
そこで今回は、ASEAN随一の大国であるインドネシアのスマート農業の現状を中心に話をうかがい、日本とインドネシア2カ国がお互いから学べる点について考えてみたいと思います。
今回も、インドネシアでのスマート農業の事例と課題について、前回同様名古屋大学大学院にJICA留学生として留学しているインドネシア農業省 企画局企画官のCahyono Tri Wahyu(トリワヒュ・チャヒヨノ)さんにお話をうかがいました。
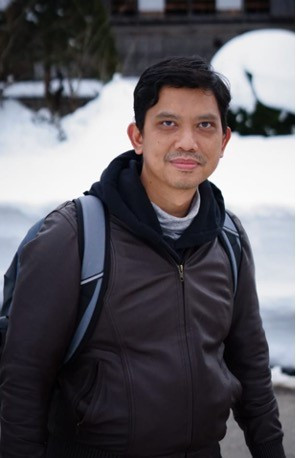 Cahyono Tri Wahyuさん
Cahyono Tri Wahyuさん
まずは、インドネシアの人口、農業およびスマート農業政策について紹介します。2020年のインドネシアの人口は2億7000万人、GDPはASEAN 1位で、タイの約2倍。ASEANの大国だと言えるでしょう。
 ASEAN各国のGDP比較(資料:「World Bank, World Development Indicators database」をもとに筆者作成)
ASEAN各国のGDP比較(資料:「World Bank, World Development Indicators database」をもとに筆者作成)
政府の農業に関する技術革新の概念は、以下の通りです。
「種子、栽培、収穫後の施設の近代化」に関しては、私が訪問した発展途上国の共通の課題だと思います。また、インドネシア政府は生産者に対して生産技術だけでなく、生産者に対して「経営感覚」を持ってもらうことを目指していました。
 政府の技術革新の概念(資料:インドネシア農業省資料をもとに筆者作成)
政府の技術革新の概念(資料:インドネシア農業省資料をもとに筆者作成)
前回の記事で紹介したとおり、2018年以降インドネシア政府は「Smart Farming 4.0」というコンセプトを導入し、農業栽培にドローンとセンサー技術を導入し始めました。
 生産者によるドローン操作(出典:TV Tani Indonesia)
生産者によるドローン操作(出典:TV Tani Indonesia)
インドネシア政府は、農業機械の自動化も推進。スマート農業のプロジェクトを通じて日本と同様、自動運転トラクター、自動運転田植機などの実証も行っています。スマート農機は、中国や日本など国外の農機が多いそうです。
 自動運転トラクター(出典:TV Tani Indonesia)
自動運転トラクター(出典:TV Tani Indonesia)
 自動運転田植機(出典:TV Tani Indonesia)
自動運転田植機(出典:TV Tani Indonesia)
ここからは、インドネシアで実践されているスマート農業の具体的な事例を紹介します。
メロンのスマート温室栽培(西ジャワ州)
ジャワ島では施設園芸、露地野菜などにスマート農業を導入。西ジャワ州ボゴールのポルバンタンでは、メロンのスマート温室プロジェクトが進められています。
 西ジャワ州ボゴールのポルバンタンにおけるメロンのスマート温室プロジェクト。(資料:Tri氏提供資料をもとに筆者作成)
西ジャワ州ボゴールのポルバンタンにおけるメロンのスマート温室プロジェクト。(資料:Tri氏提供資料をもとに筆者作成)
露地野菜の自動灌漑施設(中部ジャワ州)
中部ジャワ州ウォノソボ県では野菜への自動灌漑施設を導入しています。インドネシアでは他の業界から農業に参入して法人として登録し、農業経営を行っている企業的な法人が増えています。
筆者が以前ジャワ島を訪問した際、企業的農家がICT(情報通信技術)など新しい技術に積極的に取り込んでおり、日本のICT事情について熱心に質問されたことをよく覚えています。このあたりは、他業種からスマート農業技術で農業界に参入している日本とも似ています。
 中部ジャワ州ウォノソボ県における野菜への自動灌漑の適用(写真提供:Tri氏)
中部ジャワ州ウォノソボ県における野菜への自動灌漑の適用(写真提供:Tri氏)
タマネギ栽培での土壌・気象センシング(東ジャワ州)
さらにジャワ島東部マラン県にある企業ベースのタマネギ農園は、スタートアップ企業と通信情報省による協働で土壌および気象センサーを利用したスマート農業を行っています。
 タマネギ農園でのスマート農業(写真提供:Tri氏)
タマネギ農園でのスマート農業(写真提供:Tri氏)
リアルタイムの土壌と気象情報を提供する「スマートファーミングシステム」は、Androidのアプリケーションとして開発され、農家の栽培改善に非常に役立てられています。土壌および気象センサーを導入したことで、以下の効果がありました。
NPK(窒素・リン酸・カリウム) や pH 要素に関する情報や正確な施肥情報をリアルタイムで提供。 この技術を利用することで、イネの生産性は最大 20% 向上、タマネギの生産量においては最大30%の増加しながらも、肥料使用を最大 50% 削減できると見込んでいるそうです。このアプリケーションによる気象情報は、農薬や除草剤をいつ散布するかを判断するための栽培管理にも役立っています。
農家と流通を結びつけるマッチングアプリ「PAKTANI DIGITAL」
「PAKTANI DIGITAL」というアプリは、スタートアップ企業が開発し、農家と最終的なバイヤーを結びつけるデジタルなマッチングソフトです。日本からもインストールは可能です。
 アプリ画面例(出典: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagatekno.ptd&hl=ja&gl=US )
アプリ画面例(出典: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagatekno.ptd&hl=ja&gl=US )
このアプリの特徴は、農業者・事業者・政府・一般市民などに有益な農産物の売買価格を知らせること。トウガラシ、トマト、タマネギ、ジャガイモ、キャベツ、ニンジンなど主要な商品に関する価格をチェックできます。
価格データの決定方式は参加型であり、関連する利害関係者に通知されます。このレベルの参加を増やすには、従来のスマートな取り組みだけでなく、デジタル・マーケティングなどの取り組みも必要になりますが、このアプリによって農家・協同組合・仲買人などと、スーパーマーケット等の小売販売店・レストラン等の飲食店・ホテル・病院・ケータリング業者などとの間で行われる売買過程の情報を共有し、お互いの橋渡しをしています。
今回紹介したプロジェクトのほとんどが、中央政府主導のプログラムです。中央政府が管轄する中央普及センターの普及員は、農民グループの組織化と指導を行っています。しかし、普及員自身がまだまだスマート農業についてあまり理解していないため、地方自治体のプログラムを除き、ほとんど関与していません。
 害虫防除方法研修の様子(写真提供:Tri氏)
害虫防除方法研修の様子(写真提供:Tri氏)
また、インドネシアのスマート農業には以下のような課題があります。
こうして見ると、インドネシアの課題は日本と共通しているものが多く、日本側がインドネシアの事例から学べることも多いように思います。
たとえば日本では、米等の生産抑制の中で人件費が高いこともあって、スマート農業の目的として「省力化」に重点が置かれています。
一方、人件費が安く、将来の供給力が不安視されてはいるものの増産意欲の高いインドネシアでのスマート農業の導入目的は「農作物の収量アップ」「農作物の品質向上」「農業労働の効率向上」となっています。「省力化」も目的の一つではありますが、日本ほど重視されていないようです。
インドネシア、日本両国とも、スマート農業推進には、スマート農業を支援する「普及員の教育」「普及員と民間企業の協働」が重要だと思います。また、インドネシアでもスマート農機は農家のレベルに合わせて改良する必要があることに変わりはないと指摘されています。
今回お話をうかがったインドネシアの留学生Triさんは、日本側との継続的な交流を希望しています。それは、日本のスマート農業が大規模農家だけでなく、中小規模の農家も取り入れようとしているからです。
日本の小規模なスマート農業(スモールスマート農業)は中山間地で展開されていますが、多くの小規模農家が活動している発展途上国で直面している状況と、非常に似通っています。
海外のスマート農業の実態について情報が入手しにくい日本の関係者にとっても、異なる視点でスマート農業を進めているインドネシアの状況を知ることは、日本のスマート農業を客観化することができ、大いに参考になると思っています。前述の通り、日本のスマート農業を考える時、人手不足と労賃の高さから、省力化に力点が置かれていますが、今後日本農業を海外の農業とも競争できるように発展させるには、インドネシアのように農産物の収量・品質アップが重視されるべきでしょう。
大規模農家を中心としている欧米諸国などのスマート農業推進とは異なり、日本では中山間地農業振興の一つの手段としてスマート農業を取り入れ、鳥獣害対策や効率化を促そうとしています。この方向性は、インドネシアなど小規模農家が多い新興国や発展途上国のお手本になるはずで、日本の農業関係者は自信を持って進めていくべきだと実感しています。
今年5月、インドネシアの農業とスマート農業の概要について
「インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由」という記事をインタビュー形式で書きました。
私は2005~2006年、インドネシアで開催されたAPECのワークショップに派遣され、日本の農業や普及活動でのIT活用について講演したことがあります。さらに、2017~2018年には農林水産省が進めている農業情報標準化調査をタイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンのASEAN(東南アジア諸国連合)4カ国で実施しました。
ここ10年間で、ASEAN諸国の農業分野はICTを利用した、スマート農業が普及しています。その普及スピードは私の予想より進んでおり、日本が学べる点も多くあるのではないかと考えています。
そこで今回は、ASEAN随一の大国であるインドネシアのスマート農業の現状を中心に話をうかがい、日本とインドネシア2カ国がお互いから学べる点について考えてみたいと思います。
今回も、インドネシアでのスマート農業の事例と課題について、前回同様名古屋大学大学院にJICA留学生として留学しているインドネシア農業省 企画局企画官のCahyono Tri Wahyu(トリワヒュ・チャヒヨノ)さんにお話をうかがいました。
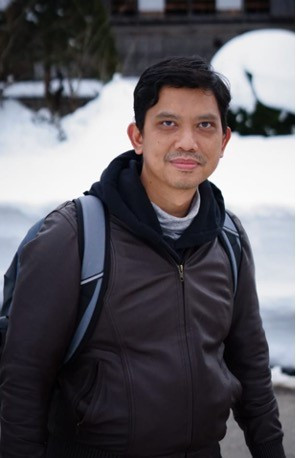 Cahyono Tri Wahyuさん
Cahyono Tri Wahyuさん政府によりスマート農業が推進されているインドネシア
まずは、インドネシアの人口、農業およびスマート農業政策について紹介します。2020年のインドネシアの人口は2億7000万人、GDPはASEAN 1位で、タイの約2倍。ASEANの大国だと言えるでしょう。
 ASEAN各国のGDP比較(資料:「World Bank, World Development Indicators database」をもとに筆者作成)
ASEAN各国のGDP比較(資料:「World Bank, World Development Indicators database」をもとに筆者作成)政府の農業に関する技術革新の概念は、以下の通りです。
- 近代農業(精密農業、スマート農業、機械化)の推進
- 種子、栽培、収穫後の施設の近代化
- 制度や体制強化(生産だけでなく経営感覚醸成)
「種子、栽培、収穫後の施設の近代化」に関しては、私が訪問した発展途上国の共通の課題だと思います。また、インドネシア政府は生産者に対して生産技術だけでなく、生産者に対して「経営感覚」を持ってもらうことを目指していました。
 政府の技術革新の概念(資料:インドネシア農業省資料をもとに筆者作成)
政府の技術革新の概念(資料:インドネシア農業省資料をもとに筆者作成)前回の記事で紹介したとおり、2018年以降インドネシア政府は「Smart Farming 4.0」というコンセプトを導入し、農業栽培にドローンとセンサー技術を導入し始めました。
 生産者によるドローン操作(出典:TV Tani Indonesia)
生産者によるドローン操作(出典:TV Tani Indonesia)インドネシア政府は、農業機械の自動化も推進。スマート農業のプロジェクトを通じて日本と同様、自動運転トラクター、自動運転田植機などの実証も行っています。スマート農機は、中国や日本など国外の農機が多いそうです。
 自動運転トラクター(出典:TV Tani Indonesia)
自動運転トラクター(出典:TV Tani Indonesia) 自動運転田植機(出典:TV Tani Indonesia)
自動運転田植機(出典:TV Tani Indonesia)インドネシア国内の具体的なスマート農業事例
ここからは、インドネシアで実践されているスマート農業の具体的な事例を紹介します。
メロンのスマート温室栽培(西ジャワ州)
ジャワ島では施設園芸、露地野菜などにスマート農業を導入。西ジャワ州ボゴールのポルバンタンでは、メロンのスマート温室プロジェクトが進められています。
 西ジャワ州ボゴールのポルバンタンにおけるメロンのスマート温室プロジェクト。(資料:Tri氏提供資料をもとに筆者作成)
西ジャワ州ボゴールのポルバンタンにおけるメロンのスマート温室プロジェクト。(資料:Tri氏提供資料をもとに筆者作成)露地野菜の自動灌漑施設(中部ジャワ州)
中部ジャワ州ウォノソボ県では野菜への自動灌漑施設を導入しています。インドネシアでは他の業界から農業に参入して法人として登録し、農業経営を行っている企業的な法人が増えています。
筆者が以前ジャワ島を訪問した際、企業的農家がICT(情報通信技術)など新しい技術に積極的に取り込んでおり、日本のICT事情について熱心に質問されたことをよく覚えています。このあたりは、他業種からスマート農業技術で農業界に参入している日本とも似ています。
 中部ジャワ州ウォノソボ県における野菜への自動灌漑の適用(写真提供:Tri氏)
中部ジャワ州ウォノソボ県における野菜への自動灌漑の適用(写真提供:Tri氏)タマネギ栽培での土壌・気象センシング(東ジャワ州)
さらにジャワ島東部マラン県にある企業ベースのタマネギ農園は、スタートアップ企業と通信情報省による協働で土壌および気象センサーを利用したスマート農業を行っています。
 タマネギ農園でのスマート農業(写真提供:Tri氏)
タマネギ農園でのスマート農業(写真提供:Tri氏)リアルタイムの土壌と気象情報を提供する「スマートファーミングシステム」は、Androidのアプリケーションとして開発され、農家の栽培改善に非常に役立てられています。土壌および気象センサーを導入したことで、以下の効果がありました。
- 降水時間の予測
- 植物害虫の発生予測
- 肥料の有効利用
- 生産コスト削減
- 農家の利益の上昇
NPK(窒素・リン酸・カリウム) や pH 要素に関する情報や正確な施肥情報をリアルタイムで提供。 この技術を利用することで、イネの生産性は最大 20% 向上、タマネギの生産量においては最大30%の増加しながらも、肥料使用を最大 50% 削減できると見込んでいるそうです。このアプリケーションによる気象情報は、農薬や除草剤をいつ散布するかを判断するための栽培管理にも役立っています。
農家と流通を結びつけるマッチングアプリ「PAKTANI DIGITAL」
「PAKTANI DIGITAL」というアプリは、スタートアップ企業が開発し、農家と最終的なバイヤーを結びつけるデジタルなマッチングソフトです。日本からもインストールは可能です。
 アプリ画面例(出典: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagatekno.ptd&hl=ja&gl=US )
アプリ画面例(出典: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagatekno.ptd&hl=ja&gl=US )このアプリの特徴は、農業者・事業者・政府・一般市民などに有益な農産物の売買価格を知らせること。トウガラシ、トマト、タマネギ、ジャガイモ、キャベツ、ニンジンなど主要な商品に関する価格をチェックできます。
価格データの決定方式は参加型であり、関連する利害関係者に通知されます。このレベルの参加を増やすには、従来のスマートな取り組みだけでなく、デジタル・マーケティングなどの取り組みも必要になりますが、このアプリによって農家・協同組合・仲買人などと、スーパーマーケット等の小売販売店・レストラン等の飲食店・ホテル・病院・ケータリング業者などとの間で行われる売買過程の情報を共有し、お互いの橋渡しをしています。
省力化目的の日本と、収量・品質アップ目的のインドネシア
今回紹介したプロジェクトのほとんどが、中央政府主導のプログラムです。中央政府が管轄する中央普及センターの普及員は、農民グループの組織化と指導を行っています。しかし、普及員自身がまだまだスマート農業についてあまり理解していないため、地方自治体のプログラムを除き、ほとんど関与していません。
 害虫防除方法研修の様子(写真提供:Tri氏)
害虫防除方法研修の様子(写真提供:Tri氏)また、インドネシアのスマート農業には以下のような課題があります。
- スマート農機のコストが高く、小規模農家は購入・使用する余裕がない。投資回収には5~8年かかる
- 小規模農家は、スマート農業導入の政府の支援を必要としている
- 民間部門は、中規模および大規模な農家にだけスマート農業技術を提供している
- 支援すべき普及員がスマート農業をよく理解していない
こうして見ると、インドネシアの課題は日本と共通しているものが多く、日本側がインドネシアの事例から学べることも多いように思います。
たとえば日本では、米等の生産抑制の中で人件費が高いこともあって、スマート農業の目的として「省力化」に重点が置かれています。
一方、人件費が安く、将来の供給力が不安視されてはいるものの増産意欲の高いインドネシアでのスマート農業の導入目的は「農作物の収量アップ」「農作物の品質向上」「農業労働の効率向上」となっています。「省力化」も目的の一つではありますが、日本ほど重視されていないようです。
“小規模農家を切り捨てない”日本のスマート農業が海外から注目されている
インドネシア、日本両国とも、スマート農業推進には、スマート農業を支援する「普及員の教育」「普及員と民間企業の協働」が重要だと思います。また、インドネシアでもスマート農機は農家のレベルに合わせて改良する必要があることに変わりはないと指摘されています。
今回お話をうかがったインドネシアの留学生Triさんは、日本側との継続的な交流を希望しています。それは、日本のスマート農業が大規模農家だけでなく、中小規模の農家も取り入れようとしているからです。
日本の小規模なスマート農業(スモールスマート農業)は中山間地で展開されていますが、多くの小規模農家が活動している発展途上国で直面している状況と、非常に似通っています。
海外のスマート農業の実態について情報が入手しにくい日本の関係者にとっても、異なる視点でスマート農業を進めているインドネシアの状況を知ることは、日本のスマート農業を客観化することができ、大いに参考になると思っています。前述の通り、日本のスマート農業を考える時、人手不足と労賃の高さから、省力化に力点が置かれていますが、今後日本農業を海外の農業とも競争できるように発展させるには、インドネシアのように農産物の収量・品質アップが重視されるべきでしょう。
大規模農家を中心としている欧米諸国などのスマート農業推進とは異なり、日本では中山間地農業振興の一つの手段としてスマート農業を取り入れ、鳥獣害対策や効率化を促そうとしています。この方向性は、インドネシアなど小規模農家が多い新興国や発展途上国のお手本になるはずで、日本の農業関係者は自信を持って進めていくべきだと実感しています。
【連載】“生産者目線”で考えるスマート農業
- 世界有数の農産物輸出国、タイの農業現場から見える “スマートな農業経営”の現実【生産者目線でスマート農業を考える 第30回】
- アフリカのスマート農業はどうなっているのか? ギニアの農業専門家に聞きました【生産者目線でスマート農業を考える 第29回】
- 農業DXで先を行く台湾に学ぶ、スマート農業の現状【生産者目線でスマート農業を考える 第28回】
- スマート農業の本質は経営をスマートに考えること【生産者目線でスマート農業を考える 第27回】
- 肥料高騰のなか北海道で普及が進む「衛星画像サービス」の実効性【生産者目線でスマート農業を考える 第26回】
- 中山間地の稲作に本当に必要とされているスマート農業とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第25回】
- 海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】
- ロボットが常時稼働する理想のスマートリンゴ園の構築は可能か?【生産者目線でスマート農業を考える 第23回】
- 日本産野菜の輸出に関わるQRコードを使ったトレーサビリティの「見える化」【生産者目線でスマート農業を考える 第22回】
- インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由【生産者目線でスマート農業を考える 第21回】
- みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】
- スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】
- 生産者にとって本当に役立つ自動灌水、自動換気・遮光システムとは【生産者目線でスマート農業を考える 第18回】
- JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】
- スマート農機の導入コストを大幅に下げる、日本の「農業コントラクター事業」普及・拡大の展望 【生産者目線でスマート農業を考える 第16回】
- AI農薬散布ロボットによってユリの農薬使用量50%削減へ【生産者目線でスマート農業を考える 第15回】
- 農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】
- ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”【生産者目線でスマート農業を考える 第13回】
- IoTカメラ&電気柵導入でわかった、中山間地での獣害対策に必要なこと【生産者目線でスマート農業を考える 第12回】
- 直進アシスト機能付き田植機は初心者でも簡単に使えるのか?【生産者目線でスマート農業を考える 第11回】
- 全国初! 福井県内全域をカバーするRTK固定基地局はスマート農業普及を加速させるか?【生産者目線でスマート農業を考える 第10回】
- キャベツ栽培を「見える化」へ導く「クロノロジー型危機管理情報共有システム」とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第9回】
- ブロッコリー収穫機で見た機械化と栽培法との妥協方法【生産者目線でスマート農業を考える 第8回】
- コロナ禍で急速に進化するICT活用とスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第7回】
- 徳島県のミニトマトハウスで見たスマート農業で、軽労化と高能率化を同時に実現する方法【生産者目線でスマート農業を考える 第6回】
- 若手後継者を呼び込むスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第5回】
- 地上を走るドローンによるセンシングをサポートする普及指導員【生産者目線でスマート農業を考える 第4回】
- スマート農機は安くないと普及しない?【生産者目線でスマート農業を考える 第3回】
- 果樹用ロボットで生産者に寄り添うスマート農機ベンチャー【生産者目線でスマート農業を考える 第2回】
- 浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」【生産者目線でスマート農業を考える 第1回】
SHARE















































