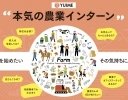ドローン防除を体験! 未来が少し近づいた一日【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第13回】
「SMART AGRI」をご覧のみなさん、こんにちは。さわちんと申します。
現在38歳で、妻と小学生の子ども2人の4人家族です。
前回は、ユズの収穫について、お伝えしました。その独特な香りと爽やかな酸味をお試しいただけたでしょうか? 冬至にはお風呂にユズを浮かべるという方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、日常の癒しにユズをお使いくださいね。さわちんは毎晩のようにユズ焼酎で酔っ払っています(笑)
さて、たまにはSMART AGRIのコンセプトに沿った内容をお届けしたい! ということで、今回は、かんきつアカデミーの授業にて、防除用ドローンの講義と防除デモがありましたので、その様子をお伝えしたいと思います。
 イラスト:ヤマハチ
イラスト:ヤマハチ

DJI社の「AGRAS T20」というずっしりとした重厚感のあるドローンで、計6枚のプロペラがついており、16リットルの農薬散布用タンクを搭載しています。ちなみに1枚プロペラが壊れても、飛行を続けることができるのだそう。それにしてもこんな重いタンクを搭載して飛べるんだろうか……という、さわちんの不安を払拭するかのごとく、華麗に空へ舞い上がるドローン。しかも音が思ったよりも静か!
今回はたくさんの木にまんべんなく農薬を散布するモードと、1本の木に重点的に農薬を散布するモード、2つのデモを見せてもらいました。
リモコンを持って操縦している担当者の方に、「やっぱり操縦は気を使いますか? 」と質問したところ、「いえ、全然! 」との答えが。
というのも、今回のデモでは、予め圃場全体を3Dマップとして取り込み、飛行ルートをプログラミングした「自動操縦モード」。よほど不意なアクシデントが起こらない限りは、手動で操縦することはないそうです。
す、すげぇ……と思いつつ、その性能を見学することに。

やっぱりすごい! 防除対象としている木の真上でぴったり静止し、農薬を散布し始めました。ダウンウォッシュ(ドローンのプロペラの回転によってできる下降気流のこと)を利用して農薬を散布するため、目的の木に対して的確に散布できているように見えます。
農薬を的確に散布することは、農薬使用料の節約だけではなく、周囲への影響も少なく済むので、まさに一石二鳥。
デモを目の当たりにして、これは便利だと心から思いました。こんなに便利なドローン防除、なぜ果樹業界では普及が遅れているのか、その原因を解明するヒントを担当の方からもらいました。
なんで? と思う方に、順を追って説明しますね。
今回のドローンが1度の飛行で搭載できる農薬は16リットル。この量である程度の広い面積の防除を行えなければ、省力化にはつながりません。そのため、濃度を濃くして散布する必要があります。
例えば、黒点病にとても効力を発揮する「ジマンダイセン」という農薬があります。ミカンの木に人力で散布する場合、濃度は400~800倍で、「10aあたり200~700リットル散布する」という基準が定められています。
もし、ドローンでこの農薬を使用する場合、濃度は5倍で、10aあたり4リットル散布すると定められているのです。
この基準を作るのは農薬メーカーさんの仕事ですが、これがとてつもなく大変なんです。この濃度で散布したときに、効果はちゃんと出るのか? 農薬散布による薬害は出ないか? 果実に農薬が残留しないか? ……などのさまざまな懸念点をすべて確認する必要が出てきます。テストにテストを重ねるため、使用できるまでに数年かかることもざらにあるそうです。
この手間と時間をかけてまで、ドローンでの使用登録が必要か? という判断を農薬メーカーさんが慎重に行っているところも、登録農薬が少ないという原因の一つ。
逆に言うと、ここまで確認しているからこそ、しっかり基準を守って使うことで日本の農薬はほとんど影響がないといえるんですね。
試験方法として、葉の表側と裏側に、水がかかると色が変わる試験紙を取り付け、ドローンでの散布を実施してもらいました。結果を確認してみると……葉の表側の試験紙は、しっかりと色が変わっており、農薬がかかったことが確認できましたが、葉の裏側の試験紙はほとんど色が変わっていませんでした。
先に記載した「ジマンダイセン」のような、病気に対する農薬であれば、葉の表側にかかっていれば、その効力をしっかり発揮できるのですが、害虫駆除を目的とした場合、特にダニ対策の防除をする際は、葉の裏や木の幹にもしっかりと農薬を散布しなくてはいけません。環境や条件によって結果は変わると思いますが、今回の結果から考察すると、害虫駆除を目的とした場合、しっかりと防除ができたとはいえないでしょう。
せっかく防除をしたのに、害虫の被害を受けては元も子もありません。この辺りにどういった改善ができるか、今後の注目ポイントですね。
従来の動力噴霧器を使う防除の回数がゼロになるわけではありませんが、省力化の効果は抜群といえます。 担当者の方の話を聞くと、今まで防除に丸2日かかっていたミカン農園にて、ドローンを使って防除を実施したところ、1時間半で終了したそう。人体への影響も少なく、農薬使用量も削減できたことで農家さんはとっても喜んでくれたそうです。
今回のデモを体験して、未来が今になった感覚を覚えたさわちんです。まだまだ改善する余地はありそうですが、すべての防除をドローンに置き換えるのではなく、半分人力での散布、半分ドローンでの散布のような使い方でも、十分な省力化につながると思います。
これからも自分のアンテナを伸ばして、最新の情報を収集していくつもりです。
さて次回は、お借りしたハウスのビニール張りが完了し、ついに動き出したさわちんのチンゲンサイ栽培の状況と、今後の展望をお伝えしようと思います。果たしてうまく育てることができるのか、不安がいっぱいの農家見習いにご期待ください!
現在38歳で、妻と小学生の子ども2人の4人家族です。
前回は、ユズの収穫について、お伝えしました。その独特な香りと爽やかな酸味をお試しいただけたでしょうか? 冬至にはお風呂にユズを浮かべるという方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、日常の癒しにユズをお使いくださいね。さわちんは毎晩のようにユズ焼酎で酔っ払っています(笑)
さて、たまにはSMART AGRIのコンセプトに沿った内容をお届けしたい! ということで、今回は、かんきつアカデミーの授業にて、防除用ドローンの講義と防除デモがありましたので、その様子をお伝えしたいと思います。
 イラスト:ヤマハチ
イラスト:ヤマハチかんきつアカデミーの空を舞う! 防除用ドローン「DJI AGRAS T20」
やっぱり実物を見るとワクワクが止まりませんね! 今回使用したドローンはこちらです。
DJI社の「AGRAS T20」というずっしりとした重厚感のあるドローンで、計6枚のプロペラがついており、16リットルの農薬散布用タンクを搭載しています。ちなみに1枚プロペラが壊れても、飛行を続けることができるのだそう。それにしてもこんな重いタンクを搭載して飛べるんだろうか……という、さわちんの不安を払拭するかのごとく、華麗に空へ舞い上がるドローン。しかも音が思ったよりも静か!
今回はたくさんの木にまんべんなく農薬を散布するモードと、1本の木に重点的に農薬を散布するモード、2つのデモを見せてもらいました。
リモコンを持って操縦している担当者の方に、「やっぱり操縦は気を使いますか? 」と質問したところ、「いえ、全然! 」との答えが。
というのも、今回のデモでは、予め圃場全体を3Dマップとして取り込み、飛行ルートをプログラミングした「自動操縦モード」。よほど不意なアクシデントが起こらない限りは、手動で操縦することはないそうです。
す、すげぇ……と思いつつ、その性能を見学することに。

やっぱりすごい! 防除対象としている木の真上でぴったり静止し、農薬を散布し始めました。ダウンウォッシュ(ドローンのプロペラの回転によってできる下降気流のこと)を利用して農薬を散布するため、目的の木に対して的確に散布できているように見えます。
農薬を的確に散布することは、農薬使用料の節約だけではなく、周囲への影響も少なく済むので、まさに一石二鳥。
デモを目の当たりにして、これは便利だと心から思いました。こんなに便利なドローン防除、なぜ果樹業界では普及が遅れているのか、その原因を解明するヒントを担当の方からもらいました。
登録農薬が少ない
ずばり、これが果樹業界においてドローンの普及が遅れている大きな理由の一つです。人力の散布では使える農薬も、ドローンで使用するとなると、新たに使用登録を申請する必要があります。なんで? と思う方に、順を追って説明しますね。
今回のドローンが1度の飛行で搭載できる農薬は16リットル。この量である程度の広い面積の防除を行えなければ、省力化にはつながりません。そのため、濃度を濃くして散布する必要があります。
例えば、黒点病にとても効力を発揮する「ジマンダイセン」という農薬があります。ミカンの木に人力で散布する場合、濃度は400~800倍で、「10aあたり200~700リットル散布する」という基準が定められています。
もし、ドローンでこの農薬を使用する場合、濃度は5倍で、10aあたり4リットル散布すると定められているのです。
この基準を作るのは農薬メーカーさんの仕事ですが、これがとてつもなく大変なんです。この濃度で散布したときに、効果はちゃんと出るのか? 農薬散布による薬害は出ないか? 果実に農薬が残留しないか? ……などのさまざまな懸念点をすべて確認する必要が出てきます。テストにテストを重ねるため、使用できるまでに数年かかることもざらにあるそうです。
この手間と時間をかけてまで、ドローンでの使用登録が必要か? という判断を農薬メーカーさんが慎重に行っているところも、登録農薬が少ないという原因の一つ。
逆に言うと、ここまで確認しているからこそ、しっかり基準を守って使うことで日本の農薬はほとんど影響がないといえるんですね。
上空からの散布なので、農薬がかかりにくい部分がある
これもなかなかの問題の一つです。今回のデモで、どれだけ木や葉に農薬がかかっているか、試験をしてみました。試験方法として、葉の表側と裏側に、水がかかると色が変わる試験紙を取り付け、ドローンでの散布を実施してもらいました。結果を確認してみると……葉の表側の試験紙は、しっかりと色が変わっており、農薬がかかったことが確認できましたが、葉の裏側の試験紙はほとんど色が変わっていませんでした。
先に記載した「ジマンダイセン」のような、病気に対する農薬であれば、葉の表側にかかっていれば、その効力をしっかり発揮できるのですが、害虫駆除を目的とした場合、特にダニ対策の防除をする際は、葉の裏や木の幹にもしっかりと農薬を散布しなくてはいけません。環境や条件によって結果は変わると思いますが、今回の結果から考察すると、害虫駆除を目的とした場合、しっかりと防除ができたとはいえないでしょう。
せっかく防除をしたのに、害虫の被害を受けては元も子もありません。この辺りにどういった改善ができるか、今後の注目ポイントですね。
課題は見えつつもメリットたっぷりのドローン防除
稲作や大規模な露地栽培では、すでに取り入れられているドローン防除。果樹に関しては、上記のような課題が見えつつも、実は年間の防除の半数以上が、ドローン防除で十分効力を発揮できると想定されています。従来の動力噴霧器を使う防除の回数がゼロになるわけではありませんが、省力化の効果は抜群といえます。 担当者の方の話を聞くと、今まで防除に丸2日かかっていたミカン農園にて、ドローンを使って防除を実施したところ、1時間半で終了したそう。人体への影響も少なく、農薬使用量も削減できたことで農家さんはとっても喜んでくれたそうです。
今回のデモを体験して、未来が今になった感覚を覚えたさわちんです。まだまだ改善する余地はありそうですが、すべての防除をドローンに置き換えるのではなく、半分人力での散布、半分ドローンでの散布のような使い方でも、十分な省力化につながると思います。
これからも自分のアンテナを伸ばして、最新の情報を収集していくつもりです。
さて次回は、お借りしたハウスのビニール張りが完了し、ついに動き出したさわちんのチンゲンサイ栽培の状況と、今後の展望をお伝えしようと思います。果たしてうまく育てることができるのか、不安がいっぱいの農家見習いにご期待ください!
【農家コラム】さわちんの「リアルタイム新規就農日記」
- 新規就農に必要なのはITスキル・コミュ力・マネジメント力! さらに成長した姿で会いましょう! 【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第14回】
- 農家2年目! 目標所得を達成するためには【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第13回】
- チンゲンサイ農家1年生の収支をご報告! 【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第12回】
- Uターン就農2年目突入! 2021年の成績&2022年の抱負を語ります【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第10回】
- Uターン就農1年! 直面している「困ったこと」【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第9回】
- 就農1年目! チンゲンサイ農家の収入・経費・人件費を大公開します!【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第8回】
- ネットショップ計画、始動します! 【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第7回】
- 理想の「スマートセンサー」はどれ? いろいろ調べてみた【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第6回】
- 新米農家は記録が肝心! 「アグリノート」を使ってみた【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第5回】
- 「もったいない」精神を発揮! 廃棄野菜を利用する方法を考えてみた【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第4回】
- 新しい販路・「JA」に出荷しました!【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第3回】
- 駆け出し農家のとある日の収益【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第2回】
- デビューほやほや! 新米農家の一日の仕事【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第1回】
- 農業大学校を卒業しました!【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第21回】
- さわちんオススメ! 美味しいかんきつトップ5【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第20回】
- まるで修行!? な剪定作業【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第19回】
- 何かと物要りな就農! 補助金を申請してみた【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第18回】
- 初めてチンゲンサイが売れました! 【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第17回】
- スムーズな水やりが実現! 灌水設備を作ってみた【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第16回】
- 新規就農1年で学んだ「いま農家になるために必要なこと」【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第15回】
- ついに栽培を開始したチンゲンサイにさっそく“アイツ”が……【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第14回】
- ドローン防除を体験! 未来が少し近づいた一日【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第13回】
- ユズの収穫は思ったよりも大変!【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第12回】
- 想像以上に重労働! 初めてのビニールハウス【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第11回】
- 移住&新規就農からの半年間を振り返ってみました【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第10回】
- 移住して半年。新型コロナ禍を移住先で過ごした家族の感想は? 【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第9回】
- 農業大学校でIoTセンサーを導入して気づいたこと【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第8回】
- 農家研修で身をもって知った、かんきつ農家の苦労【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第7回】
- 「農業大学校」で学んでいること【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第6回】
- 念願の農地(ビニールハウス)をゲット!【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第5回】
- 移住して3カ月、家族の感想は……?【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第4回】
- 移住セミナーで決心! さわちん一家、移住する!【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第3回】
- 就農で理想の子育てを実現したい! 家族に打ち明けた思い【さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第2回】
- この手で農業のイメージを変える! 私が就農を目指すまで【農家見習い・さわちんの「リアルタイム新規就農日記」第1回】
SHARE