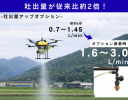優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)
佐賀県伊万里市でキュウリを養液栽培する中山道徳さん(33)は、土耕から固形培地に、整枝法は摘心からつる下ろしに刷新した。
 佐賀県伊万里市でキュウリを養液栽培する中山道徳さん
佐賀県伊万里市でキュウリを養液栽培する中山道徳さん
従来の方法で反収40tを超えながらも栽培法の変更にあえて挑んだのは、生産の安定と省力化のため。
そこには規模拡大への備えとともに、産地の発展に向けた思いがあった。
伊万里市大川町に広がる水田の一角に立つ軒高2.4mのハウス。入ってすぐに気づくのは、地面のどこにも土が見えないことだ。代わって敷いてあるのは白い防草シート。その上にココナッツの繊維を素材にした固形培地が一定の間隔で整然と並べてある。シートからの反射もあり、光が作物にまんべんなく当たっているのが印象的である。
 省力化と規模拡大のため導入した固形培地
省力化と規模拡大のため導入した固形培地
中山さんが土耕を止めたのは、6~8月の土づくりや太陽熱消毒をしないで済ませたかったから。
「暑い夏の時期に土づくりのためといって、大量の麦わらや米ぬかを入れるのはめちゃくちゃきつい。太陽熱消毒にしても同じ。自分でもそうなのに、従業員はそんな作業はしたくないですよね」
土耕栽培で収量を落とさないためには、土づくりも太陽熱消毒も欠かせない。ただ、それができるのは「若くて体力があるから」。いずれ年齢を重ねていったとき、満足のいく作業ができるか自信はない。
しかも農家が今後も減る中、残る農家は経営面積を拡大するのが望ましい。前回紹介した通り、中山さんはJA伊万里きゅうり部会に所属している。部会の主な出荷先は市場である以上、産地の維持と発展のためには生産量の確保が求められるからだ。
では、その時に従業員が自分と同じように土づくりや太陽熱消毒をこなしてくれるだろうか。中山さんはそうなるとは思えなかった。
固形培地には周囲から疑問視する声が挙がった。佐賀県では誰も試したことがなく、全国でも取り組んだ事例が少なかったからだ。
ただ、自信はあった。一つは施設園芸の先進国では固形培地を使うのは一般的だから。もう一つは過去の経験から、常識はいつかひっくり返されるものだということを学んだからだ。
「一例を挙げると、以前のキュウリづくりは根をとにかく広く生やしたほうが収量が上がるというので、辺り一帯に灌水することが常識やったですね。でも、海外では灌水する範囲は小さい根圏で構わない。むしろ適期に適量をまくことが大事。実際に試したところ、そっちのほうが取れたんです。それなら固形培地でもいけると思いました」
同時に整枝法は経験値が求められる摘心から、初心者でも適期だけ逃さなければこなせるつるおろしに変えた。つるおろしは産地として取り組みが少なく、個人として初めてだったものの、初年度に10a当たりの収量で40tを挙げた。
「この40tは土耕と固形培地では違う意味を持つ」と中山さん。
既述の通り、土耕は経験がものをいう。一方、固形培地は養液の供給量と排出量、培地の重量、pHやECなどをデータで確認できるようになった。「見える化」したことで、中山さんは「自分以外でも管理しやすくなった。つまり面積を広げていける素地ができた」と語る。
中山さんは軒高が4mに及ぶ23aのハウスを建て、2020年産からキュウリの栽培を始めている。重視したのは従業員が働きやすい環境づくりだ。「軒が高い分だけ換気が良く、作業しやすくなっています」
ハウス内の特徴を挙げれば、さまざまな工夫から、人が重量物を持ち運びしないで済むようになっていることである。入り口の向こうにあるのは管理棟。施設内環境の制御盤や養液の貯留槽などを備えた場所だ。ここから栽培棟に向かって真っすぐなレールが敷いてある。収穫物を詰め込むコンテナを載せる台車を行き来させるためだ。
 ハウスの中央を走るレール
ハウスの中央を走るレール
栽培棟に入ると、レールの左右にキュウリが植えてある。片側の直線距離は32m。この数字には意味があるそうだ。「奥からキュウリを収穫していくと、レールのところまで来た時にちょうどコンテナが一杯になるんです」
 イチゴの収穫用の四輪車をキュウリの初期の摘葉に使っている
イチゴの収穫用の四輪車をキュウリの初期の摘葉に使っている
畝間で作業をする従業員を見ると、大人の膝上くらいの位置に椅子を搭載した小型の四輪車に座っていた。これはイチゴを収穫するために開発された台車。初期の摘葉に使っている。台車にはコンテナを載せられ、摘んだ葉を入れていく。
別の畝間には昇降台車があった。人が台車に乗って立ち、ハイワイヤーに巻きついたつるを下ろす。立った時に手元にあるレバーを動かせば、車体が前後に移動する。
 つるおろしのための昇降台車
つるおろしのための昇降台車
「これもそうです、コーティングさせたんです」
そう言って中山さんが指さした先の鉄骨は白色だった。特殊な塗料で白色にした目的は二つある。一つは光を反射させて作物に当てること。もう一つは鉄骨に熱を持たせないことで、夏場に室温の上昇を抑えることだ。
ちなみにこのハウスでは補助金の申請の関係で土耕を採用しているものの、近いうちに固形培地に変更するという。
「水田にハウスを建てているので、土耕だと場所によって排水性や肥沃度が違う。一方、固形培地は再現性がある。もう一つは作業性を改善。作業環境が悪いところは誰もしたがらないですよね。面積をさらに拡大するための雇用を増やすのであれば、まずはいかに良い作業環境を作れるが経営者には問われてくると思います」
 中山さんが2020年から栽培を始めた軒が高いハウス
中山さんが2020年から栽培を始めた軒が高いハウス
中山さんは2022年までに30a強のハウスを増設する予定だ。JA伊万里管内ではその先駆的な取り組みに刺激を受け、キュウリの栽培で環境制御技術を導入する農家が増えている。同JAによると、2021年産では一戸の農家が固形培地を試すという。一人の優れた経営者によって産地に変革の気運が高まっている。
 佐賀県伊万里市でキュウリを養液栽培する中山道徳さん
佐賀県伊万里市でキュウリを養液栽培する中山道徳さん従来の方法で反収40tを超えながらも栽培法の変更にあえて挑んだのは、生産の安定と省力化のため。
そこには規模拡大への備えとともに、産地の発展に向けた思いがあった。
土づくりや太陽熱消毒を省略したい
伊万里市大川町に広がる水田の一角に立つ軒高2.4mのハウス。入ってすぐに気づくのは、地面のどこにも土が見えないことだ。代わって敷いてあるのは白い防草シート。その上にココナッツの繊維を素材にした固形培地が一定の間隔で整然と並べてある。シートからの反射もあり、光が作物にまんべんなく当たっているのが印象的である。
 省力化と規模拡大のため導入した固形培地
省力化と規模拡大のため導入した固形培地中山さんが土耕を止めたのは、6~8月の土づくりや太陽熱消毒をしないで済ませたかったから。
「暑い夏の時期に土づくりのためといって、大量の麦わらや米ぬかを入れるのはめちゃくちゃきつい。太陽熱消毒にしても同じ。自分でもそうなのに、従業員はそんな作業はしたくないですよね」
規模拡大の壁を取り払う
土耕栽培で収量を落とさないためには、土づくりも太陽熱消毒も欠かせない。ただ、それができるのは「若くて体力があるから」。いずれ年齢を重ねていったとき、満足のいく作業ができるか自信はない。
しかも農家が今後も減る中、残る農家は経営面積を拡大するのが望ましい。前回紹介した通り、中山さんはJA伊万里きゅうり部会に所属している。部会の主な出荷先は市場である以上、産地の維持と発展のためには生産量の確保が求められるからだ。
では、その時に従業員が自分と同じように土づくりや太陽熱消毒をこなしてくれるだろうか。中山さんはそうなるとは思えなかった。
常識はひっくり返されるもの
固形培地には周囲から疑問視する声が挙がった。佐賀県では誰も試したことがなく、全国でも取り組んだ事例が少なかったからだ。
ただ、自信はあった。一つは施設園芸の先進国では固形培地を使うのは一般的だから。もう一つは過去の経験から、常識はいつかひっくり返されるものだということを学んだからだ。
「一例を挙げると、以前のキュウリづくりは根をとにかく広く生やしたほうが収量が上がるというので、辺り一帯に灌水することが常識やったですね。でも、海外では灌水する範囲は小さい根圏で構わない。むしろ適期に適量をまくことが大事。実際に試したところ、そっちのほうが取れたんです。それなら固形培地でもいけると思いました」
同時に整枝法は経験値が求められる摘心から、初心者でも適期だけ逃さなければこなせるつるおろしに変えた。つるおろしは産地として取り組みが少なく、個人として初めてだったものの、初年度に10a当たりの収量で40tを挙げた。
「この40tは土耕と固形培地では違う意味を持つ」と中山さん。
既述の通り、土耕は経験がものをいう。一方、固形培地は養液の供給量と排出量、培地の重量、pHやECなどをデータで確認できるようになった。「見える化」したことで、中山さんは「自分以外でも管理しやすくなった。つまり面積を広げていける素地ができた」と語る。
従業員が働きやすい環境づくり
中山さんは軒高が4mに及ぶ23aのハウスを建て、2020年産からキュウリの栽培を始めている。重視したのは従業員が働きやすい環境づくりだ。「軒が高い分だけ換気が良く、作業しやすくなっています」
ハウス内の特徴を挙げれば、さまざまな工夫から、人が重量物を持ち運びしないで済むようになっていることである。入り口の向こうにあるのは管理棟。施設内環境の制御盤や養液の貯留槽などを備えた場所だ。ここから栽培棟に向かって真っすぐなレールが敷いてある。収穫物を詰め込むコンテナを載せる台車を行き来させるためだ。
 ハウスの中央を走るレール
ハウスの中央を走るレール栽培棟に入ると、レールの左右にキュウリが植えてある。片側の直線距離は32m。この数字には意味があるそうだ。「奥からキュウリを収穫していくと、レールのところまで来た時にちょうどコンテナが一杯になるんです」
 イチゴの収穫用の四輪車をキュウリの初期の摘葉に使っている
イチゴの収穫用の四輪車をキュウリの初期の摘葉に使っている畝間で作業をする従業員を見ると、大人の膝上くらいの位置に椅子を搭載した小型の四輪車に座っていた。これはイチゴを収穫するために開発された台車。初期の摘葉に使っている。台車にはコンテナを載せられ、摘んだ葉を入れていく。
別の畝間には昇降台車があった。人が台車に乗って立ち、ハイワイヤーに巻きついたつるを下ろす。立った時に手元にあるレバーを動かせば、車体が前後に移動する。
 つるおろしのための昇降台車
つるおろしのための昇降台車「これもそうです、コーティングさせたんです」
そう言って中山さんが指さした先の鉄骨は白色だった。特殊な塗料で白色にした目的は二つある。一つは光を反射させて作物に当てること。もう一つは鉄骨に熱を持たせないことで、夏場に室温の上昇を抑えることだ。
ちなみにこのハウスでは補助金の申請の関係で土耕を採用しているものの、近いうちに固形培地に変更するという。
「水田にハウスを建てているので、土耕だと場所によって排水性や肥沃度が違う。一方、固形培地は再現性がある。もう一つは作業性を改善。作業環境が悪いところは誰もしたがらないですよね。面積をさらに拡大するための雇用を増やすのであれば、まずはいかに良い作業環境を作れるが経営者には問われてくると思います」
 中山さんが2020年から栽培を始めた軒が高いハウス
中山さんが2020年から栽培を始めた軒が高いハウス中山さんは2022年までに30a強のハウスを増設する予定だ。JA伊万里管内ではその先駆的な取り組みに刺激を受け、キュウリの栽培で環境制御技術を導入する農家が増えている。同JAによると、2021年産では一戸の農家が固形培地を試すという。一人の優れた経営者によって産地に変革の気運が高まっている。
【事例紹介】スマート農業の実践事例
- きゅうりの国内最多反収を達成し、6年目を迎えた「ゆめファーム全農SAGA」が次に目指すこと
- 豪雨を乗り越えてキュウリの反収50トンを実現した、高軒高ハウスでの養液栽培メソッド
- 2024年度に市販化予定のJA阿蘇「いちごの選果ロボット」はどこまできたか
- リーフレタスを露地栽培比で80倍生産できる「ガラス温室」の革命 〜舞台ファーム(仙台市)
- ロボトラでの「協調作業」提案者の思いと大規模化に必要なこと 〜北海道・三浦農場
- 大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場
- 女性だけのドローンチームが農薬散布を担う! 新潟県新発田市の「スマート米」生産者による新たな取り組み
- 野菜の「美味しさ」につなげるためのスマート農業の取り組み〜中池農園(前編)
- ドローン自動飛行&播種で打込条播! アシスト二十一&オプティムが挑む新栽培技術の現状
- 22haの果樹経営で「最も機械化を果たした」青森県のリンゴ農家(前編)
- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)
- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜キュウリで反収44tを達成した佐賀の脱サラ農家(前編)
- 耕地面積の7割が中山間地の大分県で、なぜスマート農業がアツいのか
- 農業法人で穀粒判別器を導入した理由 〜新型は政府備蓄米で利あり
- 大分高専と組んで「芽かきロボット」を開発する菊農家
- スマホひとつで気孔の開度を見える化し灌水に活用する「Happy Quality」の技術
- 目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】
- 「自動飛行ドローン直播技術」をわずか2年で開発できた理由【石川県×オプティムの取り組み 後編】
- 自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】
- 300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート
- スマート米 玄米でクラフトビールを醸造!? 青森でのスマート農業×地産都消の取り組み
- 宇宙から稲の生育を監視し、可変施肥で最高品質の「山田錦」を目指す
- 農業関係者がスマート農業事例を交流するFacebookコミュニティ「明るく楽しく農業ICTを始めよう! スマート農業 事例集」とは?
- 日本のフェノミクス研究は「露地栽培」分野で【ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(後編)】
- 農業における「フェノミクス」の意義とは? ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(前編)
- 糖度と大きさのバランスを制御して“トマトの新基準”を打ち立てたい──AIでつくる高糖度トマト(後編)
- 「経験と勘」に頼らない安定的なトマトの生産を目指して──AIでつくる高糖度トマト(前編)
- 【スマート農業×ドローン】2機同時の自動航行で短時間で農薬散布──DJI×シンジェンタ実証実験レポート
- 画像認識とAIで柑橘の腐敗を選別、防止──愛媛県のスマート農業事例
- 農業ICTやロボットを取り入れるべき農家の規模とは──有限会社フクハラファーム
- ICTで大規模稲作経営の作業時間&効率を改善──有限会社フクハラファーム
- 農家のスマート農業導入を支援する全国組織を──株式会社ヤマザキライス(後編)
- 農家が求める水田センサーを農家自ら企画──株式会社ヤマザキライス(前編)
- inahoのアスパラガス自動収穫ロボットの仕組みとは?──inaho株式会社(前編)
- シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み
- 農業参入企業が共通課題を解決する、北杜市農業企業コンソーシアムの実践<下>
- 中玉トマトで国内トップの反収を上げる最先端園芸施設──北杜市農業企業コンソーシアムの実践<上>
- 農家がグーグルのAIエンジン「Tensor Flow」でキュウリの自動選果を実現
SHARE