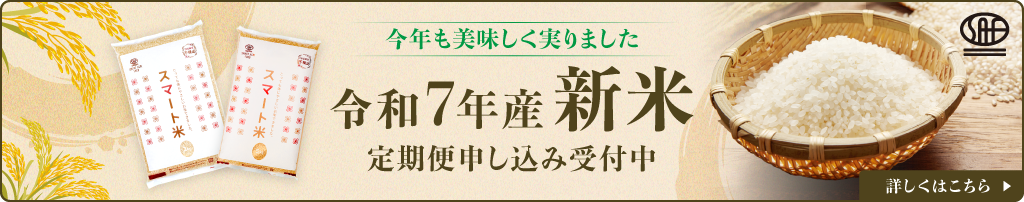あらためて問う、鳥獣害対策
2019年が終わろうとしているなか、東京都内のJR駅前や住宅街でイノシシが出没したというニュースで世間が賑わった。第一報から数日経った現在、本稿を書いているが、イノシシが捕獲されたという話は聞かない。現時点でイノシシは逃げまわっていることがうかがえる。

今回の件は都市部であったから大きく取り上げられたものの、すでに人里に野生動物が出てくる事態は当たり前になりつつあり、我々と彼らとの関係をあらためて問われているように思う。
しかし、実際の被害額はこれより多いと推測される。なぜなら、多くの市町村が集計している被害額は、農業共済への被害申告に基づくからだ。農業共済に加入していない作物の被害分は含まれない。以前取材したある自治体の職員は、農業共済に入っていない被害額についても推計したところ、県に提出した数字の5倍になったと話していた。
仮にこの推計を採用すれば、全国では1000億円近くになる。さらに鳥獣害は農作物が食べられるという物理的な損害だけでなく、被害に遭った農家の営農意欲をそぐから厄介である。
狩猟免許の所持者数を、試しに1990年と2016年で比較すると、確かに29万人から20万人へと3割以上減っている。狩猟者の平均年齢も68歳。環境省も狩猟者を増やすため、2014年5月に鳥獣保護法を改正した。そのおかげか狩猟者は微増している。
ただ肝心なのは、狩猟者の増減ではなく、どれだけ野生動物を捕獲したか、のはず。そこで金額ベースで鳥獣害の6割を占めるシカとイノシシの年間捕獲頭数について、1990年と2016年で比較してみたところ、シカは4万2000頭から57万9300頭と14倍弱、イノシシは7万5000頭から62万400頭と8倍以上。狩猟者の頑張りで年を追うごとに捕獲頭数は大幅に増えてきているのだ。狩猟者の減少と、鳥獣害がおさまらない事態が関係しているとは言えない。
ほかの要因としてオオカミ絶滅説も挙がるが、これは論外である。一般社団法人・日本オオカミ協会によれば、絶滅したのは明治時代の終わりであり、近年の鳥獣害が減らない事態とは無関係と言い切れるためだ。
それよりも注目すべきは、捕獲頭数をはるかに超える勢いで野生動物が増えている点である。環境省は2016年度末、ニホンジカとイノシシについて個体数を推計した。推計値には幅があるものの、真ん中の値を取ると年のニホンジカは272頭で前回調査の11年の261万頭より増えている。1989年と比べればざっと10倍である。イノシシは89万頭で前回調査の88万頭から微増であるものの、1989年と比べると同3.5倍となっている。
なぜこれほどまでに野生動物は増えているのか。そこにはまだ突き詰めるべき要因があるように考える。
その要因とは、農山村で暮らす人たちが、知らないうちにシカやイノシシに食べ物を与えているということが挙げられる。だから、彼らは集落にやって来て農地を荒らすのだ。山の恵みが乏しくなる冬場でも、人里に出向けば、食べ物が豊富に転がっている。それらをあさることで、幼獣の死亡率や初産年齢が低下して、個体数は増えていく。
もし食べ物がなければ、そうした事態になりようがない。だから重要なのは餌をなくすことなのではないか。
専門家たちはかねてよりこの点を強調してきた。だがその認識は十分には浸透せず、先ほど触れたようにいまだに狩猟者の減少やオオカミ絶滅説で片づけられることが多い。
鳥獣害対策の研究で先駆者である奈良県に取材した際、「餌は2種類ある」という説明を受けたことがある。野生動物に食べられたら、人が怒る餌と怒らない餌である。
怒る餌は栽培しているもの。人に売ったり上げたりするための作物なので、作り手は被害に遭わないよう対策をする。しかし、これよりも注意が要るのは、食べられても対策をしない怒らない餌だという。

怒らない餌とは、たとえば廃屋や里山に昔から植えたままで、人間が収穫しなくなった果樹の実や、果樹園の付近で傷物だからと野積みして捨ててある果実や家の前の田んぼに捨ててある生ごみ。収穫後の残さもそうだ。
同センターによる調査では、収穫後に残る外葉などの残さはハクサイで10a当たり5.5t、キャベツで同3.7tほどあることがわかった。また滋賀県の調べでは、稲刈り後に切株から生える二番草(ひこばえ)がシカによって10a当たり50kg食べられていた。いずれも人間にとっては無価値だが、野生動物にとってみれば立派な食料である。ここに盲点があるという。
イノシシも「猪突猛進」という言葉とは裏腹に、実際は小心者の動物だ。集落の周辺部の雑草が刈り払われていたり、里山の間伐がされていたりすれば、見通しが良くて人目に付くので人里に入り込みにくい。だから集落に食べ物があるというのを学習する機会は少なかった。
それが今では、林業の衰退や過疎・高齢化で里山や農地は荒れ、野生動物は人目に触れずに集落に降りてくることが可能となった。そうして段々と集落に食べ物があることを学んでいく。いずれも山の恵みより美味しく、農地やその周辺に行けば量は豊富にある。いまや野生動物にとって集落は楽園となってしまったのだ。
野生動物の集落や農地への侵入を防ぐことも重要となる。ただ、これに関しても知識不足から効果が上がらない方法を取っているところが多い。農家に正しい知識を身につけてもらうためには指導機関の役割が重要だ。一部の自治体は農業試験場内に柵の展示圃を設置。農家や関係団体職員の視察を受け入れて、専門の研究員が電気や金網、トタンなど柵の種類ごとに正しい使い方を説明している。
こうした展示圃がなくても、最近では自治体や研究機関が鳥獣の種類に応じた対策マニュアルを用意している。
指導機関の中には専門家が出張して、防除の仕方を教えてくれるところも出てきた。さらに技術も進歩し、ICTを活用して野生動物の動きを見える化したり、捕獲を省力化したりできるようになっている。これらを利用しながら、農家含めて住民が自主的に学び、行動していくことが被害を防ぐ第一歩である。
1 鳥獣被害の現状と要因 - 農林水産省[PDF]
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/old_manual/old_manual_kiso/data1.pdf

今回の件は都市部であったから大きく取り上げられたものの、すでに人里に野生動物が出てくる事態は当たり前になりつつあり、我々と彼らとの関係をあらためて問われているように思う。
鳥獣害による農林業被害は1000億円近く?
野生動物による農林水産業への影響でいえば、食害は段々と減ってきている。農水省が年末に毎年公表する被害額は、2010年度に過去最悪の239億円を記録したものの、ここ6年は連続して減り続け、2017年度は164億円にまで下がった。しかし、実際の被害額はこれより多いと推測される。なぜなら、多くの市町村が集計している被害額は、農業共済への被害申告に基づくからだ。農業共済に加入していない作物の被害分は含まれない。以前取材したある自治体の職員は、農業共済に入っていない被害額についても推計したところ、県に提出した数字の5倍になったと話していた。
仮にこの推計を採用すれば、全国では1000億円近くになる。さらに鳥獣害は農作物が食べられるという物理的な損害だけでなく、被害に遭った農家の営農意欲をそぐから厄介である。
捕獲数を大幅に上回る野生動物の増加
なぜ鳥獣害はおさまらないのか。よく挙げられるのは狩猟者の減少と高齢化だ。狩猟免許の所持者数を、試しに1990年と2016年で比較すると、確かに29万人から20万人へと3割以上減っている。狩猟者の平均年齢も68歳。環境省も狩猟者を増やすため、2014年5月に鳥獣保護法を改正した。そのおかげか狩猟者は微増している。
ただ肝心なのは、狩猟者の増減ではなく、どれだけ野生動物を捕獲したか、のはず。そこで金額ベースで鳥獣害の6割を占めるシカとイノシシの年間捕獲頭数について、1990年と2016年で比較してみたところ、シカは4万2000頭から57万9300頭と14倍弱、イノシシは7万5000頭から62万400頭と8倍以上。狩猟者の頑張りで年を追うごとに捕獲頭数は大幅に増えてきているのだ。狩猟者の減少と、鳥獣害がおさまらない事態が関係しているとは言えない。
ほかの要因としてオオカミ絶滅説も挙がるが、これは論外である。一般社団法人・日本オオカミ協会によれば、絶滅したのは明治時代の終わりであり、近年の鳥獣害が減らない事態とは無関係と言い切れるためだ。
それよりも注目すべきは、捕獲頭数をはるかに超える勢いで野生動物が増えている点である。環境省は2016年度末、ニホンジカとイノシシについて個体数を推計した。推計値には幅があるものの、真ん中の値を取ると年のニホンジカは272頭で前回調査の11年の261万頭より増えている。1989年と比べればざっと10倍である。イノシシは89万頭で前回調査の88万頭から微増であるものの、1989年と比べると同3.5倍となっている。
なぜこれほどまでに野生動物は増えているのか。そこにはまだ突き詰めるべき要因があるように考える。
その要因とは、農山村で暮らす人たちが、知らないうちにシカやイノシシに食べ物を与えているということが挙げられる。だから、彼らは集落にやって来て農地を荒らすのだ。山の恵みが乏しくなる冬場でも、人里に出向けば、食べ物が豊富に転がっている。それらをあさることで、幼獣の死亡率や初産年齢が低下して、個体数は増えていく。
もし食べ物がなければ、そうした事態になりようがない。だから重要なのは餌をなくすことなのではないか。
専門家たちはかねてよりこの点を強調してきた。だがその認識は十分には浸透せず、先ほど触れたようにいまだに狩猟者の減少やオオカミ絶滅説で片づけられることが多い。
餌とは何か
ここで問いたい。「餌とは何か」。鳥獣害対策の研究で先駆者である奈良県に取材した際、「餌は2種類ある」という説明を受けたことがある。野生動物に食べられたら、人が怒る餌と怒らない餌である。
怒る餌は栽培しているもの。人に売ったり上げたりするための作物なので、作り手は被害に遭わないよう対策をする。しかし、これよりも注意が要るのは、食べられても対策をしない怒らない餌だという。

怒らない餌とは、たとえば廃屋や里山に昔から植えたままで、人間が収穫しなくなった果樹の実や、果樹園の付近で傷物だからと野積みして捨ててある果実や家の前の田んぼに捨ててある生ごみ。収穫後の残さもそうだ。
同センターによる調査では、収穫後に残る外葉などの残さはハクサイで10a当たり5.5t、キャベツで同3.7tほどあることがわかった。また滋賀県の調べでは、稲刈り後に切株から生える二番草(ひこばえ)がシカによって10a当たり50kg食べられていた。いずれも人間にとっては無価値だが、野生動物にとってみれば立派な食料である。ここに盲点があるという。
「猪突猛進」の嘘
そもそも里山で人間が活発に活動をしていた時代には、野生動物は集落には容易に近づけなかった。野生動物の多くは臆病だからである。イノシシも「猪突猛進」という言葉とは裏腹に、実際は小心者の動物だ。集落の周辺部の雑草が刈り払われていたり、里山の間伐がされていたりすれば、見通しが良くて人目に付くので人里に入り込みにくい。だから集落に食べ物があるというのを学習する機会は少なかった。
それが今では、林業の衰退や過疎・高齢化で里山や農地は荒れ、野生動物は人目に触れずに集落に降りてくることが可能となった。そうして段々と集落に食べ物があることを学んでいく。いずれも山の恵みより美味しく、農地やその周辺に行けば量は豊富にある。いまや野生動物にとって集落は楽園となってしまったのだ。
農家が正しい知識を身につける
農山村を野生動物の住処としないために、まずやるべきは正しい知識を身につけることである。対策の主役である農家が餌とは何かを学び、ひとつひとつ対策をとっていくことが肝心だ。野生動物の集落や農地への侵入を防ぐことも重要となる。ただ、これに関しても知識不足から効果が上がらない方法を取っているところが多い。農家に正しい知識を身につけてもらうためには指導機関の役割が重要だ。一部の自治体は農業試験場内に柵の展示圃を設置。農家や関係団体職員の視察を受け入れて、専門の研究員が電気や金網、トタンなど柵の種類ごとに正しい使い方を説明している。
こうした展示圃がなくても、最近では自治体や研究機関が鳥獣の種類に応じた対策マニュアルを用意している。
指導機関の中には専門家が出張して、防除の仕方を教えてくれるところも出てきた。さらに技術も進歩し、ICTを活用して野生動物の動きを見える化したり、捕獲を省力化したりできるようになっている。これらを利用しながら、農家含めて住民が自主的に学び、行動していくことが被害を防ぐ第一歩である。
1 鳥獣被害の現状と要因 - 農林水産省[PDF]
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/old_manual/old_manual_kiso/data1.pdf
【コラム】窪田新之助のスマート農業コラム
- 現状の輸出統計に意味はあるのか【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 秋田県がスマート農業で実現する、コメから小菊への転換と生産規模拡大(後編)
- 秋田県がスマート農業で実現する、コメから小菊への転換と生産規模拡大(前編)
- 経済事業の立て直しに迫られるJA【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 種子法廃止のから騒ぎ【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 「科学者の心」を持って自ら考えてほしい 〜遺伝子組み換え技術の議論【窪田新之助のスマート農業コラム】
- データ栽培管理により反収増を実現したゆめファームの今年の成果【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 日本の食料基地・北海道が直面する物流問題の憂うつ【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 従業員の定着を図る「作業分解」という考え方【窪田新之助のスマート農業コラム】
- パレットを返却しない青果物流通の常識を変えよう【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 青果物流の改善にパレットとフレコンの普及を【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 麦わらのストローで脱プラ。農家らがプロジェクトを始動【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 資本主義の変容とこれからの農業 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- キュウリの反収アップに連なる「土は根を生やす培地」という考え
- 年収1000万円を捨てた脱サラ農家の夢
- 集落営農法人は「3階建て方式」の時代へ
- バリューチェーン構築のためのデータ利用を【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 収量を高める根の力 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 10aの収入試算が18万円となった「みのりのちから」
- 「あまおう」増産の鍵はどこにある!? 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- キュウリ農家によるAI自動選別機の最新版【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 1万5000俵のコメを評価する「頭脳」【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 農業ベンチャーによる生産管理と物流制御を可能にしたシステムとは?〜農業総合研究所【中編】
- 国内最大の事業協同組合が求めた小麦「みのりのちから」の魅力と可能性
- トラクターと作業機のデータ連携により、相関関係が見える農業の実現へ
- 小麦の品質評価基準はなぜ変わるのか
- あらためて問う、鳥獣害対策
- 東京で生産量日本一の農産物? 新宿で広がる「内藤とうがらし」
- 「減反政策は終わった」という暴論
- 農作物の体調を“リアルタイム”で診断する新技術とは?
- 農業に転用したい自動運転技術「LiDAR」とは?【窪田新之助の農業コラム】
- 米穀店も稲作経営を始める時代【窪田新之助の農業コラム】
- 醸造用ブドウの品質向上にスマート農業を活かす「信州ワインバレー構想」〜長野県高山村の例
- 「Kintone」による地域運営 ──島根県益田市【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 農家目線で開発された開水路用の自動給水機の現地実証 〜横田農場の例
- センサーの向こうにある野菜の本質とは何か──NKアグリの例<後編>
- ニンジンの機能性はいつ高まるのか? ──NKアグリの例<前編>
- 農家の負担を減らす最新農業用ロボット【窪田新之助のスマート農業コラム】
- スマート農業の先にあるもの【窪田新之助のスマート農業コラム】
- いまなぜスマート農業なのか【窪田新之助のスマート農業コラム】
SHARE