トラクターと作業機のデータ連携により、相関関係が見える農業の実現へ
トラクターと作業機はデータの宝庫だ。以前の連載でもご紹介したISOBUSで利用するデータはそのごくわずかに過ぎない。両者では相当量のデータの収集や通信がなされているものの、蓄積されずに破棄されているのが現状である。
「もったいないですよね」。こう語るのは農研機構・農業技術革新工学研究センターの自律移動体ユニット長の西脇健太郎氏。
西脇氏はそうした捨てられている膨大なデータを収集する方法を開発し、営農に役立てることを目指している。
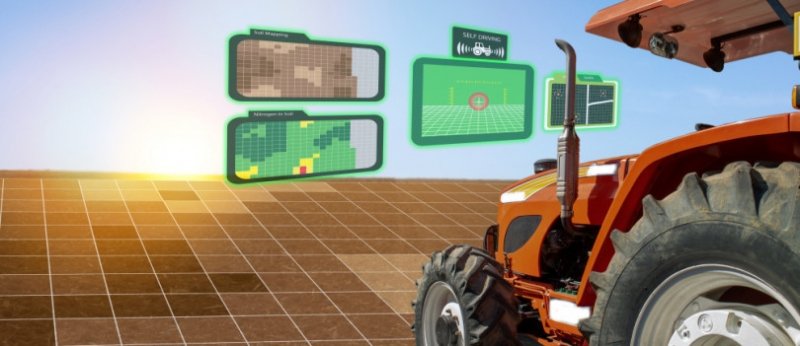
トラクターに装着する作業機の一つに「サブソイラ」(Sub Soiler)がある。土の中に突き入れて進むことで、下層部にあるすき床層やトラクターが踏み固めた重みでできた硬い層に亀裂を入れ、水の通りや排水を良くする効果が期待できる。
途中で石のようにあまりに硬い物が眠っていれば、そのまま突き進もうとすると破損する恐れがあるので、その場合はサブソイラを一瞬引き上げる。障害物を回避したら、すぐさま元の深さに戻す。
そうしたサブソイラを上下した動きをデータとして収集。GIS(地理情報システム)を用いて畑1枚の中でサブソイラの高さに応じて色分けした。
 トラクターと作業機とのデータ連携の事例の一つ。ISOBUS仕様のトラクターについている専用のモニター。タッチパネルで肥料を散布する幅や量を調整できるようになっている。
トラクターと作業機とのデータ連携の事例の一つ。ISOBUS仕様のトラクターについている専用のモニター。タッチパネルで肥料を散布する幅や量を調整できるようになっている。
同時に用意したのは、衛星データを基にその畑での作物の生育の状態を解析し、その状態に応じてGISで色分けした地図。両者を照合して気づいたのは、サブソイラが浅く入ったエリアの一部で作物の生育が良くなかったという事実だ。その場合、施肥量を多くするといった対応をすればいい。
一方、サブソイラが深く入っていても、生育が悪かったエリアもある。そこには別の原因が考えられる。西脇さんはこうしたデータを収集して、AIに解析させたら「面白くなるのではないか」とみている。
ここで押さえておきたいのは、ビッグデータの時代には因果関係から相関関係に主軸が移るということだ。膨大なデータと高度な計算処理能力があれば、最も相関の高い事柄を特定できてしまうのだ。
人間は知的好奇心が旺盛だから、物事の仕組みを解き明かすのに因果関係を追い求めてしまいがち。あらゆる結果には必ず原因があると考えるのだ。
ただ、因果関係を追究するのは厄介だ。追究したところで原因などないかもしれない。相関関係の特定に必要なデータがそろうなら、AIを使うに越したことはない。
「燃料消費のデータも収集できるので、そこから作業日誌をつけることを自動化できるのではないでしょうか。どの機械がいつ、どの圃場に、いつからいつまで、どんな作業をしていたというデータが簡単に取れる。その時に燃料をどれくらい消費し、走行時間と休憩時間はどれくらいだったか。さらには、作業機の上げ下げの状態はどうだったか、圃場の中の土壌が硬いか柔らかいか、タイヤの空回りが多いか少ないか等も……。
農家は作業をしていればその一部は覚えているんですが、面積が拡大して圃場が多くなると、頭から抜けていってしまう。そうしたデータを自動的に収集できたら、収量や品質の向上にとって面白いことがわかるようになると思います」
人の代わりにロボットが農作業の多くをこなすようになれば、農機に関するデータの価値は高まる。その時代に向けて今後の研究の発展に期待したい。
農業技術革新工学研究センター | 農研機構
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/iam/
「もったいないですよね」。こう語るのは農研機構・農業技術革新工学研究センターの自律移動体ユニット長の西脇健太郎氏。
西脇氏はそうした捨てられている膨大なデータを収集する方法を開発し、営農に役立てることを目指している。
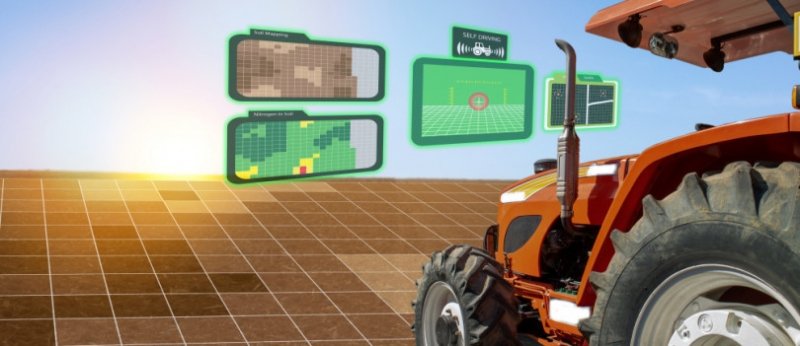
すべてのデータを収集・分析して見えること
そのための試みとして、まずは関連するデータをすべて収集した。そのデータの一部を分析すると、例えば次のようなことがわかってきた。トラクターに装着する作業機の一つに「サブソイラ」(Sub Soiler)がある。土の中に突き入れて進むことで、下層部にあるすき床層やトラクターが踏み固めた重みでできた硬い層に亀裂を入れ、水の通りや排水を良くする効果が期待できる。
途中で石のようにあまりに硬い物が眠っていれば、そのまま突き進もうとすると破損する恐れがあるので、その場合はサブソイラを一瞬引き上げる。障害物を回避したら、すぐさま元の深さに戻す。
そうしたサブソイラを上下した動きをデータとして収集。GIS(地理情報システム)を用いて畑1枚の中でサブソイラの高さに応じて色分けした。
 トラクターと作業機とのデータ連携の事例の一つ。ISOBUS仕様のトラクターについている専用のモニター。タッチパネルで肥料を散布する幅や量を調整できるようになっている。
トラクターと作業機とのデータ連携の事例の一つ。ISOBUS仕様のトラクターについている専用のモニター。タッチパネルで肥料を散布する幅や量を調整できるようになっている。同時に用意したのは、衛星データを基にその畑での作物の生育の状態を解析し、その状態に応じてGISで色分けした地図。両者を照合して気づいたのは、サブソイラが浅く入ったエリアの一部で作物の生育が良くなかったという事実だ。その場合、施肥量を多くするといった対応をすればいい。
一方、サブソイラが深く入っていても、生育が悪かったエリアもある。そこには別の原因が考えられる。西脇さんはこうしたデータを収集して、AIに解析させたら「面白くなるのではないか」とみている。
ここで押さえておきたいのは、ビッグデータの時代には因果関係から相関関係に主軸が移るということだ。膨大なデータと高度な計算処理能力があれば、最も相関の高い事柄を特定できてしまうのだ。
人間は知的好奇心が旺盛だから、物事の仕組みを解き明かすのに因果関係を追い求めてしまいがち。あらゆる結果には必ず原因があると考えるのだ。
ただ、因果関係を追究するのは厄介だ。追究したところで原因などないかもしれない。相関関係の特定に必要なデータがそろうなら、AIを使うに越したことはない。
データを収量と品質の向上に役立てる
トラクターと作業機のデータを解析することで、ほかにどんなことがわかるのだろうか。西脇さんはこんな夢を膨らませる。「燃料消費のデータも収集できるので、そこから作業日誌をつけることを自動化できるのではないでしょうか。どの機械がいつ、どの圃場に、いつからいつまで、どんな作業をしていたというデータが簡単に取れる。その時に燃料をどれくらい消費し、走行時間と休憩時間はどれくらいだったか。さらには、作業機の上げ下げの状態はどうだったか、圃場の中の土壌が硬いか柔らかいか、タイヤの空回りが多いか少ないか等も……。
農家は作業をしていればその一部は覚えているんですが、面積が拡大して圃場が多くなると、頭から抜けていってしまう。そうしたデータを自動的に収集できたら、収量や品質の向上にとって面白いことがわかるようになると思います」
人の代わりにロボットが農作業の多くをこなすようになれば、農機に関するデータの価値は高まる。その時代に向けて今後の研究の発展に期待したい。
農業技術革新工学研究センター | 農研機構
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/iam/
【コラム】窪田新之助のスマート農業コラム
- 現状の輸出統計に意味はあるのか【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 秋田県がスマート農業で実現する、コメから小菊への転換と生産規模拡大(後編)
- 秋田県がスマート農業で実現する、コメから小菊への転換と生産規模拡大(前編)
- 経済事業の立て直しに迫られるJA【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 種子法廃止のから騒ぎ【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 「科学者の心」を持って自ら考えてほしい 〜遺伝子組み換え技術の議論【窪田新之助のスマート農業コラム】
- データ栽培管理により反収増を実現したゆめファームの今年の成果【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 日本の食料基地・北海道が直面する物流問題の憂うつ【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 従業員の定着を図る「作業分解」という考え方【窪田新之助のスマート農業コラム】
- パレットを返却しない青果物流通の常識を変えよう【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 青果物流の改善にパレットとフレコンの普及を【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 麦わらのストローで脱プラ。農家らがプロジェクトを始動【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 資本主義の変容とこれからの農業 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- キュウリの反収アップに連なる「土は根を生やす培地」という考え
- 年収1000万円を捨てた脱サラ農家の夢
- 集落営農法人は「3階建て方式」の時代へ
- バリューチェーン構築のためのデータ利用を【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 収量を高める根の力 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 10aの収入試算が18万円となった「みのりのちから」
- 「あまおう」増産の鍵はどこにある!? 【窪田新之助のスマート農業コラム】
- キュウリ農家によるAI自動選別機の最新版【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 1万5000俵のコメを評価する「頭脳」【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 農業ベンチャーによる生産管理と物流制御を可能にしたシステムとは?〜農業総合研究所【中編】
- 国内最大の事業協同組合が求めた小麦「みのりのちから」の魅力と可能性
- トラクターと作業機のデータ連携により、相関関係が見える農業の実現へ
- 小麦の品質評価基準はなぜ変わるのか
- あらためて問う、鳥獣害対策
- 東京で生産量日本一の農産物? 新宿で広がる「内藤とうがらし」
- 「減反政策は終わった」という暴論
- 農作物の体調を“リアルタイム”で診断する新技術とは?
- 農業に転用したい自動運転技術「LiDAR」とは?【窪田新之助の農業コラム】
- 米穀店も稲作経営を始める時代【窪田新之助の農業コラム】
- 醸造用ブドウの品質向上にスマート農業を活かす「信州ワインバレー構想」〜長野県高山村の例
- 「Kintone」による地域運営 ──島根県益田市【窪田新之助のスマート農業コラム】
- 農家目線で開発された開水路用の自動給水機の現地実証 〜横田農場の例
- センサーの向こうにある野菜の本質とは何か──NKアグリの例<後編>
- ニンジンの機能性はいつ高まるのか? ──NKアグリの例<前編>
- 農家の負担を減らす最新農業用ロボット【窪田新之助のスマート農業コラム】
- スマート農業の先にあるもの【窪田新之助のスマート農業コラム】
- いまなぜスマート農業なのか【窪田新之助のスマート農業コラム】
SHARE
















































